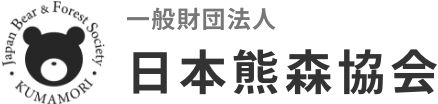お知らせ
2024/06/17
くまもりNews環境省が現在、「鳥獣保護管理法第38条の改正に関する対応方針(案)」のパブコメを募集しています。みなさんの声を届けてください。
ただし、前回の環境省パブコメで、賛成意見9、反対意見440にもかかわらず、環境省は原案通り、捕殺強化をめざす指定管理鳥獣にクマ類を指定しましたから、また同様の結果になることが予想されます。しかし、捕殺優先ではなく、棲み分けて共存を望む国民の声を、環境省に送り続けることが大切です。
今回は、前回の「クマを指定管理鳥獣にする」という環境省だけで決めることができる規則改正ではなく、国会議員の審議が必要な法改正へ向けた方針案です。選挙区の国会議員にも訴えていただきたいです。
<意見提出方法>
意見募集要領と「鳥獣保護管理法第38条の改正に関する対応方針(案)」は、以下をご覧になってください。
https://www.env.go.jp/press/press_03249.html
<どのような法改正なのか>
現在、警察官の発砲命令がなければ住居集合地域等での鳥獣への発砲はできないことになっていますが、今回の改正案では、クマ類が住居集合地域等に出てきた場合、迅速に事態を収束させるため、警察官の発砲命令がなくても、行政の判断で銃猟者が発砲できるようにするそうです。
<熊森の見解>
原則は、棲み分けて共存し、市街地への侵入を事前に防ぎ、住居集合地域等にでてきた場合も、捕殺でない対応をとるべき。どうしても殺処分するしかない場合のみ、銃やクマの動きに詳しい専門員が発砲許可を降ろすようにすべきで、行政専門員の育成が急務。環境省の今回の対応方針については、大幅な修正を求めたい。
(理由)
- 住居集合地域等にクマが出てきても殺さずに解決できるケースは実に多く、実際、殺さない対応が各地で実施されている。しかし、今回の方針案では、早期解決のためとして、すばやくクマを銃で殺してしまうことしか書かれていないから。
- 箱罠で捕獲したクマを安全に山に返すことは、いくつもの県で普通に多く行われているのに、今回の方針案では、箱罠に入ったクマを、銃で速やかに殺すことしか書かれていないから。
- 発砲事故が起きた時の責任や補償がどうなるのか全く明記されていないから。
以下はパブコメ例です。ご参考になさってください。
意見要約(100字まで)
対応方針の大幅な修正を求める。住居集合地域等にクマ類が出てきた場合、まず、出没原因や目的を探り、それに合わせて人身事故が起きないよう最大限配慮しながら、可能な限り捕殺でない対応を行うとの内容にすべき。
意見内容(2000字まで)
私たちは、環境省に日本の自然や野生生物を守ってほしいと願っています。
しかし、環境大臣省が、自然が破壊されたり汚染されたりする知床での再エネ事業計画について、やむおえないと答弁したり、クマ類に関してはパブリックコメントの結果が賛成9名、反対440名だったにもかかわらず、絶滅寸前であと20頭前後しか生息しない四国のクマ以外は、全て原案通り捕殺強化対象の指定管理鳥獣に指定してしまいました。
環境省は、生物の多様性を守るというのが、環境省の本来の職務であり、この立場にたって計画を立てるべきです。
今回の環境省の対応方針には、但し書きはついているものの、クマ類を殺すことの記述しかなく、「居住地に現れたクマは速やかに捕殺」の方針転換が明白であり、逃がしたり、放獣したりできるものは山に返すという、野生動物との共存のための原則が欠落しており、倫理的にも問題です。
この対応方針では、殺さなくてもよいクマまで安直に殺す流れを作ってしまいます。
殺さない対応法が多く記載された対応方針となるよう、全面的な書き直しを求ます。
環境省は検討会委員に、野生生物の声を代弁できる自然保護団体や動物愛護団体を入れることが必要です。
(修正内容)
1 棲み分けてクマと共存するという理念を示し、住居集合地域等にクマが出てきた場合も、可能な限り殺さないで対応する。クマが自分ひとりで山に帰れるような環境を作ってやったり、一旦罠で人が捕獲してから山に運んで放獣したりするなど、捕殺以外の方法も示すべき。
くまもりブログ「事故0捕殺0ベテラン行政担当者のクマ対応」参照
https://kumamori.org/topics/kumamori-news/20240520-1.html
https://kumamori.org/topics/kumamori-news/20240520-2.html
https://kumamori.org/topics/kumamori-news/20240520-3.html
2 クマ類が建物に立てこもった場合とあるが、逃げ込んだだけで、人が離れ、山へ帰るルートを確保してやると、逃がせる場合も多くある。早期捕獲をめざしての発砲より、山へ返すことができるクマは、時間をかけても返すべき。
3 箱罠に捕獲した後、止めさしとしての発砲しか考えていないが、捕獲後は山に放獣することを考えるべき。
4 専門家の養成は、大いに必要で大賛成。ただし、捕殺の専門家ではなく、野外での実際のクマの行動がわかり、可能な限り殺さないでクマ類に対応できる専門家であること。かつ、地元の人たちのために被害防除を指導したり実施したりできる専門家でもあること。
5 クマの目撃が多発するようになってきた過疎化・高齢化地域では、山のえさ場や生息地を再生したり、犬の活用や電気柵、有刺鉄線の設置、クマの潜み場の草刈りなどの被害防除対策を、国、地方行政、猟師、自然保護団体など、都市市民も含めて官民一体となって行い、クマが山から出て来ないようにすることがクマ対策の第一歩であることを明記すべき。
6 集合居住地域等に現れたクマを刺激してクマをパニックに陥らせないように、メディアや第三者を遠ざけて静かにしてもらう必要はあるが、排除するという方針は安易な捕殺を国民の目から隠そうとすることにつながり望ましくない。
最新のお知らせ
-
2026/02/26 くまもりNews
㊗️静岡県支部が約20年ぶりに再結成されました -
2026/02/26 イベント
📢 環境省ガイドライン(クマ編)改定案 オンライン勉強会 緊急開催!今後のクマ対策はどう変わるのか -
2026/02/24 くまもりNews
🐻和歌山県・生石高原 ツキノワグマの太郎 -
2026/02/20 イベント
3月21日 いのちかがやく水源の森をこどもたちへ in 京都
ページトップに戻る