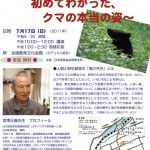ホーム > アーカイブ > 2011-07
2011-07
2011年7月17日(日)宮澤正義先生講演会(関東支部主催)
宮澤正義先生講演会
7月17日(日)
9:30 開場
10:00~12:00 講演
13:00~14:30 質疑応答
所「エデュカス東京」教育文化会館地下会議室
(市ヶ谷駅徒歩5分 日テレ通り沿い)
※先着100名、参加費無料
●人間と野生動物の「真の共存」とは
私のクマとの関わりは、研究のための共同生活であったが、わたし はクマを育てることによって、いろいろなことを学んだ。 最近、野生鳥獣との共生という言葉が多用されている。いま一度、 共生という言葉の意味について、人間は考えるべきだ。…「住み分け」「食 い分け」は、自然界が律する鉄の掟である。
すべての命は、この鉄の 掟に従うことで生存権を手にしてきたのだ。いま、自然は、そのこと を肝に銘じて行動するよう人間に求めている。すべての命は、地球に 生きる役割を与えられている。人間が勝手に他の生物種を絶滅におい やることなど許されないはずだ。〔『家族になった10頭のクマ』より〕
申し込み・問い合わせ先
申し込みフォーム
日本熊森協会関東支部(中村)
kanto.kumamori@gmail.com
TEL/FAX 046-825-7028
関東支部長より
「宮澤先生はくまもり協会の最初の顧問になられた先生で、本当のクマの姿を教えてくださいました。この講演会では知っているようで知らないツキノワグマについて、すべてのことを教 えていただこうと思っています。宮澤先生のお話を聞いて、クマを守っていくことの大切さをもう一度認識できるような会にしたいと思います。質疑応答の時間も長くとってありますので、疑問を持っていらしてください。」
3/14 兵庫県野生動物保護管理運営協議会での森山会長の質問と当局の答え
《3/14 兵庫県野生動物保護管理運営協議会での森山会長の質問と当局の答え》
3月14日、兵庫県野生動物保護管理運営協議会が、兵庫県民会館303号室で開かれました。
上写真は協議会委員のメンバー
下写真の委員と向かい合って座っておられる方々は兵庫県庁担当者と兵庫県森林動物研究センターの研究者たち(兵庫県立大学)や専門員たち(県庁職員)からなる当局
森山会長発言要旨 シカ問題
■地元ではシカ問題が深刻であることはわかりますが、山から出て来たシカを捕殺して解決するというのはあくまで対症療法であると思います。大量に捕殺してもシカが減らないので獲り続けるということですが、どうしてシカが最近そんな状態になったのですか。原因が分からないと本当の対策を立てられないのではないかと思います。
●原因諸説として以下の3つがよく挙げられています。
①シカが増えだしたのはオオカミが絶滅したから⇒しかし、オオカミが絶滅したのは明治ですから、今の事態とは関係がないと思います。
②猟友会員が減ったから⇒猟友会員は1970年頃が最大でした。以前は今より少なかったけれど、シカは人間の所には出てきていませんでした。よって、この説も説明がつきません。
③地球温暖化で雪が減ったからシカの生き残りが増えた⇒では、今年すごく雪が多かったので、シカはどっと減ったんでしょうか?
シカの世界にいったい何が起きているのか、県としての見解を教えてほしいです。
(研究員の答え)
県の見解としては、毎年シカの自然環境の状態が良くて、シカの妊娠率、栄養状態なんかも見てますけど、非常に好調です。妊娠率15%~18%くらいの自然増加で、自然に増加するもんですから、獲らなければやはり自然に増加していく。シカの世界では毎年15%以上増えていくという状況が今起こっているという風に考えています。
森山会長発言要旨 クマ問題
■先ほどの委員が、クマ数は回復しているとして個体数調整の開始を提案されましたが、私はとても危険だと危機感を持ちました。
クマというのは日本最大の動物です。人間活動がここまで大きくなった今、人との共存は大変です。ワシントン条約でクマが保護対象獣に指定されているのは、よほど人が気をつけないと絶滅させてしまう、現にヨーロッパなどでは各地で絶滅させてしまったという経緯があるからです。クマは繁殖力も弱いので、慎重に取り扱うべきだろうと思います。
私たちは去年2010年の大凶作は普通の凶作と思っていません。日本の山で2004年2006年に引き続き、動物が棲めないような奥山の実りゼロという異常事態が起こったのです。たとえば、去年、山火事のように広がったナラ枯れによって、クマは主なエサであるミズナラを大量に失いました。原因はわかりませんが、自然界で人間活動による異変が起きている。それによってクマが生きられなくなって山から出て来た。
去年の夏から秋、冬にかけて、兵庫県でも驚くほど多数のクマが山から出てきました。兵庫県は蜂の巣にクマが付いたとき以外はハチミツを使ってクマを獲らないと決まってるはずなのに、去年現地を巡回していましたら、結構捕獲誘引剤としてハチミツが使用されていました。
こういうことをすると、クマが遠くからも集まってくるため、目撃数や捕獲数がどっと増えるのはあたりまえです。先ほど発表された兵庫県内のクマ生息推定数は、目撃数と捕獲数を2大パラメーターとして算出したという事ですから、それによって推定生息数を出すと、実際よりすごく多くなってしまうんじゃないかと思います。
先ほどからの県担当者の話は、人間の視点だけに偏っています。集落の柿の木を伐ってしまったらクマが来なくなるから伐れと言われますが、クマにしたら山のドングリはなし、カキやクリもなしでは、食べる物がなくて生き残れない。餌を探して町中に入っていくしかない。本当にこんな対応が正しいのかどうか、もっともっと議論をしてもらいたい。私たちは去年の秋に危機感を感じて、地元農林事務所に電話をして、担当者に状況を聞こうとしましたが、「忙しい。1分1秒の余裕もありません。」と断られました。県庁に緊急協議会の開催を要望しましたが、これも断られました。
私たちの祖先はほんとに生き物にやさしかったので、猟友会の方でもよく「三つ熊は獲るな」とか「子グマはよう撃たん」とかそういう人がいっぱいいました。だから、今も日本にまだクマが生き残っているのです。去年の兵庫県行政は、親子グマでも獲るし、子グマも7頭殺しています。こんな方向に日本文明を変えていっていいのだろうか?と思います。
いろんな生き物がいてクマがいて、初めてこんこんと水が湧き出す豊かな森が維持形成されます。そのお蔭で農業用水が得られるのです。動物たちに、この国で一緒に生きようというやさしい気持ちを失ったなら、日本文明は滅びるんじゃないかと思います。
去年同じように滋賀県や岡山県でもクマの目撃数がとても多かったわけですけども、滋賀県は9頭しか捕殺していません。岡山県の捕殺数はゼロです。2004年と2006年の山の実りゼロという大凶作年、兵庫県で捕殺されたクマ数は、7頭と4頭でした。去年は70頭捕殺、いくらなんでもこんなに殺してしまっていいのでしょうか。
昨年、私たちはせっせと地元を訪問しました。地元でも、「これくらいのことでクマを殺さなくてもいいんじゃないか」という声がすごくたくさんありました。他府県でも、多くの集落で、「今年の山は異常だから、柿はクマにあげよう」と、クマをみんなで見守ったところがたくさんありました。これこそが日本文化であって、こういう考え方があるからこそ、日本に豊かな森が残ったし、いろんな動物も残ったのだと思います。、
このような原因不明の異変が山で起きている時に、出て来たクマは全部捕殺してしまえとか、個体数調整を始めようというようなことを、人間がする権利はあるのだろうか。人間が、自然界をここまでいじっていいのだろうかと思います。県民は、去年兵庫県が70頭も絶滅危惧種のクマを有害駆除したことを知りません。マスコミに発表していただきたいし、私たち自然保護団体にも情報を流して欲しい。県だけで暴走しないで、もっといろんな意見を聞いていただきたいと思います。
司会者は、いつものことながら、ありがとうございましたとお礼を言って、会長の発言は議題に取り上げず、次の話題に移ってしまいました。兵庫県では自然保護団体が協議会に参加していると言っても、これでは形だけの参加ですね。
7月8日 熊森と兵庫県野生動物担当者の意見交換会
昨年度の兵庫県のクマ大量捕殺に危機感を感じる県民有志の会(熊森会員+非会員)が、今年になってから何度も県担当者に面会を申し込みましたが、忙しいという事で会っていただけませんでした。そのことを知ったある県会議員が双方を引き合わせようとご尽力くださり、やっと1時間の面会がかないました。
県からは、自然環境課課長様ら8名の方々がご出席くださいました。お忙しい中、本当にありがとうございました。この日の話し合いで、熊森と県の、森や動物に関する現状認識のどこが違っているのか、大分はっきりしてきました。
この日の話し合いでは、討論して歩み寄る所までいきませんでした。1時間ではとても足りなかったので、今後、定期的に、県と熊森などの市民団体との意見交換会を持つことを提案しましたが、職員が3割も削減され忙しいので無理と断られました。文書なら受けるという事でした。3割も人員を削減されたら大変だろうと思いました。
第16回 貸し切りバスで行く 夏休みくまもり原生林ツアー 参加者大募集!
- 2011-07-07 (木)
- お知らせ(参加者募集) | 企画・イベント

今年も熊森本部は、恒例、大好評のくまもり夏休み原生林ツアーを実施いたします!子供たちの夏休み自由研究にも最適!ブナ・ミズナラの巨木が立ち並び、滋養あふれる水が一年中湧き出している本当の森に、年1回は入りませんか。
途中、たつの動物園に寄って、熊森要望で広く大きくなった獣舎のクマさんたちに御対面。また道中、人工林内にも入ります。バスの中は、最新の森林生態学講座。盛りだくさんのプログラムをお楽しみください。
行き先:岡山県西粟倉村の若杉天然林。
クマ・サル・シカ・イノシシ・アライグマなどの研究者をめざしておられる方はご連絡を
- 2011-07-04 (月)
- _野生動物保全
クマ・サル・シカ・イノシシ・アライグマなどの動物を、かれらに負担をかけることなく痕跡などで研究しようとされている方がおられたら、ご連絡ください。わたしたちは、原子力資料情報室の野生動物バージョンを作っていこうと考えています。ポストドクター歓迎。
「一切の鳥獣殺生を認めない考え方は問題で、秩序ある狩猟が必要」との提言に、狩猟団体と環境団体が合意
- 2011-07-03 (日)
- _野生動物保全
農作物の鳥獣被害は全国で年間200億円に上る。また、知床(北海道)をはじめ全国で貴重な植物が食い荒らされる一方、特定の動物が増え、生態系のバランスも崩れてきた。しかし、ハンターの減少や捕獲に対する社会的な理解不足で、害獣対策は遅れてきた。
ハンターの全国組織「大日本猟友会」は昨年11月、日本自然保護協会など国内を代表する環境団体、学識経験者、長野県などでつくる円卓会議を発足、5回にわたり議論した。
その結果、日本では動物愛護の思想から殺生を忌避する考えがあるが、過度な保護や捕獲態勢の遅れが農林業被害の増加、生物多様性の劣化を招いたと 指摘し、日本人と野生動物との関係は転換期にあると分析。増えすぎた動物の命を奪う意味を理解するための教育の充実▽捕獲の担い手確保▽捕獲した鳥獣の食 料や毛皮への活用--などを求めた。さらに、食肉などを市場に流通させることは、捕獲に必要な経費の確保や山村の活性化、食料自給率の向上につながると指 摘。提言には、参考図書や食材の入手先も盛り込んだ。
梶座長は「このままでは自然も人の暮らしも守られない。早急に行動しなければならない」と話す。環境省鳥獣保護業務室は「提言を尊重し、政策を充実させたい」としている。
兵庫県氷ノ山中腹で、学術用クマ捕獲罠発見
- 2011-07-03 (日)
- _野生動物保全
迷彩模様のドラム缶檻発見(兵庫県氷ノ山)
兵庫県は去年、熊森の度重なるクマ救命願いも無視し、これまでのクマ保護政策を一転させて、わかっているだけでも70頭のクマを有害捕殺しました。確かに奥山の実り大凶作年の去年、たくさんのクマが食料を求めて山から出てきましたが、隣接する岡山県のように1頭も殺さずに対応した県もあるのです。交通事故死12頭を加えると、兵庫県は昨年度、82頭という大量のクマを失いました。(以前当協会ブログにて既報)
兵庫県内にまだクマが残っているだろうか。熊森本部は、クマ生息の痕跡を求めて兵庫県内のクマ生息地を次々と回っていますが、ほとんど見つかりません。兵庫の最高峰、氷ノ山の中腹にあるスギの人工林前を通りかかった時、クマ捕獲用ドラム缶檻が目に付き、そばまで見に行きました。学術研究用として、兵庫県の森林動物研究センターが、今年の5月から来年の5月まで、1年間の間の捕獲許可を取ったものでした。
去年、あんなに大量のクマを獲って解剖したというのに、兵庫県立大学の研究者たちはまだクマを獲りたいのか。何のためか。獲ってどうするのか。クマの論文を書くには、クマのサンプルが多いほどいいのでしょうが、こんなクマ生息地のど真ん中に罠を仕掛ければ、母グマは安心して子グマを育てられません。熊森は、野のものに手を付ける研究は、人間の倫理上、すべきでないという考えです。
人工林の中に檻を仕掛けたのは、移動させやすいからでしょう。森林動物研究センターに聞きたいことがいくつも出てきました。同じ県民なのに、わたしたちのような市民団体には情報が全く入ってきません。文書で問い合わせてみようと思います。
池ノ谷トラスト地のボーリング調査、本部からの要請で取りやめ
- 2011-07-01 (金)
- 公益財団法人奥山保全トラスト
6月22日の中日新聞の記事は、本部にとって寝耳に水でびっくりしました。モリアオガエル産卵の時期だけ水がわいてきて池になるという「池ノ谷」の神秘を探るため、研究者のグループが近々池の近くでボーリング調査を開始するというのです。地元の方々からも、工事の振動で生き物たちにストレスがかかるから中止できないのかという声が、本部に届きました。研究者の方々の調べたいというお気持ちはわかりますが、トラスト地なのでそっとしておいてもらいたい旨を研究者の先生方に連絡。大変申し訳ないのですが、ボーリング調査を取りやめて頂きました。
ここの池の水はあくまで透明で、安心して飲めます。人間が手を付けなければ、自然はこんなに美しく清らかなのです。6月27日池ノ谷にて撮影。
環境ジャーナリスト石 弘之先生が原発事故問題で講演 会場満席約200名参加
- 2011-07-01 (金)
- 講演会
6月25日(土)、兵庫県西宮市民会館で石弘之先生の講演会「自然災害と地球環境-東日本大震災を考える」(主催:日本熊森協会)がもたれました。石先生は会場に入られるなり、参加者を見て「わあ大勢だね。ここにきている人たちは、どうしてみんなこんなに元気なの。学生から高齢者まで、すべての世代がそろっているね」と、驚かれました。
環境専門記者として朝日新聞社に約30年間勤められた先生は、徹底した現場主義者。スリーマイル島の原発事故の時も、チェルノブイリ原発事故の時も、現地に駆け付けて取材されました。そして、今回の福島原発事故。大手メディアでは報道されない内容を中心にお話してくださいました。3つの原発事故から、原発は人類が使える技術なんかではないことがはっきりと見えてきます。参加者のみなさんが、熱心に耳を傾けておられました。先生はお帰りの際、「今日の参加者のみなさんは、本当に熱心だね。講演中もみなさんの真剣な眼差しを感じたよ」と、感心しておられました。
 石先生のように、勇気をもって真実を国民に伝えようとする真のジャーナリストが、もっと日本にいてほしいものです。今回石先生のお話をきいて、無関心は重大な罪である、と再認識しました。
石先生のように、勇気をもって真実を国民に伝えようとする真のジャーナリストが、もっと日本にいてほしいものです。今回石先生のお話をきいて、無関心は重大な罪である、と再認識しました。
第2回くまもり講演会は10月16日(日)橋本淳司先生。
第3回くまもり講演会は11月26日(土)安田喜憲先生。
が予定されています。次回も、“真実”を、お伝えしていただきます。今からご出席予定を組んでおいてください。乞うご期待!
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ