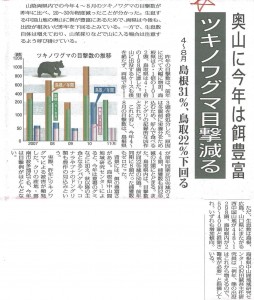ホーム > アーカイブ > 2011
2011
くまもり秋の講演会① 10・16橋本淳司氏講演会のお知らせ
- 2011-09-27 (火)
- お知らせ(参加者募集)
「安全神話が崩れたのは原発だけではない、“水”もである。」(橋本淳司氏 最新著書より)
「水と人間」をテーマに、現地調査や執筆や講演に日本全国、全世界を駆け回っていらっしゃる、気鋭の水ジャーナリスト橋本淳司氏の
講演会がついに西宮市で実現!
全生命を支える水を守るために、3.11後の日本で私たちに求められていることは何か。皆で考えましょう!
一人でも多くの方にご参加いただきたい必聴の講演会です!
————————————————————————————————-
橋本淳司氏 講演会「世界的な水争奪戦と日本の水問題」

世界的な水争奪戦に、日本は巻き込まれています。
3.11以前、日本には2つの水の危機がありました。水源林の問題と水道経営の問題です。それに加えて3.11以降、放射性物質の問題が加わりました。こうした問題について具体的に解説するとともに、いま私たちができることについてお話いたします。
と き:2011年 10月16日(日)14:00~16:30(13:30より受付開始)
ところ:兵庫県西宮市民会館 大会議室101
(兵庫県西宮市六湛寺町10-11 TEL (0798)33-3111)
阪神西宮駅「市役所口」改札北へすぐ
JR西宮駅から西徒歩約10分
受講料:会員・一般 1,000円 大学生以下無料
申込み:日本熊森協会本部事務局
電話 0798-22-4190
FAX 0798-22-4196
E-mail event@kumamori.org
※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。
Webサイト申し込みフォームからもお申込みいただけます
主催 : 一般財団法人 日本熊森協会
後援 : 兵庫県、西宮市教育委員会
————————————————————————————————————————-
橋本淳司氏 プロフィール
ジャーナリスト、著述家。水をテーマにしたルポやエッセイなどを多数執筆するとともに、水に対する興味や関心が高まるよう各地の学校で「水の授業」を行っている。現在、東京学芸大学客員准教授、日本水フォーラム節水リーダー。「みずのがっこう」副校長。
著書に『「放射能汚染水」「水不足」「水道停止」安全な水はどう確保する?』、『日本の「水」がなくなる日―誰も知らなかった水利権の謎』(主婦の友社)、『67億人の水「争奪」から「持続可能」へ』(日本経済新聞出版社)など多数。
(本部)兵庫県井戸知事に、クマの個体数調整を導入しないよう意見書を提出
<兵庫県第3期ツキノワグマ保護管理計画作成に当たっての意見書>
昨年度お会いした折、クマの人里出没問題を、できる限りクマの身体及び生命に負担をかけない方法で解決するのが望ましいという人道的判断をお示しくださったことに、感謝しております。
クマなどの野生鳥獣とかれらの棲む豊かな森を未来永劫に残すことに成功するために、第3期ツキノワグマ保護管理計画作成にあたって、以下のことを考慮してくださるようにお願いします。
(1)個体数調整名目の捕殺を取り入れないこと
研究者や捕獲業者は、個体数調整の導入を主張しますが、自然界では、野生動物の生息数は増減を繰り返しながらバランスをとっていきます。人間が捕殺により野生動物数を思い通りに一定数に保つことなど、元来不可能なことで、終わりのない泥沼の事業となります。共存は、棲み分けによる不干渉によって初めて実現できるもので、何の問題も起こしていないクマまで山の中で捕獲して、個体数調整名目で捕殺するのは残酷です。真の共存とは程遠いものです。個体数調整は、人道上からも絶対に認めないでください。
(2)現行の捕殺に至る4段階を、以前の5段階にもどす
昨年度のクマ70頭もの大量捕殺は衝撃でした。捕殺理由を入手し、全頭について読ませていただきましたが、この程度のことでなぜ殺さなければならなかったのか、理解に苦しむものがほとんどでした。
昨年度の反省の上に立って、今後、安易な捕殺が2度と行われないよう、現行の捕殺に至る4段階を、以前の5段階にもどしてください。
(3)イノシシ捕獲用檻のクマスルー化を徹底する
昨年度、イノシシ檻に誤捕獲されて放獣されたクマが、111頭もの多数にのぼっています。これは、兵庫県がイノシシの捕獲用檻のクマスルー化を徹底させていないことが原因です。費用対効果の面からも、イノシシ檻のクマスルー化を徹底させるための予算をつけてください。
(4)全く進んでいない、人が壊したクマ生息地の森の復元・再生を、早急にすすめる
クマ生息地の人工林率はどこも高く(宍粟市73%、朝来市66%、養父市61%、豊岡市44%など)て、人工林率40%で絶滅に向かうと言われるクマには、棲みづらい限りです。兵庫県はこの10年で人工林面積の3分の1を間伐したことになっていますが、2割という弱間伐だったため、現地林内はほとんどが砂漠化したままで元の木阿弥、下草すら生えておりません。5年間にわたる緑税の野生動物育成林事業も、餌場づくりにはなっておりません。動物が山に帰れる森造りを、至急進めてください。
9月25日(日) 石弘之先生講演会 群馬県高崎市 開催迫る!
- 2011-09-21 (水)
- お知らせ(参加者募集) | 群馬県
世界的な環境ジャーナリストで熊森顧問の石弘之先生による講演会「人類を取巻く地球環境の危機と自然再生」の開催が迫ってまいりました!
日本の自然保護の先駆者として活躍されてきた石先生の講演を、一人でも多くの方に聴いていただきたいです。
皆様のお誘い合わせてのご参加を心よりお待ちしております。
——————————————————————–
石弘之先生講演会「人類を取巻く地球環境の危機と自然再生」
講師 : 石 弘之 先生(東京農業大学教授/国士舘大学客員教授)
日時 : 2011年 9月25日(日)13時30分~16時30分
場所 : 高崎市総合福祉センター「たまごホール」
主催 : 日本熊森協会 群馬県支部
後援 : 高崎市、群馬県保険
お申し込み先 : TEL 080-5490-0594 FAX 027-321-2503
受講料:一般500円、熊森会員 無料(当日ご入会いただいた方も無料となります)
お申込み方法:電話かFAXでお申込み下さい。定員270名になり次第締め切りにさせて頂きます。
——————————————————–
3月11日から5ケ月、東日本大震災で2万人を超える人々が死亡や行方不明者となり、既に4万人を超える人々が福島の地を、故郷を後に県外に居を移しています。福島第一原発事故では人間、野生動物、家畜、愛玩動物やあらゆる生物が被災し、住む場所や働く場所、田畑を失い多くの人々が不安な生活を強いられ、未来に生きる子供達は放射能で内部被ばくを受け、セシウムが体内より発見されております。放射能を含む大気は既に地球を巡り、世界中の人々を不安に陥れております。
一方、1960年代から始まった国内のマツの枯損は全国的に広がり、更に、日本海沿岸各県で猛威を奮うナラ枯れが遂に群馬県内でも発生、里に出没するようになった動物達による農林業被害は次第に増加しつつあります。何か自然に重大な異変が起きているのではないかと考えざるを得ません。
日本民族は祖先が営々と築き上げてきたこの国土でこれからも安心して長く生き続けることができるのでしょうか。
石先生は世界的環境ジャーナリストとして世界130カ国を視察・調査活動を行ってこられた著名な学者であります。是非、先生の話をお聞きし、私達を取巻く地球環境の変化の実態と身近な環境変化が連関しているのかどうか、これから先の人類の進む道について勉強したいと思います。
講師 石 弘之(いし ひろゆき)先生のご紹介
1940年、東京に生まれる。東京大学卒業後、朝日新聞社入社。ニューヨーク特派員、編集委員などを経て94年退社。94~95年ブリティシュ・コロンビア大学客員教授、96~02年東京大学大学院教授(国際環境開発講座)、国際協力機構(JICA)参与。02~04年駐ザンビア特命全権大使。04~08年北海道大学大学院教授。08年から東京農業大学教授、北京大学(現職)。この間、世界約130カ国で取材・調査活動。 〔著書〕 『酸性雨』『地球環境報告Ⅰ、Ⅱ』『子どもたちのアフリカ』『キリマンジャロの雪が消えていく』『地球・環境・人間ⅠⅡ』『名作の中の地球環境史』(岩波書店)、『地球クライシス』『私の地球遍歴』(洋泉社)『地球環境“危機”報告』(有斐閣)、等多数。
9月17日 本部第10回森再生チーム活動 プロによるノコギリ間伐講習会(兵庫県宍粟市)
- 2011-09-20 (火)
- _奥山保全再生
プロによる初のノコギリ間伐現地講習会を実施しました。
皮むき間伐とは違い実際に木を伐倒するので、リスク回避のために事前に、作業場所の確認、ノコギリによる伐倒の基礎知識等のレクチャーをしっかり行います。
ノコギリの入れ方、伐倒方向の選定、伐倒する順番、退避場所の確保、かかり木の処理等いろいろな事を学んでいきます!
放置されたスギが細い場合は、ノコギリとロープだけで間伐作業が手軽にできます! 9月中旬以降、樹皮が剥きづらい時期となるため、ノコギリ間伐の出番です。参加者のみなさんは手応えを感じたようです。
ノコギリ間伐では、伐倒後に森がいっぺんに明るくなって様子がガラッと変わるので、皮むき間伐とはまた違う新鮮さ・達成感があります。
本部では今後さらに、プロによるさまざまな間伐講習会を予定しています。多くの方の参加をお待ちしています。
メディアは、スギの人工林に言及して下さい
- 2011-09-16 (金)
- _奥山保全再生
<土砂ダム>奈良、和歌山で厳戒続く…排水路を設置へ
毎日新聞 9月16日(金)11時37分配信
 |
| 拡大写真 |
| 土砂ダムが決壊する危険性があるため田辺市熊野地区へ通じる市道に鍵付きの門扉を設置する作業員ら=和歌山県田辺市で2011年9月16日午前9時55分、長谷川直亮撮影 |
奈良、和歌山両県では16日朝から一部で雨となり、台風12号による豪雨で両県内にできた土砂ダムは決壊の恐れが高まった。16日午後から17日にかけ て激しい雨が予想されている。近畿地方整備局は警戒を強めるとともに16日、和歌山県田辺市熊野(いや)と、奈良県五條市大塔町赤谷の土砂ダムで土砂の一 部を削って水を抜くための排水路を設ける緊急工事をすると発表した。この日午後から工事のために現場につながる道路を補修する作業に着手するが、いずれも 排水路完成まで数カ月かかる見通しという。
近畿地方整備局によると、排水路はいずれも長さ500メートル、幅15メートルで、土砂をくりぬいて造り、内部を金属のネットと石で固めて崩れるのを防 ぐ。熊野の土砂ダムについては、ポンプ排水も同時進行で進める方針で、早ければ17日にも着手する。赤谷の土砂ダムでは大雨の時にポンプ排水も行う方針だ が、現場に重機やポンプを運ぶのに少なくとも3日間はかかるという。
関係自治体も警戒態勢を取った。田辺市はこの日朝、土砂ダムによる土砂災害の恐れがあり、避難指示が出ている熊野地区を封鎖するため、地区に通じる市道に、金属製門扉(幅4.5メートル、高さ1.4メートル)を設置した。
大阪管区気象台によると、奈良、和歌山両県では沖縄付近でほとんど停滞状態になっている台風15号の影響で南から湿った空気が入り、16日昼過ぎから雷 を伴った激しい雨が予想される。同日正午からの24時間雨量は、多いところで300ミリ~200ミリに達する見通し。紀伊半島では18日まで強い雨に警戒 が必要で、普段よりも少ない雨量で土砂崩れや土石流が起きる恐れがあることから、気象台は大雨警報を発令する基準を暫定的に引き下げて、警戒を呼びかけて いる。【堀江拓哉、熊谷豪、川口裕之】
9月11日 太郎と花子に、熊本産早生グリを与えてみると・・・
- 2011-09-16 (金)
- 太郎と花子のファンクラブ
今日の「和歌山たろはなのお世話」は、大阪南地区が担当しました。
熊本産の大きな早生グリがお店に出ていましたので、早速購入して持って行きました。以下、この日持参した食料(真ん中の白いのは、おからです)

太郎の大好物はニンジン、花子はキュウリで、いつも真っ先に各自の大好物を心行くまで食べます。
その後、リンゴやモモなどの果物を一つづつあげ、途中、クリをあげて反応を見てみました。
・・太郎は他のものをそのままにして、栗にとびつき、ボリボリいい音を立てておいしそうに食べ始めました。
花子はなんと・・知らんぷりで、モモやトマト、ブドウなどを食べ続けています。
クマはドングリが好物ではなかったの?野生の味を忘れてしまったのかしらと心配になりました。
わたしたちが獣舎のお掃除などを終えて、クマたちを観察していると、2頭ともお腹が大きくなったのかゆったりとした動きになっています。
その時、驚いたことに、突然、花子がクリに手をのばしたのです。そうして本当に嬉しそうに、手で中身をほじくりながらゆっくりゆっくり味わうように食べ始めました。
まるで、一番の好物を最後に残して味わっている人間の子どもみたいでした。
プールにはきれいな水が満タンにたたえられ、クマたちが水遊びをして、ゆっくとりした時間が流れていきます。やさしいクマたちとふれあえた幸せな一日でした。
会員のみなさん、たろはなお世話に参加されませんか。本当に、心が癒されますよ。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ