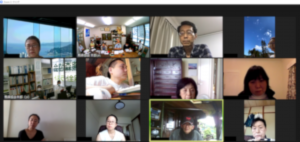ホーム > _クマ保全
カテゴリー「_クマ保全」の記事一覧
京都府与謝野町でクマによる人身事故現場を調査
現地のクマ生息地の山は、凶作の上にナラ枯れが深刻、エサ不足が懸念されます
10月24日、京都府与謝野町でクマによる人身事故が発生したと報道されました。
熊森本部は、近畿圏で発生するクマによる人身事故の現場を訪ね、お怪我をされた方をお見舞いし、再発防止対策を伝えたり、再発を防ぐお手伝いをさせていただいたりしています。
10月26日、熊森本部スタッフたちは現場へ急行しました。
お怪我をされた方のご家族と少しお話が出来ました。現場は、ご自宅の裏のクリの木付近とのことです。お怪我をされた方は、24日の朝8時頃、金属製のヒバサミを使って栗拾いをされていました。栗を拾い終えて帰るころ、クマが茂みから突然出てきて、背後から耳を引っかかれ、男性が転倒した後にクマは来た道を逃げていったそうです。幸い、命に別状はなかったそうです。
今年は、京都も山の実りが悪いと発表されています。エサが無く、里のクリを食べに来ていたクマと鉢合わせになったものと考えられます。なるべく、クマと人が至近距離で合わないように、この場の草刈り等が必要と感じました。
全国各地で、クマが出来てた、事故が発生したというニュースが後を絶ちません。秋にクマが出てくる原因を考えるには、「クマの生息地が今どうなっているか」ということを調べる必要があります。
くまもりNEWS「もはや末期症状 クマが山から次々と出てくるその訳は?」
熊森のスタッフは事故が発生した現場近くの山の調査をしました。
クマが降りてきた山を下から見ると、ナラ枯れが起きているようには見えません。しかし、山に登ってみると、標高600m程の山の上にある、コナラ、ミズナラが、木の根元から粉を吹きだし枯れていました。
100m歩くだけで、ナラ枯れで、虫の穴が開いている木は15本も見つかりました。
しかし、そのうち5本は、樹液を出して樹皮を修復しようとしていました。
ナラ枯れの原因は、カシノナガキクイムシが木に穴をあけることだというのが国の見解ですが、元気な木であればこのように樹液を出して復活できます。スタッフは、ナラ枯れ以前に木そのものが弱っていると感じました。
この山はクマの棲む自然林なのに、下草が全くありません。下草が無ければ、クマが身を潜める場所や、夏のクマの食料となる昆虫の生息環境もありません。
クマたちは、もう山に棲めないのでしょう。
里だけを見ていると真の原因や対策はわからない
山を見た後、地元の与謝野町役場を訪ねました。担当者は、山の中がこのような状況であることを知らなかったようです。その理由として「里で生活していると、里のことしかわからないから、クマが里に出てきたという情報だけしか問題にならない」ということでした。担当者は、ナラ枯れで山奥にクマがいないことは、あまりにも別世界の話でにわかに信じがたいという様子でした。
事故が発生した現場は、クマ捕獲罠が設置されましたが、1日で撤去されました。担当者のお話では、クマは事故直前に、事故現場の隣の家の柿の木に来てカキを食べていたようです。このカキを、事故後にすぐに隣の家の方が除去してくださったので、被害対策が出来ているか罠の撤去に至ったようです。
全国のクマ生息地自治体の皆さま
クマによる事故が発生した、クマの目撃が絶えない、そういった地域では、クマがなぜ、本来の生息地である山から出て来ているのか調査してみてください。山でナラ枯れが発生していたり、山の実りの大凶作など、大来な異変が発生しています。里に出て来たからといって捕獲していては、クマは滅びます。
どうか、山から降りてきたクマに遭遇しないように気をつけてください。
山の実り大飢饉の今、里の実りをわけてやってください。
人身事故の危険性がある場合は、柿の実を採って山中のクマの通り道に運んでやってください。今年のような異常年、クマと人が安全に棲み分け・共存していくためにはそれしか策はありません。
以下、今回初めて被害対策にきた、新入スタッフの感想です。
初めて事故現場を訪ねました。
事故に遭われた方以外にも町の方のお話もお伺いしましたが、対して気にされていない方から怖くてお墓参りにも行けないんだという方、クマや森の話をしても無関心な方という多様な反応に出会いました。
実りゼロという異常事態が山で起きていることに無関心な方が多いと、人身事故を起こすかもしれないクマは捕殺しておこうとなり、安易な捕殺が暴走するのではないかという印象を受けました。
問題に対し関心を持ち、実際に山に入って原因を探り、対策を考えることの重要性を改めて感じました。これからも、徹底した現場主義を貫き、現地を歩き続けます。
くまもり本部・支部、人身事故とクマの絶滅回避のために、里の実りを山に運んでいます
奥山原生林でひっそりと生きながらえてきた日本のクマたちは、戦後の林野庁の拡大造林政策と、奥山開発で、広大なえさ場を人間に破壊され、生息地を失いました。

外から見ると青々とした人工林、林内食料はゼロ
さらに、近年、残されたわずかな自然林の中から、ブドウやイチゴ類など果肉が多汁で柔らかい果物である液果の実りが少なくなっています。受粉してくれる昆虫が、地球温暖化等の影響で大量絶滅したからです。

ほとんどの液果は虫媒花です。写真は、ミズキ
ドングリ類など実の堅い堅果の実りも少なくなりました。酸性雨等の影響で、木々が弱ってきており、大量枯死してしまったからです。(ナラ枯れ、カシ枯れ、シイ枯れ)
今年枯れたクヌギの巨木(兵庫県)

今年夏の鳥取大山のナラ枯れ(赤色部分の木が枯れてしまった)
様々な液果の実りやミズナラを中心とする堅果の実りに頼って生きてきたツキノワグマたちは、食料を失いました。ツキノワグマは日本の奥山にいるだけでは生きられない状況になっています。ブナは幹の構造上、ナラ枯れしませんが、多くの地域で、去年も今年も大凶作。実りがゼロです。木々が弱ってきているのです。
こんなことになったのはすべて人間活動が原因です。
冬ごもりに備えて今大量の堅果を食べ続けなければならないクマたちは、連日、里の木々の実りを求め、次から次へと山から出てきています。
クマと共存する経験をしたことがない集落では、対応の仕方がわからず、皆さん悲鳴を上げておられます。
猟友会、警察、行政、マスコミなど大勢で1頭のクマを追いかけまわして、クマをパニックに陥れ、人身事故を誘発させています。
クマは人間と違って、本来、争いを避ける大変平和的な動物です。至近距離での突然の接触を避ければ、人身事故のほとんどは防げます。
日本のほとんどの役所は、クマが出てこないように里の柿の木を伐ったり、里の柿の実をもいで捨てたりするよう、地元に指示しています。
しかし、里の実りを利用できないと、クマたちは生きるために仕方なく、里を通り越して、その先の市街地に出て行くようになりました。
これが今、日本中で起きているクマ騒動の実態です。
熊森は、臆病なクマたちが、夜こっそり民家の柿の木に登って柿の実を食べていたら、静かに見守ってくださいと地元にお願いして回っています。
奥地に行くと、昔からクマと共存してきた集落が今もいくつもあって、必死で柿を食べるクマを皆さんそっと温かい目で見守っておられます。こういう集落では、クマによる人身事故は全く起きていません。
このようなことが無理な集落では、柿の実をもいでください。
熊森も手伝って本部・支部、みんなでどんどん山に運んでいます。
 熊森本部資料より 山中のクマの通り道に運んだドングリと柿
熊森本部資料より 山中のクマの通り道に運んだドングリと柿
熊森本部資料より 人間の運んだドングリを食べに来たクマの兄妹(自動撮影カメラ)
以下は、今年、くまもりの支部から送られてきた10月の活動報告写真です。
集落の方と協力して、一緒に、軽トラでごみ袋50袋分ものもいだ柿と集めたドングリを、クマが山から出てくる道に大量に運びました。
次の日見に行くと、「クマのエサ場です。近寄らないで下さい」という看板を、地元が立てておられました。
辺り一面クマの糞でいっぱいでした。
もいだ柿の実、ドングリを運び続けると、クマをこの場所で止めることができます。

平地のクヌギやコナラのドングリを、クマの通り道に運ぶ熊森会員たち
この町では、山裾に実のなる木をたくさん植樹して、令和のクマ止め林を作っていこうという熊森提案に賛成する方が、何人も出てきました。
熊森は、奥山水源の森の再生活動を進めるために結成されたボランティア団体で、がんばっています。しかし、これには時間がかかります。
当面のクマ対策として、平地向きのドングリや、カキ、クリなどを地元の皆さんと、山裾にたくさん植えていこうと思います。
飢えて人里に出て来ざるを得ない哀れなクマたちが、やっとのことで見つけた食料を取り上げた上、「危険」とレッテルを貼り殺してしまう。こんな行為が、今、日本全国で展開されており、このようなことが続けば、クマの個体数は激減し、クマは確実に絶滅します。
熊森は、やさしい解決法が一番優れていると思います。
クマが里や街中に出てきたという現象だけを見ている人たちは、現在のクマの異常事態に対してびっくりするような間違った原因説を出しておられます。
<クマが山から出てくる誤った原因説>
1、クマが爆発増加した(クマ爆発増加説)
→熊森反論:本来の奥山生息地は空っぽです。
2、クマが人間をなめだした(人なめ説)
→熊森反論:人間が怖いから人間から逃げようとして人身事故を起こすのです。
3、クマが山のものより里のもののほうがおいしいと味を占めた(味しめ説)
→熊森反論:実験で、ドングリと柿やリンゴを同時に与えると、クマはドングリに飛びつきます。
4、クマが生息地を拡大しようとしだした(生息地拡大説)
→熊森反論:生息地拡大ではなく、ドーナツ化現象です。
5、地元が里山を放置した(里山放置説)
→熊森反論:里山は1960年から放置されています。
どうしてこんなに誤った原因説が世に出回るのでしょうか。
日本熊森協会の原因説は、ただ一つです。
→1、山から食料が消えた
小泉進次郎環境相が26日にクマ被害対策の会議開催を表明されているそうです。
クマの生息環境の危機的な状況も踏まえた共存のために何をするべきかを具体的に進めることができる会議になることを祈るばかりです。(完)
【速報】クマ止め林をつくろう!
凶作年にクマたちが集落に出ないように、
えさ場づくりをめざして植樹会を開きました
10月18日 兵庫県宍粟市 原観光りんご園の裏山
ナラ枯れと山の実りの大凶作でクマをはじめとする野生動物にとって深刻な食料危機が現実になっている中、山から食料を求めて下りてくるクマたちのえさ場となるように、日本熊森協会は18日、兵庫県宍粟市波賀町原の原観光りんご園裏山でクマのえさ場づくり植樹会を開きました。兵庫県の奥地では、昔は、山すそにクリやカキを植えている地域が多く、奥山の実りの凶作年に、クマがクリやカキを食べに来て、植えた木々によってクマが集落に下りるのを止めていたそうです。
線路の枕木の利用や拡大造林のために伐られてしまった「クマ止め林」をもう一度、復活させたいと考えています。
兵庫県内だけでなく、大阪府や滋賀県在住の会員や非会員など15人とスタッフ4人が参加。原観光りんご園で約5年前まで専務理事を務めておられた幸福重信さん(83歳)に選んでいただいたカキ10本、クリ6本、ヤマボウシ2本を植えました。
幸福さんは、専務理事ご在任当時に苦労して育てたリンゴ約1万個を山から下りてきたクマたちに食べられてしまった体験を参加者に話されました。
「被害を知って腹は立ったけれど、よくよく考えてみると山に食料がないから生きるために下りて来たことが分かった。人間だけが良かったらいいのではなく原因は人間の側にあるのだ、人間が反省しないと、と思って共生の森づくりを熊森さんたちと始めました」と幸福さんはこれまでのいきさつを紹介。現場の裏山での植樹の取り組みなどを振り返りました。
幸福さんは「今年はあのころと同じように、山にえさがないひどい状態。あの当時から数えてちょうど今年は15年。クマたちと共生できる森をつくるために、いっしょに頑張りましょう」と呼びかけました。
幸福さんは続いて樹高約1メートルほどの苗木を手にとり、土を掘って水を入れ、土で固まった根を手でほぐしながら植え付けていく方法を身ぶり手ぶりを交えて解説しました。幸福さんの指導を受けながら、親子連れの参加者が植え付けにチャレンジ。植え終わると満足そうな笑顔を見せていました。
最後に、シカなどが侵入して食べられてしまう被害を防ぐためネットを外側に貼る作業をしました。
この日植えられた木は3年ほどで実をつけます。幸福さんは「皆さん自身の手で植えた木をぜひまた見に来てください」と呼びかけていました。奥山に実りが少ない状況は、当面は続くと思いますので、今後、液果やすぐエサになるものを補植していきたいと考えています。
小学1年の娘を連れて、初めて熊森の野外活動に参加した兵庫県の女性は「植えることの大切さや森林の意味についてとてもよく分かる説明で、参加して実際に植えることができて良かったと思います。必ずまた植えた木を見に来たいし、活動にも親子で参加します」と目を輝かせて感想を話していました。
山にエサがないクマたちが集落に降りて来ないようにするには、当面のえさ場が必要です。本部や支部を中心に、全国でこのような活動を広めていきたいです。
「クマ乱獲ストップ」2万人署名めざし、ZOOMで全国会議
3月末から呼びかけを始めた「クマの乱獲をもたらしている罠捕獲の規制強化」を求める署名運動をパワーアップさせたい。
インターネットのチェンジと紙の署名を呼びかけている熊森本部は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の解除をきっかけに本格的に活動を再開しようとしています。さっそく、全国の支部や会員のみなさんと一緒に署名を集めたいと、6日午後から兵庫県西宮市の本部と各地をつないでインターネットのZOOM会議を開きました。
遠くはニュージーランド在住の会員さんをはじめ、国内では11都府県の計約16人がネットを通じて参加されたほか、近隣在住で直接本部に来られた方も含めると約20人が参加していたたき、にぎやかな会となりました。
罠による捕殺が止まらなくなっている
室谷悠子会長が、署名の目的をまず説明。全国のクマ捕殺数が昨年過去最多で現在もどんどん増え続けていることを取りあげました。
「法律上は許可がない捕獲は違法で、放獣しないといけません。環境大臣も国会でそう答弁しているのに実際は地域で放獣の態勢が全然とられていないため、守られていないのです。狩猟の免許者は減っているのに、罠の免許者は1970年代の数倍にも増えています。山の中にはどのくらい罠があるのか分からない実態で、捕殺が暴走しています」と、室谷会長は訴えました。
さらに「滋賀県のように行政の保護意識が強く、捕殺がゼロの県がある一方、隣の京都府では170頭も殺され、0歳の子グマまでも殺されています。放獣態勢は11府県であるだけで、ほとんどできていないのが実態です」と都道府県の実情を語りました。
捕殺に頼らない棲み分け対策こそ重要
水見本部職員がクマの人身事故が起こった現場を調べた様子や、クマの食べ物が年間の時季によって異なることなども解説。
「地域で人里とクマの生息域を棲み分けるために、山の凶作のときに誘因物となるカキの実を除去しておいたり、梅酒などアルコール、ガソリン、腐った食べ物を外に置かない、突然の遭遇が人身事故につながるので、クマの潜み場となる雑草を刈るなどの対策が必要です。過疎と高齢化で、昔はできていたクマとの棲み分けができなくなっている地域が多くなっている。クマ問題は、社会問題でもあります。熊森も会をあげて、地域のクマ対策を応援する必要があるし、公的な支援も必要です」と捕殺では、クマ問題を解決できないことを伝えました。
署名を集めるためのアイデアはいろいろ
「秋の臨時国会までに2万人の賛同を集めて提出したい。『クマの乱獲をストップさせる法規制や人里との棲み分けを進め、罠にかかったクマの放獣態勢を整えよう』と国民の大きな声として国や都道府県を動かしていきましょう」と室谷会長は訴えました。
署名拡大のためのアイデアを問いかけると、ZOOM参加の全国の会員さんから次々と意見が飛び出しました。
「誕生日に、Facebookでお祝いメッセージをもらったら、お礼のメッセージに『クマ署名に協力してください』と呼びかけたら、たくさんの人が協力してくれました」
「美術館や動物病院などに署名用紙を置いてもらおうと思います」「動物園に置いてもらうのもいい」
「分かりやすくアピールできる、くまもり版のユーチューブを制作してみては」
「とよくんの動画を使ってユーチューブで署名のPRもしてみては」「インスタグラムも効果があります」
いただいたアイデアを生かして、署名拡大に向けてさらに取り組みを強化していきます。
みなさんもぜひ、署名にご協力ください!!
ネット署名アドレスはこちらから
シェアして、広めていただけるとうれしいです。
紙署名はこちらからダウンロードできます。
署名用紙がたくさん必要な方は、本部までご連絡ください。
Tel: 0798‐22-4190
Mail: contact@kumamori.org
尚、署名は、ネットか紙か、どちらか一方だけにお願いします。
富山市の事故例から:ツキノワグマによる人身事故を減らす方法
富山県で、クマによる人身事故が発生しました。
お怪我をされたお二人の方に、心からお見舞い申し上げます。
それにしても、どうして人身事故が発生してしまったのでしょうか。
このクマを生かして山に返してやることはできなかったのでしょうか。
<以下、報道から>
警察や市によると、5月17日(日)朝8時28分に「高速道路ののり面にある繁みに1頭のクマがいる」という目撃情報が入りました。
午前9時25分ごろ、同市石田の無職、Kさん(92)が自宅の家庭菜園で作業していたところ、クマに遭遇。驚いて転倒し、左脚の骨を折りました。約5分後に、近くの畑で農作業をしていた同市小杉の飲食店経営、Iさん(84)がクマに右腕と右脚をかまれました。2人とも県立中央病院に運ばれましたが、命に別条はありませんでした。
午後1時15分、クマは民家の庭に逃げ込んだところを警察官立ち合いの元、猟師が銃で射殺しました。若いメスグマでした。
現場は北陸自動車道の南側で、富山地方鉄道上滝線の布市駅に近く、周辺には住宅地があります。
熊森から
富山市の担当者に電話で聞き取ったところ、現場周辺にはクマを引き寄せるものは何もなく、どうやってそこまでクマが来たのか、経路もわからないということでした。胃の内容物は草だったそうです。
熊森としては、現場近くの地理的特徴から、このクマは人目に付かない時間帯に、河川敷に沿って草を食べながら山から出てきたのだろうと思います。その後、山に帰りそびれたクマは川の繁みを伝って移動していたのではないでしょうか。その際、何らかのきっかけがあって(障壁があった、あるいは人を避けたなど。ちなみに現場の近くにある富山空港は、神通川の河川敷が滑走路になっています)北陸道ののり面に出てしまったようです。一般に、ツキノワグマは、人をとても恐れています。今回のメスグマも。人に見つかって恐怖におののいたと想像できます。
目撃情報を得て、日曜返上で、市担当者、県担当者、猟友会、警察など皆さんが現地に駆け付けられ、クマの捜索に当たられたそうですが、クマは見つからなかったそうです。クマは、これらの人間の動きを息を潜めてそっと見ていた可能性があります。
捜索中も、一般市民から、クマを見かけたという情報が次々と入り続けていたそうです。
多くの人間がクマを追いかける。多くの市民が屋外にいる。この状況が人身事故を誘発するのです。
何とか改善願いたいものです。
このクマは、人間から逃げようと走り回った結果、次々と人間に見つかるはめになり、もうどうしていいかわからず、パニックになってしまっていたのでしょう。
必死で逃げているときに、急に目の前に現れた人を攻撃して逃げきろうとするのは、人もクマも同じです。こうして、また、人身事故が発生してしまったのだと思われます。
先進的な海外では、このような場合、行政は住民に屋内退避を指示します。全員でクマをそっと見守って、クマが逃げて帰るまで待つと聞いています。「クマ1頭のために、人間活動が制御されるのはおかしい」という考えもあると思います。しかし、人身事故を起こさず、クマの命も守るためにはとても有効なやり方ではないでしょうか。
奥山生態系の保全・再生に取り組んでいる熊森は、日本最大のクマの保護団体でもあります。熊森として、いつも一番恐れているのは人身事故の発生です。
ひとたび人身事故が発生すれば、人も大変です。クマはその場で殺されてしまいます。
本来、平和愛好者であるはずのクマが、マスコミによって人を襲う恐ろしい動物のような誤ったイメージに、あおりたてられて、独り歩きしてしまっています。
どうして人身事故が発生したのか。事故が起こるたびに熊森は調べ、考えます。
人身事故を起こしたクマは、射殺されて当然という声もあると思います。しかし、今回のクマも、人身事故など起こしたくなかったと思います。
海外のように、クマが山に帰りましたという放送があるまで人間が全員家に入っていたら、人身事故は起きませんでした。警察や行政にも責任はあると考えます。
このクマにいつの時点で射殺決定が下りたのかはわかりませんが、富山市は緊急の場合のために、あらかじめ3頭のクマ駆除枠を取ってあるそうです。今回のクマはこの駆除枠を使って射殺したのではなく、警察官職務執行法によって射殺したそうです。
富山県は、県職員が麻酔銃でクマを捕獲する体制が整備されているということで、すばらしいと思います。この体制を使って、民家に逃げ込んだクマを捕獲して山に返してやれなかったのでしょうか。
クマが最後に植物で覆われた民家の庭に逃げ込んだのは、人間たちに追いかけられて、どこかに逃げ込みたい一心だったのだろうと思います。銃を構えた多くの猟友会員に囲まれて、このクマはもう人身事故を起こして逃げおおせる可能性は消えていたと思われます。
現場で対策に当たられたみなさんは、使命感を持って頑張られたと思いますが、初めてのミスで人間の所に白昼留まってしまったこのクマを麻酔銃で捕獲して山に返してやることもできたのではないでしょうか。他生物にも思いやりある優しい社会を作っていきたいものです。
P.S 熊森からの質問に対して、お忙しい中で隠すことなく丁寧に答えてくださった富山市の担当者に感謝します。
暑くなったね、とよにたらい
- 2020-05-02 (土)
- _クマ保全 | くまもりNEWS | 大阪府 | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」
本日の最高気温は27℃。一気に、汗ばむ陽気となりました。
プールが大好きなとよは、なんと先日、暑さにたまりかねてか、水飲み用のステンレスバケツに、足を突っ込んでいたそうです。
そこで、プール改修が終わるまでの間、これで我慢してもらおうと、本日、昔洗濯に使っていた大きなたらいを持参しました。
大きなたらいと思ったのですが、とよの前では本当に小さく見えました。
右前足を入れたら、もう一杯です。
何とか水に触れたいトヨが、この後、どうしたか。動画で見てください。
両前足とお顔の半分下をつけたらもう限界。でも、楽しんでくれたようでした。
お寺やお世話隊の愛情をいっぱいに受けて、今ではとよは、人間を信頼しきって生きています。
久しぶりにとよに会って、しばらくお互いに見つめ合いました。
クマがこんなに穏やかでこんなに人の心をいやしてくれる動物だなんて。
テレビ局が撮影に来てほしいな。
家族連れが次々ととよ会いに来てくれました。
とよを見始めると、みなさんのお顔がみるみるゆるんでいきます。
みなさん、ニコニコ顔になって帰って行かれました。
とよの力、すごいね!
プール改修、急ぐね。(完)
NHKスペシャル【ヒグマと老漁師~世界遺産・知床を生きる】を見て
以下、会員からのメールです。
昨晩のNHKスペシャル【ヒグマと老漁師~世界遺産・知床を生きる】を見ました。
老漁師が大声でコラッとかこの野郎とか言ってヒグマを遠ざけながら漁をしていました。
見ていてヒグマと共存というより、私にはヒグマを虐待しているように見えました。
なぜなら、ヒグマは人が見えるところに来ただけで、大きな声で追い払われているのです。何も悪いことはしていません。
・
番組のなかで、ここまでヒグマと共存できているのは、この知床だけだというようなことを言っていましたが、そうではありません。
ロシアでは(場所は記憶していませんが)、猟師のすぐそばで何頭もの大きなヒグマが、漁師から捕った魚を分け与えてもらって食べている場所があります。
漁師たちもヒグマも、どちらも互いを恐れてはいませんでした。
・
しかし、この知床では漁師が捕った魚は1匹たりともヒグマには与えないと言っていました。
だから飢えてやせ細ったヒグマの親子は弱り果て、子熊は死んでしまいました。(多分あの母熊も死んでしまうでしょう)
そんな状態のどこが共存なのでしょう。
人間がまるで海の幸は自分たちだけのものだと言わんばかりに独り占めして、ヒグマを見殺しにする自然遺産なんて変です。
NHKは、ヒグマと人が共存しているこの場所は何と素晴らしいのかと称賛しているようですが、違うと思いました。
別の方法で共存する方法があると思います。
ユネスコ自然遺産の調査団は、漁師の都合で作った道路とダムを撤去するように要請しました。
熊森から
番組は見ておりませんが、あの場所は有名です。
あの場所は特別保護区で、普通の人は入れません。
入れるのは許可を得た特別な研究者と環境省のレンジャー、番屋の漁師だけだと思います。ああそれと、NHKのカメラマン。最果ての地です。
残念ながら、日本でヒグマが殺されないのは、あの場所だけです。
北海道に行って驚くのは、海にびっしりと張り巡らさせた定置網が延々と続いていることです。
これでは、戻ってきたサケやマスが、川を上る前にほとんど人間に捕獲されてしまうのではないかと危惧します。
それでも、ヒグマを殺さないという一点だけで言えば、知床のあの場所は、ヒグマにとっては奇跡のような唯一の天国だと思います。
その点では、ヒグマを殺すことを止めて50年という老漁師さん(84歳)はすごいと思います。
しかし、人間も含めた全生物のために、入らずの森や開かずの森を取り戻したいと考えている熊森としては、あのような最果ての場所は、将来的には海岸の定置網を除去して、漁業も撤退して、人間が入らないヒグマの国に戻すべきだろうと思います。
イノシシ罠に誤ってかかってしまったクマをどうしますか
ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情を踏まえつつ、ツキノワグマの出没状況を確認しながら、わなの形状、餌付け方法等を工夫して錯誤捕獲を防止するよう指導する。また、ツキノワグマの錯誤捕獲に対して迅速かつ安全な放獣が実施できるように、放獣体制の整備に努める。
これまで、錯誤捕獲されたクマは法律通りきちんと放獣してきた岡山県なのに、どうなってしまったのでしょうか。
・
尊厳されるべきは人間の命だけという間違った方向に日本社会が進んでいることに、熊森は大変危機感をおぼえています。すべての生命が尊厳される社会でなければ、自然も、地球環境も守れません。
・
熊森は自然保護団体として、どこまでも、全生物の生命尊厳を訴えていきます。
クマはなぜか、簡単に罠にかかってしまう動物です。
バッコヤナギに親子グマの映像 宮城県仙台市
21日午前8時ごろ、仙台市青葉区大倉ダム近くで鳥獣被害対策実施隊(猟友会)が6頭の親子を目撃しました。 クマの体長は2頭が1メートル以上、別の2頭は70センチほど、 残りの2頭が50センチほどで2組の親子と みられています。 クマたちはこの後、バッコヤナギの新芽を夢中で食べていたということです。
動画がアップされている間に、みなさん、ぜひ見ておいてください。見とれてしまいますよ。
TBC東北放送より
花火で脅すと、別の木に移り、再び食べ始めたそうです。
釣り人が来ていたので、クマが出ていますと伝えると帰られたそうです。
午後3時ごろに宮城総合支所の職員が注意を呼びかける看板を設置したりして周辺に注意を呼び掛けました。
食べ終わったら移動するだろうということで、行政として捕獲などは考えていないということです。
熊森から
人間がここにダムを造らなければ、見つかっていなかったクマたちの春の生態です。
あの重い体で枝が折れないのかとハラハラします。
クマのため、全生物のため、人のため、このような場所を未来永劫に日本各地に残していきたいです。
私たち熊森の使命でもあります。
丸尾県議が「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」の公開を求め質問してみた結果
兵庫県当局の答弁は誠実なものではありませんでした
新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴い、兵庫県にある熊森本部もテレワークに切り替えています。
これまで忙し過ぎて書けていなかったことを徐々にアップしていこうと思います。
まず初めは、兵庫県鳥獣対策課と兵庫県森林動物研究センターが主導して開催している「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」を、当局が開催場所・日時・内容に至るまで、全て徹底的に非公開としている問題です。
3月11日の兵庫県予算特別委員会農政環境部会で、丸尾牧兵庫県議(尼崎市選出)が質問してくださいました。
<質問の大意>一昨年、兵庫県が主導して近隣府県に呼びかけて発足した「近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会」に関して、協議会・科学部会の委員名と会議・議事録・プログラミングデータなど根拠の資料を公開すべきだ。
兵庫県のツキノワグマ推定生息数の算出法は問題だらけで過大推定になっていると日本福祉大学の山上俊彦教授(統計学)が指摘されている。参考人として科学部会などにお呼びして、ご意見をうかがってはどうか。
兵庫県鳥獣対策課課長の答弁:委員ご質問の広域協議会の会員と議事録におきましては、すでに公開をしている所でございます。また、科学部会の委員と議事録におきましても、今後公開する予定としております。協議会及び科学部会の会議の公開につきましては、原則公開を行おうと考えておりますが、委員の率直な意見交換などを阻害する場合においては、非公開ということを考えております。(兵庫県議会インターネット中継録画からそのまま文章化)
この委員会の後、丸尾議員から熊森に「山上俊彦教授の招へいは拒否されましたけれど、広域協議会は今年から公開されますよ。まず一歩前進です」という喜びの連絡が入りました。
熊森は念のため、後日、兵庫県庁の鳥獣対策課に確認してみました。
熊森:広域協議会の科学部会の委員名や議事録は、どこに公開されているのですか?インターネットで探し回ったのですが、見当たりません。
鳥獣対策課:出していません。
熊森:先日の丸尾議員の質問に対して、課長さんは「すでに公開している」と答えられていますが。
鳥獣対策課:情報公開請求があれば、公開しようかなという意味です。
熊森:公開されないから、情報公開請求をするのでしょう。そういうことなら「すでに公開をしている所でございます」は、虚偽の答弁だったということになりますよ。
熊森:今年から広域協議会や協議会の科学部会が公開されることになったんですよね。傍聴もOKですよね。
鳥獣対策課:非公開です。傍聴も不可です。
熊森:科学部会の委員のお名前は教えてもらえるのですよね。
鳥獣対策課:部会の委員が教えてもいいと言った場合の話で、いいと言わなければ公開できません。
熊森:今後公開する予定としておりますと答弁されたら、誰だって公開されると思ってしまいますよ。
鳥獣対策課:もう一度、(議会の)課長の答弁を一言一句確かめてください。公開するとまでは言っておりません。公開は委員の率直な意見交換を阻害する恐れがありますので。
熊森が丸尾議員に「鳥獣対策課に確かめると今年もまた非公開だそうです」と伝えると、丸尾議員は絶句しておられました。
熊森から
兵庫県に問いただした結果、要するに県は、今年も広域協議会を非公開のまま続けるのだということがわかりました。
しかし、県議会をインターネット経由で傍聴し質疑のやりとりを聞いた一般の県民はみんな、丸尾議員と同様に「今年から公開されるのだ」と受け取ってしまったに違いありません。
兵庫県の行政担当者の対応は、まるで公開しているかのごとく受け取れる答弁を議会の場ではしておいて、疑問の声が上がったら、委員の率直な意見交換などを阻害する恐れがある場合は非公開であると最後に付け加えてある。よく聞けと、まるで私たち県民に非があるかのように持って行くやり方です。
このような県担当者の答弁は、世にまやかしと言われているものです。私たち県民をはじめ、県民の信託を受けて選ばれ質問権を行使してくださった丸尾議員に対しても失礼な答弁であり、県民全体の奉仕者であるはずの行政担当者としてあるまじき姿勢です。
広域協議会は、今年度も多額の私たちの税金を使って開かれる会議です。それなのに、兵庫県の行政担当者や、兵庫県の政策を決めている森林動物研究センターの研究員は、国家機密でもあるまいに、どうしてここまでツキノワグマに関する会議の内容を隠そうとするのでしょうか。
自信がない?
科学的と称してきた発表内容に、実は科学性がない?
県民に知られたらまずいことがある?
民主主義の社会は、十分な情報公開があってこそ初めて成り立つものです。みんなで情報を公開しあって他者の意見も聞く。この姿勢がない行政担当者や研究者は、失格だと思います。誰もお互い、神様のような完璧な人間ではないのですから。
この日の農林水産部会で、農林水産部長が「世界に誇る兵庫県森林動物研究センター」などと、兵庫県森林動物研究センターの研究者のことを絶賛していました。この発言にはさすがに熊森も、耳を疑いました。
3年ごとに部署替えがある行政担当者には専門知識がありませんから、難しい数式や難しい専門用語を並べたてる専門家のいうことを信じるしかないのだろうと思います。しかし、一つのものだけを絶対的に信じきってしまう姿勢はとても危険だと思います。
以下は、現在進行中の新型コロナウイルス対策について、インターネットから拾ったコメントです。
「専門家の方々は医師免許があっても普段は診療しませんから。こういう方が主導的に感染症対策を決めるのは、暴走するリスクすらあると思います。テクノクラート(科学者・技術者出身の政治家・高級官僚)が主導権を握ると、しばしば暴走して第2次世界大戦のようなことになる可能性もありますよね。専門家に対応を丸投げするのは非常に危険なことだと思います。医療現場の判断を優先すべきでしょう。」
このことは、あらゆる分野に言えることではないかと熊森は思います。どんな問題に対しても、幅広い人の知見を集める、衆知を集めることが必要なのです。
熊森は設立以来23年間、徹底した現場主義で兵庫県のクマ問題に誠心誠意取り組んできました。審議会にしろ、広域協議会にしろ、兵庫県が熊森を排除しようとし続けている理由が全くわかりません。(以上)
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ