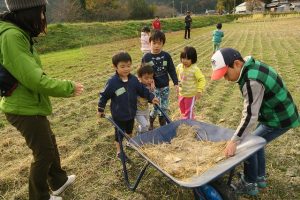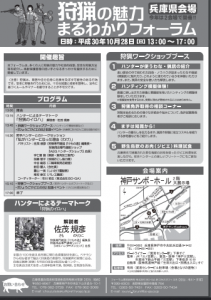以下がその内容です。
Q クマは人を襲う恐ろしいイメージがある。
A 本当はおとなしく、人を恐れている。昼行性だが、餌を求めて人里に下りるのも日中ではなく人の少ない朝夕が多い。
Q なぜ人を襲うのか。
A 出合い頭で襲われるケースが多く、クマがパニックになっている場合がある。かんだりひっかいたりするが、クマからすれば狩りではなく、逃げるための攻撃。急所を狙ってくるわけでもない。
Q 最近、市街地に現れ人を恐れないクマ「アーバンベア」が問題視される。
A 「新世代クマ」などと間違ったイメージが先行しているが、アーバンベアとて人慣れしてはいない。人を避け本能的に逃げたいのは同じ。民家の敷地に侵入するのも身を隠したい気持ちによる。
Q クマはどんな食性か。
A 植物中心の雑食性で基本的に何でも食べる。春はタケノコ、夏はアリなどの昆虫、イノシシやタヌキの死骸も食べる。秋は冬眠前に脂肪を蓄えるためドングリなど脂の多い木の実を求める。足りないと栄養価の高い柿に強く執着する。普段いる山奥が木の実不足だと行動範囲を広げる。
Q 出くわした際はどうすればいいのか。
A 刺激するような行動を避けることが重要。クマが人に気付いていない、もしくはかなり遠くにいる場合は、静かにクマから目を離さず立ち去る。クマも気付き距離が近い場合は背を向けず、目を離さず、後ずさりするようにして去る。襲われたら急所を守る防御態勢を取る。両腕で頭を抱えて顔、頭部を守り、うつぶせになって腹部を守る。
Q 山を歩くときに特に気を付けることは。
A 遭遇時の対応を知っておくことも大切だが、出合わないことが一番大切。鈴を鳴らしたり、ラジオをかけたり存在を知らせながら山に入る。遭遇は朝夕が多い。この時間帯は特に山林での単独行動を避け、複数で入る場合は会話することを意識してほしい。
Q 他の鳥獣との違いをどう見るのか。
A 農林業に悪影響を与えるイノシシ、シカなどと比べると、被害の性質が異なる。島根県内では農作物被害の大半をイノシシによるものが占め、ツキノワグマは金額としては全体の1%未満に過ぎない。人を襲うのが問題だが、クマが望んでいるわけではない。人里や市街地に呼び込まないよう、人がいなくなり放棄された果樹の撤去や残飯、生ごみの処分の徹底など、人間の努力が求められる。(完)
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ