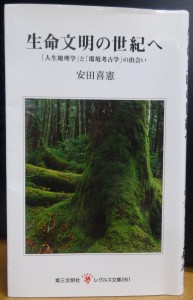くまもりNews
1月6日 年明け早々の豊能グマくん
- 2015-01-06 (火)
- _クマ保全 | くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」
役場がお正月休みだったので、久しぶりの豊能グマ君のお世話日となりました。役場の方が、休み中もお世話して下さっていました。ありがとうございました。
元気にしているかな。今回は特別で8人で行きました。
そっと部屋のドアを開けて移送檻の中の豊能グマ君をみんなでしばらく見ていました。年末にたくさん入れてもらった藁の中に埋もれて、眠っているようです。私たちが来ていることに気付かないのか、動きません。
眠っているよ
お掃除を開始です。みんなで部屋の中に入っていくと、クマ君は起きてきました。女性陣には、少しずつ気を許し始めたようです。
女性陣は信頼してもいいみたい
移送檻内の藁を、4センチの鉄格子からいったん全部取り出しました。結構時間がかかりました。その間、クマ君には、杉の間伐材の輪切りをおもちゃとして与えておきました。食事よりも、間伐材の輪切りをかじって粉々にすることに余念がないようです。
お掃除中も、杉の輪切りをかじり続けるクマ君 ストレス解消になるといいね
糞尿もたくさんあったので、移送檻の床を水できれいに洗い流しました。
その間、Mさんが、杉の輪切りをかじる豊能グマ君の歯を、集中的に撮影しました。どうも、右上下の牙が折れているのではないかと、前回、問題になったからです。
右牙上下
逃げ出そうとして獣舎の鉄をかじったのかもしれませんが、仕方がありません。箱罠にかかって檻の鉄を噛み、歯を全部失ってしまうクマも多いと聞いていますが、豊能グマ君は、今のところ、他の歯や左牙上下は大丈夫ですから、良しとするしかありません。本当に一日も早く、広い獣舎に移してやりたいものです。
「生命文明の世紀へ」 安田喜憲顧問著
- 2015-01-07 (水)
- くまもりNEWS
人間は、生態系の頂点に位置する動物ではない イエボア博士(ガーナ)
以下は、公益財団法人イオン環境財団の「生物多様性みどり賞」を受賞されたアルフレッド・オテング=イエボア博士の言葉です。
人類はもっと自然に対する理解を深めなければなりません。
それなのに、人類はこれまで自分たちの欲求のまま自然を利用してきました。
地球上のあらゆる場所で野生生物の採集や乱獲を行ってきたのです。
では、自然に対して何か配慮をしてきたでしょうか。
答えはノーです。
これまで地球上では、実に多くの破壊活動が経済開発という口実のもと行われ、環境と人間の調和がその代償となってきたのです。
このような収拾のつかない状態を解決するには、問題の多くを生み出した私たち人間が行動を起こすしかありません。
環境に対する最良のアプローチは、人間が生態系ピラミッドの頂点に立つ “Me,Me 主義”ではなく、人間も生態系の一部になること。
人間の活動が自然と調和するように、人間自身が心がけていかなければなりません。(同財団のHPより)
熊森から
海外にも私たちと同じことを感じておられる方がいることを知って、とても勇気が湧きました。
1月12日 本部から高知県へ 高知県支部長と人工林の共同伐採
1月12日。高知県支部長が奥山の人工林を購入して伐採しているということなので、本部も協力しようと高知県に行ってきました。高知県の人工林率は66%にも達しています。
なんと、この日の高知県の奥山は、かなりの雪でした。
雪のために、高知県支部長の自宅からは車を出せないと言われました。仕方なく、近くの宿泊施設に車を置き、あとは10分ほど歩いて、支部長の家に到着しました。最初、林業に従事してこられた徳島県の会員といっしょに来ようと思ったのですが、残念ながらひとりで来ることになりました。
家のまわりは白銀の世界でした。
猫さんも寒そうです
鶏もいます
ヤギもいます
そして、なんと羊も飼っておられました。
作業中、支部長の愛犬がまわりを走り回っていて楽しいのですが、危ないので慎重に伐採を進めました。
この日、伐採した木は33本。これでしばらくは薪が足りると、支部長が喜んでいました。
この道の奥に支部長が購入した杉山が10haほどあります。これからどんどん伐採して、自然林に戻していくそうです。
また、本部から伐採を手伝いに行きたいと思います。四国の会員で伐採に参加できる方はお知らせください。
お寺の裏山の人工林を、くまもり本部が無料伐採① 兵庫県三田市 1月8日
- 2015-01-08 (木)
- _奥山保全再生
昨年、三田市にあるお寺から、「お寺のすぐ裏山が放置人工林で、いつ崩れるかわからない。伐採していただけるのですか」という問い合わせがありました。このお寺の方はくまもり岐阜県支部にご友人がいるようで、その方から熊森本部のチェンソー隊の話を聞いたということです。
昨年11月にそのお寺を視察
お寺は有馬富士の近くでのどかな田園風景が広がっていました。
この裏山が現場になります。50年生くらいのヒノキの放置人工林が広がっていました。
今年、1月8日、いよいよ伐採開始です。
伐採初日は雪が少しちらついていました。
みんなでチェンソーの扱いを再確認
地元の方と伐採方法の確認
チルホールという牽引機を使って、伐採木がお寺の方に倒れないように気をつけながら伐採。
お昼は地元の方がお釜で炊いてくださったおいしいご飯をいただきました。この方は家中のお風呂、炊事、ストーブなど燃料のほとんどを薪で生活しておられるそうです。
伐採後はみんなで玉切り枝打ちなどの林床整備。
この日は12本伐採して処理。
伐採前
↓
伐採後
見上げると、少し空間ができてきました。
ここは、奥山ではありませんが、昨年、この近くでも、ツキノワグマの目撃が数件あったそうです。
里にたくさん仕掛けられたイノシシやシカ用の捕獲罠には、ヌカなどのおいしい餌が入っています。
何キロ先からでも察知できると言われるほど嗅覚がずば抜けてすごいと言われるクマを、人間が大量罠設置によって里に呼び寄せていると指摘する人もいます。
くまもりは、クマだけを守ろうとしているわけではないので、野生動物が棲める山を少しでも増やしていくために、今後もこのような里にある放置人工林でも、機会があれば、伐採していきます。
お寺の裏山の人工林を、くまもり本部が無料伐採その2 兵庫県三田市 1月19日
1月19日、この日は三田市のお寺の裏山の伐採第2回目です。
前回の伐採で少し空が明るくなったと感じましたが、外から見るとあまり変わっていません。
この日はまず、建物に一番近くて、危険な立木に印をつけていきました。
前回同様、チルホールを使いますが、今回は枝打ち用のはしごを持ってきたので簡単に滑車を掛けることができました。
枝打ち梯子に昇って作業風景を撮影するとこんな感じです。玉切りした丸太が斜面を転げ落ちないように伐根(伐採した後の株)に引っかけるようにして置いていきます。
この日初めてボランティアに参加された方ですが、普段からチェンソーを使って公園整備などをしているので、慣れた手つきでどんどん玉切りしていきます。

一人でこんな丸太も持ち上げます。あまり無理しないで!(笑)
この日は16本切りました。だいぶ林内が明るくなってきたと感じます。
ヒノキで40cmは結構太い方だと思います。樹高は24m程でした。
お寺にある柿の木にはたくさんの実がついており、いろんな小鳥が柿を食べにやってきます。
この日は、前回窯でごはんを炊いてきてくださった地元の方の自宅にお邪魔しました。
玄関にも太陽光パネル。これは携帯の充電用だそうです。
ここでお釜のごはんを炊いたそうです
室内に設置された薪ストーブ
お風呂も薪で沸かしています
ここまで徹底して薪を利用し、自然環境に優しい生活をされており、とても勉強になりました。
このお寺の伐採はあと数回で終わってしまうと思いますが、ここでできた地元の方々との人間関係を今後も大切にしていきたいと思います。
1月15日 尼崎市の小学校で環境教育
1月15日に、兵庫県尼崎市内の小学校で、
3学年を対象に、環境教育をさせていただきました。
今回は、8人で授業に臨みました。
5年生『森と人間』
前半は、私たち現代人にとって森が必要かどうか、
昔と今の生活を比較しながら考えていくプログラムです。
さすが上級生、少し難しいお話でも、みんな真剣に耳を傾けてくれました。
後半は、森の現状とこれからについて。
8000年前から今に至る、世界の森の面積の減少を図示したところ、
子どもたちからは驚きの声があがりました。
1年生『もりとどうぶつ』
クマの食べ物クイズや紙芝居を通して、森が動物にとって
なくてはならない存在であることを伝えるプログラムです。
食べ物クイズでは、みんな元気いっぱいに手を挙げてくれました。
一方、紙芝居が始まると、子供たちは、とたんに真剣なまなざしに。
子どもたちが集中して参加してくれている様子に、私たちもやりがいを感じました。
3年生『森の力と動物』
自然の森と人工林を、「動物」「土」「水」「建材」の4つの観点で比較しながら見ていきます。
各観点をクイズ形式で見ていくのですが、みんな活発に発言してくれました。
木の根っこ比べでは、「おお~」とみんなどよめきの声。
視覚的な授業の大切さを実感します。
環境教育を終えて
今年も、子どもたちから大きな元気をもらい、楽しい一日となりました。
そして、授業者として、今回もたくさんのことを学ばせていただきました。
森や自然とかかわる機会の少ない都会の子どもに、
どうやったら自然の事を伝えられるのか、時々悩むことがあります。
しかし、実物を見せたときの、子どもたちのきらきらとした表情に、
子どもたちの心の中には、もっと自然を知りたいという意思があるように感じました。
私たちの環境教育が、子どもたちの自然への興味関心を引き出す
きっかけになれればと願い、これからもがんばっていこうと思います。
この学校で授業させていただくのは、今年で連続13年目。
毎年、環境教育の機会をいただけていることに、心から感謝です。
関係者の皆様、本当にありがとうございました。
<くまもり本部環境教育チーム定例会のお知らせ>
環境教育部は、毎月第2金曜日午後13時から、
西宮市の本部事務所にて定例会を開いております。
次回は、2月13日(金)13:00~です。
現在は‘水’をテーマにした新プログラムを考案中。
初めての方でも大歓迎ですので、どうぞ、お気軽にご参加ください。(SY)
1月5日 謹賀新年 クマ(大型野生動物)とも共存すべき
同じ国土に住むもう一つの国民<野生動物>を殺さない国に
狭い移送檻に閉じ込められて6か月の大阪府豊能町誤捕獲グマ 2014年12月撮影
平成は、野生動物大量補殺国家
野生動物による農作物被害等が増加していますが、人間が彼らの生息地を大破壊したことが原因です。
国も行政も研究者もマスコミも、このことを隠して、ハンター養成やジビエ料理推奨に躍起です。
その上、今春からは、環境省の方針で野生動物捕殺株式会社が各地で認可され、更なる野生動物大量補殺が展開されます。
野生動物を殺すと、国からお金がもらえるのです。(私たちの税金です)
今春から、殺したシカは、野山に放置していいことになります。(今も、県によっては100%近く放置されていますが)
放置されたシカの死体に、クマを初めいろいろな動物が群がっています。
バランスが取れていた生態系は、こうして人間が手を入れ回るのでもう無茶苦茶になっていっています。
鳥獣被害問題の解決は、人間が動物の棲める森を復元して、棲み分けを復活するしかありません。
これ以外の解決法は全て失敗します。
1月5日 森・・・造り過ぎた人工林の3分の2を、自然林に
くまもりは、今年も、森と動物を守る活動を、地元の人達と協力して推進していきます。
ひとりで胸を痛めているだけでは、世の中は変わりません。
賛同して下さる方は、どうぞご入会下さい。みんなで力を合わせましょう。
・全生物(人間も含む)のため、造り過ぎた全国人工林の3分の2を、自然林に戻す。
・酸性雨で弱っている自然林を、炭撒きなどで元気にする。
スギの間伐&除去
2013年度皮むき間伐した山が、ずいぶん明るくなってきました。(京都府支部からの活動報告2014.12.22より)
NPO法人奥山保全トラスト所有の京都府京北トラスト地渡辺保護区 2014,12,21撮影
皮むきされたスギが枯れて、日光が地面を射すようになり、見事に林内が明るくなってきています。
この写真を見たら、皮むき間伐に自分も参加してみようという人が、増えるのではないでしょうか。皮むき間伐は、小学生でもできます。
訪れる人もなく、チェンソーを担いで歩くのも大変な奥山での自然林復元には、短時間に大量に間伐できる皮むき間伐が最適です。
チェンソーによる皆伐や間伐が向いている場所では、今年もチェンソー使用します。
12月7日 やってよかった、第7回くまもり東京シンポジウム
- 2014-12-07 (日)
- くまもりNEWS
大変遅くなってしまいましたが、第7回東京シンポジウムの報告です。
会場となったお茶の水女子大学の正門からの風景
東京都支部新スタッフのみなさんが、ほとんど自分たちで第7回東京シンポジウムを企画運営して下さいました。本当にありがとうございました。ご苦労様でした。
最近、集会の参加者が減っています。東京都支部のみなさんが一生懸命呼びかけてくださいましたが、なかなか人が集まらず、本部としても気が気ではありませんでした。直前になってやっと参加者が増え始め、最終的には110人の参加者を得ることができました。年末の忙しい時期に、又寒い中、ご参加くださったみなさん、本当にありがとうございました。
東京都支部スタッフのみなさんや東京都の会員のみなさんを元気づけたい一心で、本部からは会長と青年スタッフ3名が参加させていただきました。会員のみなさん、どうしたのですか。無力感を感じているのですか。もっと元気を出しましょうよという感じでの参加です。
(会長講演要旨)
「森や動物の惨状を見て、何とも思わない人もいるが、それはそれでいいではないか。わたしたちは胸が痛む。国のあちこちで弱い者いじめが横行している。知って知らんぷりできない。福島、辺野古、リニア大鹿村・・・。力を合わせて、声を上げよう。孤立していてはダメ。一致団結。くまもりの旗のもとに集結せよ。メディアは最高の国家権力と言った人がいるがその通りだ。今や日本の大手メディアは国家権力とぴったりくっついて、国民世論を誘導をしている。何が真実かわからなくなってきた。国民はメディアに振り回されている。
今年、10月末までに3414頭のクマが有害駆除された。大変な数なのに、国民が以前のように騒がなくなった。理由は簡単。報道されなくなったから。みんな知らない。声を上げられない。テレビや新聞にだけに情報を頼っていたら、真実が見えなくなる。洗脳されるだけ。いろんな集会に積極的に参加して真実を見極め、大人の国民としての責任を果たそう。逃げない人生を、誇り高く歩もう」
講師の先生方のお話はとてもよく準備されており、参加者に大変好評でした。先生方、本当にありがとうございました。
「野生動物と悪化する生息環境」 金井塚務氏
(参加者の感想)一口に水環境と言っても、滴り落ちる水、たまり水、湧水、勢いよく流れている水・・・水の状態によって、生息することのできる生き物たちがみんな変わってくるというお話は、目から鱗。今まで気づかされていなかった野生動物にとっての生息環境の大切さが、改めて見えてきた。これは、現地を歩いてしっかり調査している人の話だと納得した。もっともっとお話をお聞きしたい。
「日本の水とリニア新幹線」 橋本淳司氏
(参加者の感想)リニア新幹線にこんなに問題が多々あったのか。初めて聞いた。いかにマスコミが、大事な情報を国民に伝えていないか気づかされた。橋本先生のお話はとても分かりやすく、時のたつのを忘れて引き込まれてしまった。
第7回東京シンポジウムを成功させた、東京都支部川崎支部長とスタッフのみなさん
最後、スタッフのみなさんのお顔が輝いていましたよ。
結果的には、これまでの東京シンポジウムと比べると参加者は少なかったのですが、スタッフのみなさんは自信を付けてさらにやる気になってくださっていたし、参加者のみなさんも非常に熱心に集中して参加して下さり、満足度の高いシンポジウムになりました。本部としては、この日の講演内容や質疑応答については、機会を見て何らかの方法で全会員のみなさんに伝えたいと思っています。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ