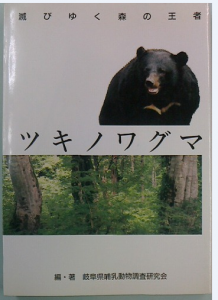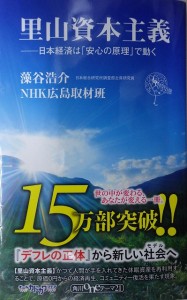くまもりNews
2月9日 環境省主催 広島県での「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」に300人
各県で環境省が順次開催している、「すごいアウトドア!狩猟の魅力まるわかりフォーラム」。
広島県での参加者は300人を超え、これまでの最多だそうです。若いカップルも結構多く参加していました。環境省のねらい通り、狩猟が、うまくファッションに結び付けられたのかもしれません。
野生動物たちとこの国で共存したいと願っている私たちは、行政の考えや仕組み、狩猟や有害捕殺、猟友会などの現状についても、知っておかねばなりません。いろいろ勉強してきました。
●狩猟者数変化グラフが、1970年以前も提示するものに換えられていた
環境省はこれまでのフォーラムで、狩猟者が減る一方だから狩猟者を増やさねばならないと、まるで、狩猟者が減ったことが、動物たちが里に出てくる唯一の原因でもあるかのように、狩猟者が減り始めた1970年以降の狩猟者数変化とシカやイノシシの捕殺数増加グラフを対比させて提示してきました。
しかし、昨年秋、熊森協会が、「環境省のグラフ提示は、狩猟者が減ったから里に出てくるシカやイノシシが増えたと、世論を単純誘導をしている。以前はもっと狩猟者が少なかったがときもあるが、シカやイノシシはほとんど里に出てこなかった。1970年より以前の今より狩猟者が少なかった時の狩猟者数データも提示すべきだ」と申し入れ、環境省が改善を約束した経緯があります。
広島のフォーラムでは、1970年以前は今より狩猟者が少なかったという事実を示すグラフに取り換えられていました。環境省が約束を守ってくれたことを知り、うれしかったです。
しかし、集まった多くの参加者の方々は、最近シカやイノシシが里に出てくるようになった原因を、深く追究しようという雰囲気にはなく、提示グラフが変わったことに対して、別に関心もない感じでした。
全国的にはシカの被害が問題となっていますが、広島県ではシカ被害よりもイノシシ被害の方が問題だそうで、猟友会の方も、イノシシ被害の話ばかりされていました。
●錯誤捕獲が多く、問題になっているくくり罠
くくり罠は県によっていろいろな種類のものがありますが、広島県では、この真ん中にあるものがよく使われているそうす。自作で1000円ちょっとで作れるそうです。これだと、誰でも罠が仕掛けられそうだと思いました。
環境省は、クマの誤捕獲を避けるため、クマ生息地ではくくり罠の直径を12センチまでとすると規制しています。輪っかの一番短い部分が12センチであれば良いということで、ワイアーが固定されているわけでもなく、12センチ規制が本当に守られているのだろうかと不安に思いました。
また、たとえ、12センチ規制が守られていたとしても、タヌキやキツネなどのご捕獲を防ぐことはできません。これらの動物がかかると殺してしまうしかないとハンターに聞いたこともあるので、くくり罠の使用は本当に問題だと思いました。
●誤捕獲グマ対策付きの、新型クマスルー檻
写真の箱罠は、5万円~10万円です。もし、クマが誤ってかかったら、丸い部分を持ち上げて上部を外し、クマを逃がすことができるようになっています。これまでの、クマスルー檻だと、上の脱出口が開いたままでした。これだと、賢いクマが、餌を食べては脱出口から逃げるという行為を繰り返すので、それを防ぐように改良されたものです。
●銃のコーナーは人だかり
銃のコーナーには、散弾銃と空気銃が置かれていました。どちらの銃も重くて、なかなかうまく扱えそうにはありませんでした。実際は、銃免許を取得するには警察の厳しい許可が必要で、罠猟ほど簡単には免許取得はできません。それでも銃猟免許を取りたいという人が多いのか、銃のコーナーは人だかりができていました。
●広島では、有害捕殺されたシカ・イノシシは、すべて焼却
兵庫県では有害捕殺されたたくさんのシカの死体が山に放置されていますが、広島ではどうなのだろうかと思い、質問してみました。広島県ではシカ・イノシシの死体は、すべて、市の焼却施設で焼却しているそうです。山に放置するなんてことは絶対にないと、断言されていました。
少なくとも、広島では、他の野生鳥獣がシカの死肉を鉛弾ごと食べてしまい、鉛中毒に陥ることはないとわかりました。
●野生動物を殺したくない参加者も
参加者の中で定年退職をして農業を始めようとしている方とお話しできました。その方は近所の人たちがイノシシの農作物被害にあわれていることを知って、このフォーラムに参加したそうです。
罠の説明を聞きながら、これでシカやイノシシが捕まえられるのはわかるが、その後は殺さないといけないのかと何度も質問していました。被害はない方が良いが、といって、動物は殺したくないというお考えが伝わってきました。
●<参加した感想>
生息地復元と被害防除が抜けている
ただ狩猟をしたい人だけではなく、少しでも農業被害を減らしたいからと参加された人も多かったように思います。いきなり、動物を殺すという解決法だけを示すのではなく、その前に、動物たちが田畑に出てこないように、①生息地を復元したり、②被害防除策を研究したり、殺す以前のことも教えてあげるフォーラムに変えていくように、環境省に望みます。
今や立派な観光資源、市民の癒し、京都市鴨川の何とも愛らしいヌートリアたち
京都新聞によると、京都市が、鴨川などで繁殖する特定外来生物ヌートリアを、特定外来生物法に基づいて、今春から民間に補殺してもらう計画を策定しているという。京都市はこれまで、農作物の被害がないことから、鴨川のヌートリアの対策に消極的だったが、生態系保全のため、捕獲(=補殺すること)が必要と判断したとのこと。
この生態系保全のためということばが、くせものなのである。専門知識のない一般市民にとっては、「生態系保全のため」という錦の御旗を立てられると、具体性がないため、何のことかさっぱりわからない。行政が、殺さねばならないと言っているから、殺さねばならないのかなと思ってしまう。しかし、実は、行政担当者も、よくわかっていないことが多い。日本の行政担当者は、ふつう3年で担当部署を異動していくため、行政担当者に高い専門性を期待することは一般的に無理である。
では、だれがヌートリアを殺そうとしているのか。「このことによって、だれがもうかるのか」を、考えると、簡単に構造が見えてくる。もうけたい人は、どうしたら行政にヌートリア捕殺予算を付けてもらえるか、考える。常套手段として使われるのが、肩書や権威である。
「専門家が殺さねばならないと言っている」
「大学の教授が、ヌートリアを殺さないと、生態系が保全できなくなり大変なことになると言っている」
行政担当者は、よくわからないので、これらの脅しにいつも弱い。そして、予算を付けてしまう。こうして、殺さなくてもいい命を奪うという残虐なことに、税金を使ってしまうのだ。肩書・権威と、業者は、しばしば裏でつながっているのである。利権のない市民が、もっともっとこういう問題に声を上げていかなければ、命を大切にするやさしい社会は作れない。行政担当者の皆さんには、もっともっと権威を疑っていただきたい。
2月4日、とりあえず現地に行ってみた。
鴨川に着いて、まずびっくりしたのは、野鳥の多さである。いくら川があるといっても、都会のど真ん中に、こんなに野鳥がいるものなのか。
トンビ・ユリカモメ・ハト・ゴイサギ・カモ・カラス・・・見とれてしまう。これまで、トンビなど、はるか上空に飛んでいるのしか見たことがなかったが、ここでは目の前に見ることができるのである。
うーん。歩かなくても駅を降りたところでこれだけの野鳥が見られるなんて、観光地としては、100点満点だ。観光客が大喜びするだろう。
それにしても、ヌートリアに会えるのだろうか。川をのぞくと、いたいた。すいすい泳いでいる。思わず、「ヌーちゃん」と声をかけてしまう。
私たちを見て、人懐っこそうに上陸してきた。そばで見ていると、何とも愛らしい動物だ。我が国は、カワウソを絶滅させてしまったけれど、カワウソの生まれ代わりと思えばいいのではないか。観光客や市民が、楽しそうに眺めている。何とも癒し系だ。また会いに来たいと思う。
この日、2頭のヌートリアに出会えた。人間への警戒心がなくて、人間を信頼しきっている。
京都市役所の担当課を訪れ、ヌートリアはもう日本の生態系の中に組み込まれているので、根絶殺害など今更無意味な殺生はやめてほしいと申し入れる。
担当者に、農作物被害が出ていると言われた。ヌートリアは水系から離れられないのに、どのような農作物被害が出ているのか不思議に思って尋ねると、河川敷で畑をしている人の畑が被害を受けたという。柵をして、防除すれば、殺さなくてもいいのではないか。
熊森としては、外来動物を日本の野に放すことにはもちろん反対だが、もう、日本の野で繁殖して数十年になる動物、殺しても殺しても、すぐに元の数に戻ってしまう動物を、税金で殺し続ける大義名分など何もないと考える。
生態系への、どのような許しがたいマイナス面があるというのか、じっくり追求していきたい。
クマの捕殺緩和ありきは問題 「岐阜県ツキノワグマ保護管理計画第2期案」パブリックコメント募集中③
- 2014-02-10 (月)
- くまもりNEWS
<山にクマが何頭いたっていいではないか 熊森の提言>
2月8日、岐阜県支部の定例会で、長年岐阜県で哺乳動物を調査してこられた講師を招き、岐阜県のクマについての勉強会が持たれました。
その席上、講師の先生が、岐阜でもクマを初め多くの動物たちが、里の食べ物の味をしめたのか、奥山を捨てて里に下りてきていると問題提示されました。
だからといって、里に出てきた野生動物を殺すことばかり考えるのではなく、もう一度野生動物たちが奥山に帰れるように、●人間が奥山から撤退し、野生動物たちが奥山で餌を取れるような●自然林を復元・再生し、大型野生動物と●人との棲み分けを復活させる方向へ持って行くべきだと熊森は提言します。
その結果、奥山に、クマが何頭いたっていいではありませんか。増えたり減ったりするでしょうが、それが自然です。各生物間のバランスを自然界の力によって取りもどせるようにもどしていけば、人間は労力もお金も節約できます。
ちなみに、講師の先生に、最近岐阜県のクマが増えていると思われるかお尋ねしたところ、「増えも減りもしていないように思う。それより、20年前には岐阜県のどこにでもいたウサギやイタチなどの小動物がさっぱり見かけられなくなってしまったのはどういうことか」と、心配されていました。
(その他、岐阜県ツキノワグマ保護管理計画第2期案から)
●人身被害・・・平成19年度以降はほとんどない。
ただし、放獣作業中の作業員の事故が3件発生したため、今後は放獣を十分な安全確保がない限り推奨しない。
→ <熊森から>奥山放獣は、今後も必要。事故が起きないように、作業に従事する職員の研修を深めてもらい、今後も積極的に実行していただきたい。
今後、イノシシやシカの罠狩猟者が増えて、ツキノワグマの錯誤捕獲が増加する可能性あり。
→ <熊森から>箱罠は、上部を開けてクマスルー檻に改良することを義務付ける。くくり罠に誤捕獲された動物は放すことが難しいので、くくり罠は今後、使用禁止にすること。
●有害捕獲・・・市町村の判断で実施。
→ <熊森から>市町村に任せると、結果的に猟友会に任せたことになることが多いので、県の判断とすること。
●有害捕獲されたクマの年齢構成は0~19歳と幅広く、個体群維持について、緊急の危険性は認められない。
→ <熊森から> 各1頭という少ない例では、とてもこのような判断は出せない。
(全体的な結論として)
捕殺上限の撤廃など、全体として狩猟・有害駆除の捕殺緩和案になっているが、岐阜では人身事故、農林業被害とも、平成19年以降、大きな問題は起きていないのであるから、捕殺緩和を行うべきではない。
私たちの税金は、動物補殺ではなく、生息地の復元・再生と被害防除に使ってもらい、どの動物の命も大切にしていただきたい。
この大地は人間だけのものではなく、全生物のものである。彼らには、人間に影響されずに生きる権利がある。
自然界のことはお互い人間にはわからないことだらけなので、今後も偏りなく、いろいろな団体や個人と情報交換する場を持っていただきたい。
岐阜県には本当に豊かな自然が残されているのか 「岐阜県ツキノワグマ保護管理計画第2期案」パブリックコメント募集中②
- 2014-02-09 (日)
- くまもりNEWS
<「岐阜県には豊かな自然が残されている」に対する熊森の疑問>
野生鳥獣をはじめ無数の野生動植物・菌類の存在によって、水源の森が維持形成され、人間はその恩恵を受けて生きている動物である。
しかし、このことを忘れ、近年、人間はかれらの生息地である自然を、開発や人工林で全国的に破壊し続け、かれらを追い詰めてきた。
そして、自分たちのしてきたことを棚に上げ、「人身被害」「農作物被害」「林業被害」等と、鳥獣が存在することへの感謝を忘れ、被害ばかりを強調して騒いでいる。
人間のことしか考えないという、この日本人の倫理観の低下には、嘆かわしいものがある。
被害を受けたくなければ、生息地の復元や被害防除など、人間側も努力しなければならない。それをせずに、環境省を筆頭に、国を挙げて野生鳥獣を殺すことだけに躍起になっている。その様は、もはや狂気であり、今こそ、日本人の冷静さが求められる。
今回の、「岐阜県ツキノワグマ保護管理計画第2期案」を読んで感じたのは、クマの生息地環境に関するどの資料も、岐阜県の自然環境の悪化がわかりにくいように意図的に工夫して提示されているということである。(図4の岐阜県の広葉樹林面積の推移グラフ、図5の岐阜県における林地開発許可の推移、図6の岐阜県のナラ枯れ被害量の推移)
岐阜県には豊かな自然環境が残されているとあるが、本当だろうか。岐阜県の人工林率は県平均44%にも上っており、残された自然林もナラ枯れのすさまじい脅威に見舞われたばかりで、クマたちの命を支えてきたミズナラの巨木群の復活には、何百年かかるか見通しも立たない。奥地まで観光地開発が進んでいる。このような現実がわかるように、正々堂々と現状を提示すべきである。
平成5年に岐阜新聞社から出版された「滅びゆく森の王者ツキノワグマ」岐阜県哺乳動物調査研究会編という本がある。
この本は、岐阜県の主に教師たちが集まって、地道な調査研究を続けた結果をまとめたものである。この本には、岐阜県のツキノワグマが絶滅への道をたどっているのではないかという視点からの記述が、各所にある。
「恵那山の原始林といわれていた御料林を1本残らず伐ってしまったところ、クマの餌になる木はなくなり、山は崩れ、クマのねぐらもなくなってしまった」など、クマの数が急減している所もあるなどの証言がたくさん載せられている。
民間と行政の現状認識の差には愕然とする。
最も、もっと自然破壊が進んでいる都府県も多くあるので、そこと比べるとまだ自然が残っている方だということは言えるが、だからこそ本来の自然生態系を真剣に取り戻してもらいたいと思う。
岐阜県ツキノワグマが2.7倍に増加?! 「岐阜県ツキノワグマ保護管理計画第2期案」パブリックコメント募集中① 2月14日締め切り
- 2014-02-09 (日)
- くまもりNEWS
岐阜県庁パブリックコメント資料は、以下をクリックください。
「岐阜県特定鳥獣保護管理計画(ツキノワグマ)第2期(案)」 に対する県民意見募集(パブリック・コメント)
(熊森から)
平成26年3月作成の岐阜県ツキノワグマ保護管理計画第2期案の1ページ目に書かれた「背景」文は、ツキノワグマについて述べられた文としては、ツキノワグマを害獣視しない、大変すばらしいものです。
しかし、その後に続く岐阜県の第2期案は、ひたすら岐阜県のツキノワグマが増えていると書き続け、保護対策を必要としない安定存続個体群であるという記述になっています。残念であると同時に、とても認められない内容です。
<生息推定数増加説へのくまもり反論>
岐阜県のツキノワグマは、本当に増えているのでしょうか。増えたか減ったかというのは、いつと比べてかで、答えは変わります。計画案にある以下の昭和44年~平成24年までの岐阜県ツキノワグマ捕獲数推移グラフを見ると、ツキノワグマの捕獲総数は、平成以降、かなりごそっと減っています。
銃猟狩猟者が減っていることを考慮しても、罠猟狩猟者はかなり増加しており、また、有害捕獲技術(クマに罠使用可)もどんどん向上しています。この点を考えると、ツキノワグマの生息数が増えているとはとても考えられません。
今回の岐阜県の計画案で、岐阜県のツキノワグマが増えているという根拠として、岐阜県が示した資料記述は、以下です。
平成16年~23年までモニタリング調査を行い、兵庫県立大学准教授(=環境省中央環境審議会委員)が、科学的根拠を伴う有害捕獲数、出没情報件数などから得られたデータをもとに、ブナ科堅果類の豊凶の影響を補正し、MCMC法によるベイズ推定法を用いて、生息数を推定した。
その結果、平成23年度岐阜県ツキノワグマ生息推定数は、
●北アルプス地域個体群中央値が1353頭(90%信頼限界値は428~4548頭)、
●白山・奥美濃地域個体群が644頭(90%信頼限界値は231~2124頭)
となっており、
平成16年の北アルプス地域個体群の推定生息数中央値は500頭、白山・奥美濃地域個体群の推定生息数中央値は300頭で、7年間にそれぞれの地域個体群のツキノワグマは、2.7倍と、2.1倍に増加した。(注:平成16年度の推定生息数は実数が出されていないため、グラフから読み取りました)
それぞれ、年平均増加率は25.2%、23.7%である。
岐阜県は2010年を中心に、ナラ枯れによって、クマたちの生存を支えるミズナラの巨木を大量に失っています。しかも、動物たちが棲めないスギだけヒノキだけの人工林は山林面積の44%もあり、今もそのままです。
クマの生息数がどんどん増えていく要因など何もないと思われるのに、どうしてそんなにどんどんツキノワグマが増えていくことになるのでしょうか。
実は、2011年、兵庫県でも、
MCMC法によるベイズ推定計算の結果、ツキノワグマの年平均増加率が一時期22.3%と発表されたことがあります。
しかし、熊森が協議会で委員として、「あり得ない」と猛反発しただけでなく、県の審議会でも、複数の研究者から、「クマの増加率がシカより多いということなどありえない」という反論があり、増加率が、一挙に11.5%に下方修正された歴史があります。(専門家に問い合わせると、MCMC法によるベイズ推定というのは、どのようなパラメーターをどう入れるかの個々人の恣意的な判断により、いかようにも結果を変えられるもので、増加率11.5%さえ、真偽のほどはわからないとのこと。計算過程を1からすべて公表していただきたいものです)
MCMC法は、コンピューターを何日間も使って推定生息数を計算する方法だそうですが、だからといって正確な推定数が出るわけでもないことが、この時わかりました。
しかも今回の岐阜県の生息推定数は、下方推定数と上方推定数の間に10倍以上の差があり、これはもう推定の枠を超えているのではないでしょうか。
北アルプス地域個体群が、428頭かもしれないし、4548頭かもしれないと言われれば、どちらに合わせればいいのか、対応策などとれないのではないでしょうか。
生息推定数を出したのが、大学の研究者であるとしても、岐阜県の検討会や審議会の先生方や岐阜県庁の担当者の中で、こんなデータは使えないという声が出なかったのか、不思議に思います。
なぜなら、今回、MCMC法によるベイズ推定によって、平成16年~23年までの間の岐阜県ツキノワグマの生息数推移推定が出されていますが、この間、平成18年と平成22年に、奥山の実りゼロという異常事態が発生して、奥山で生きられなくなったクマたちが里に出てきて、それぞれ280頭とみられるほどの大量補殺がなされたのです。
にもかかわらず、生息数推移推定グラフでは、生息推定数はがくんと減っておらず、反対に増えていることになっている場合もあります。2011年の兵庫県の場合も、当初は今回の岐阜県モデルと同じでしたが、修正後は、がくんと減らされました。
100歩譲って、たとえ平成16年~23年までの間に岐阜県のクマが2倍以上に増加したとしても、このような短期間だけの増加を見て、今後5年間、岐阜県のクマは、狩猟を禁止または自粛したり、有害捕殺の上限を決めるなどの保護対策をとる必要がないなどと、どうして結論付けられるのか、大いに疑問であり危険だと感じます。
まずは、岐阜県のツキノワグマが以前と比べて増えているのか減っているのかの判断の正当性から、検討されるべきでしょう。
林野庁を林業から解放し、奥山の国有人工林を、まず自然林にもどすべき 参考書籍:里山資本主義
わたしたちが、人工林率60%70%80%という、針葉樹一辺倒の奥地の行き過ぎた人工林の大変な弊害を訴え続けて22年。
しかし、台風や大雨という自然の力が人工林を倒していく以外、人工林は放置されたままで、一向に、人為的な力による
人工林→自然林
の転換が進みません。
奥山生息地を壊された野生動物たちは人里に出てくるしかなく、哀れにも、人間によって有害獣のレッテルを張られ、大量殺害を受け続けています。
国や研究者、行政の指導で、地元の人たちの中には、動物を殺すことが当たり前のように洗脳される人たちが出てきているようで、心配です。
殺生をしない。生き物の命を大切にする。
これは、日本人のすばらしい特性であったはずです。この文化があったからこそ、日本には自然が残り、豊富な水があり、今日の繁栄があるのです。
自然を守るには、自然への畏敬の念や、同じ生きとし生けるものとしての生き物への深い愛情があればよく、高度の学問も研究者も科学技術も不要です。
かくなる上は、
林野庁を林業から解放し、奥山国有人工林を自然林に戻していっていただく
しかありません。
林野庁に電話をして、前提となる現在の債務について尋ねてみました。
<林野庁債務> 2014年1月31日現在
一時期3兆8千億円まで膨らんだ累積赤字ですが、1997年、2兆8千億円が、国により補填され、残り1兆円の債務(国や銀行から借りたため、返さなければならないお金)となりました。
しかるに、この1兆円の赤字ですが、現在、1兆2700億円まで膨らんでしまいました。
林野庁はこれまでの特別会計から一般会計になり、職員の給料は国から出るようになりました。
あとは、木を伐って売って、1兆2700億円の債務(内訳、銀行に8000億円、財務省に4700億円)を返していけばいいだけです。
ちなみに、平成24年度返還できたのは41億円だそうです。これでは永遠に、林野庁は奥山の木を伐り続けなければなりません。
熊森は、2兆8千億円に引き続いて、1兆2700億円の債務も、国が補填して下さることを望みます。戦後の森林政策が失敗したわけですが、これは、林野庁だけに責任があるものではなく、行き過ぎた拡大造林に反対する声を上げなかった国民にもあると思います。
林野庁が林業から解放され、奥山国有人工林が保水力豊かな自然の森に戻されていくなら、国民にとってはこちらの方が、はるかにメリットがあると思います。林業は、里山民有林で行うようにすれば、伐り出しも簡単になります。(以下、参考書籍)
林野庁を、森林保全庁とし、今後は森林保全業務のみ行うようにしていただくことを提案します。
みなさんは、どう思われますか。
政府は今国会で、さらなる狩猟の規制緩和に向けた捕殺一辺倒の「鳥獣保護法改定案」を提出
1、罠猟網猟の免許取得年齢
現行 20歳以上 → 18歳前後の適切な年齢に引き下げる。
2、狩猟可能時間帯
現行 日の出から日没 → 都道府県や国の事業に限り、24時間、銃の使用可能。
3、捕獲者
現行 ハンター → 捕獲等を行う事業者の認定制度を創設し、効率的な捕獲をめざす。
<以下、新聞報道から>
各地で野生のシカやイノシシが急増し、農作物の食害や貴重な生態系への影響が広がっていることを受けて、環境省の諮問機関である中央環境審議会は、1月27日、生態系や農林業に被害をもたらすシカやイノシシの駆除を進めるため、民間の専門業者や団体に、捕殺してもらう制度を新設することを大筋で了承した。
環境省は、1999年に導入した個体数調整から、さらに捕獲を強化し、積極的な鳥獣管理(=鳥獣補殺)へ政策転換する。
( 熊森から)
今でも、わが国には狩猟監視員制度がなくて違反狩猟が横行しているのに、18歳狩猟者、24時間銃OK、利潤第一の民間業者に補殺を任せる・・・日本の野生動物は、人間に命をもてあそばれて、もう生きていけなくなる。人間には、こんなことをする権利など絶対にない。
地球は人間だけのものではないし、人間に自然生態系のバランスをコントロールする力などない。
くまもり新年の誓いは、この国の奥山の風景を変えてみせる(=自然林にもどす)
- 2014-01-30 (木)
- _奥山保全再生 | くまもりNEWS | 公益財団法人奥山保全トラスト
自然生態系は、絶妙のバランスの上に成り立っています。
シカ増加問題に関して、まるでシカに問題があって勝手にシカが増加したように、環境省はとらえておられるのでしょうか。
環境省は、ハンターを増やしたり、民間捕殺会社を創設したりして、シカを殺せばシカ増加問題が解決するかのように、次々と殺害強化法案を出し続けていますが、そんな単純な問題ではありません。
各地の山で、キツネ、ウサギ、ネズミなど、多くの野生鳥獣たちが激減している問題の方は、どうされるおつもりでしょうか。
食料がなく動物が棲めないスギ人工林を除去中(遠景)静岡県
上記写真の(近景拡大)静岡県2013年11月撮影
シカ増加問題は、人間が、戦後、自然を大破壊した結果、自然生態系がバランスを壊してしまったのが原因だと、私たちはとらえています。
シカも人間の自然破壊の被害者なのです。
自分たち人間がしてきたことを隠し、物言えぬ生き物たちにすべての罪をかぶせるやり方は、銃によってこの地球上で最強となった人間として、この上もなく卑怯であり、いじめの最たるものです。
環境省は、どうして、根本原因である、破壊し過ぎた山の自然林復元に、林野庁が乗り出してくださるようお願いしないのでしょうか。
殺すだけでは解決しない、シカ増加問題。今こそ、壊した自然の復元を!
本部 1月20日 雪の中の痕跡調査
冬の間、クマは冬籠りをしており、活動していません。しかし、最近、冬籠り前の食い込みがしっかりできていなかったのか、雪の中を歩いているクマがいたそうです。顧問の先生に、雪山の調査は危険だからしないようにと言われたのですが、若さを頼りに2人で出かけて行きました。
足にはいているのは、スノーシューです。
地面は白一色でした。冬は、落葉広葉樹が葉を落としているので、山の様子がとてもよくわかります。
動物の足跡やフン尿の跡などの痕跡が見れましたが、クマ棚や爪痕などはなかなか見つかりません。
1m以上の積雪がありました。沢沿いでは、積雪の下が川ということもあると聞いていたので、慎重に慎重に歩を進めました。斜面を登るのにも、普段以上に時間がかかります。
途中でカヤを見つけたので、もしやと思い握ってみました。するとまったく痛くありません!握って痛くないのはハイイヌガヤ。葉がやわらかくてシカの大好物です。兵庫県ではほとんど見かけなくなったと思っていたら、こんなところにありました!
そっくりでも、握ると葉が固くて手がチクチクするのは、チャボガヤです。こちらはシカも食べないようで、兵庫県では、下層植生としてチャボガヤが群落になっている所があります。
目的地は標高800mくらいでしたが、その辺りまで行くとブナ・ミズナラ帯になります。GPSで記録しながら進みました。なだらかな森が広がっておりとても美しかったです。
やっとブナの木に、クマの痕跡を発見しました!新しい爪跡です。このあたりにクマが来たことがわかりました。
林道は積雪が少ないのか、不思議とスノーシューなしでも歩けました。動物も、林道の方が歩きやすいのでしょう。林道の動物の足跡は、林内よりも多いと感じました。雪の林道を歩くだけで、いろいろな足跡に出会え、とても勉強になります。
足跡の明瞭さで、その足跡がどれくらい前につけられたものなのかわかります。
このシカの足跡は、つい今しがたついたくらい新しいなと思って、顔をあげると、案の定、目の前に立派なオスジカが1頭いて、逃げて行きました。この日出会った唯一の動物です。
尾根付近の景色は本当に素晴らしく、1m以上の雪が積もっている上を歩くと不思議な感覚があります。
厳しい場所が多かったのですが、何とかクリアーして進みました。しかし、帰るルートが見つからなくなり、適当に歩いていくとかなりの急斜面を降りなければならなくなり、そこを回避するために沢を渡ったり、人工林内を進んだりと、だいぶんじたばたしてしまいました。やっと林道に出れたときは、生きて山を出ることができたことを2人で喜び合いました。
雪山は、歩く前にコースをきちんと設定しておかないと、死の危険があると痛感しました。また、スノーシューがないと絶対に無理です。スノーシューをはいていても、足が埋まってしまって抜けなくなることもありました。途中で、もし、このスノーシューをなくしたら、足が埋まってしまってもう二度と歩けないと思うと、こわくなりました。
この日は一日中天候も良く、とても気持ち良く調査をすることができました。雪山の静寂さなど、貴重な体験ができました。しかし、これだけの大変な思いをして雪山に登っても、動物のくらしはほとんどわかりませんでした。みんな、どこで何をしているのだろう。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ