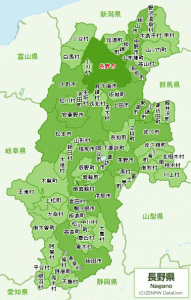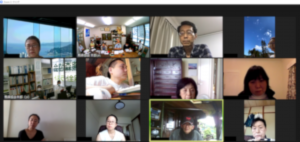くまもりNews
新潟県南魚沼市の親子グマ放獣報道に関して
- 2020-06-19 (金)
- くまもりNEWS
南魚沼市が昨年12月に捕獲した親子グマを、今春、南魚沼市の山に放獣することは、南魚沼市の了承を得て、当協会と南魚沼市がずっと共に進めてきたことです。
しかるに、6月17日、新潟県のテレビニュースで、当会が5月上旬、新潟県南魚沼市の奥山に親子グマ3頭を放獣した件について、誤解を生むような報道がなされました。
放獣に至った経緯を、以下の通りみなさまにきちんとご報告しておきます。
昨年、12月9日、南魚沼市の診療所の縁の下で冬ごもりに入ろうとしていた親子グマが捕獲され、殺処分されそうになっているところへ、当会本部職員が駆け付けました。
この年、新潟県では生息推定数の58%にものぼる大量のクマが捕殺されており、クマと共存するためには、非捕殺対応に変えていただかねばならないと当会が判断したからです。
この親子グマに関しては、母グマが痩せすぎていたため、冬ごもり中に死亡する恐れがありました。そこで、当会でいったんこの親子グマを保護し、来春、山に放獣したいと申し出たところ、南魚沼市も了承されました(これについては、南魚沼市からも同じ旨の報道発表がなされています)
たくさんの方のご協力のもと、親子グマは安全な飼育環境の中、健康な状態で無事に冬を越すことができました。冬の間、当会は、放獣計画を提出するなど南魚沼市と放獣計画について協議をしてきました。
奥山の雪解けがはじまる4月に入り、放獣の準備のため当会職員が現地調査を行い、山にクマの春の食糧が十分にそろっていることを確認し、より詳細な放獣計画を提出しました。
南魚沼市の担当者からは、林道の除雪は南魚沼市でやりますから、放獣は熊森さんでお願いしますと言われていたため、準備万端整え、市からの放獣実施日の連絡を待っておりました。
南魚沼市は、放獣へ向けて調整しているようでしたが、具体的な放獣の日程が決まらないようで、時が経過していきました。
当会は、地域にとって最も安全にクマを放獣できるのは、バッコヤナギの花やブナの芽など山にクマたちの春の食料が豊富に出そろい、緊急事態宣言下で登山や山菜採りに入る人が少ない今しかないことを何度も市にお伝えし、あの手この手で放獣実施日の指定を催促し続けましたが、まだ日が決まりませんというお返事が続きました。
狭い檻の中での3頭の暮らしがもはや限界であることや、5月に入り、ほぼ密閉状態の保冷車の中が30度を超える状態となり、クマたちがいつ熱中症になってもおかしくない状況になってきたという報告を現場から受けたため、これ以上、放獣を遅らせることができないと判断、やむを得ず、当会の方で急遽、奥山に親子グマを放獣、その後、すぐに南魚沼市に報告をさせていただきました。人にとってもクマにとっても、最も安全に放獣できるタイムリミットでした。
公表が遅くなったのは、南魚沼市に公表の仕方について協議を求めていたのにもかかわらず、1か月近く待っても、とうとう市からのお返事がなかったからです。
親子グマは人慣れしないように保護しておりましたので、放獣の直前段階でも、人に対し強い警戒感を持っていました。このような場合、飼育グマを山に放しても、人間の所には帰ってこないことが、過去のいくつもの実験例から確かめられています。人間の所に戻ってくるのではないかというのは人間の思い込みにすぎません。
この親子グマも予想通り、人間の所には戻って来ませんでした。
市に提出した放獣計画にのっとって当会職員が、放獣後1週間、現地をパトロールし続けましたが、親子グマはもはや影も形もありませんでした。
今頃は、奥山の広い山野を駆け巡っていることでしょう。
不自由な狭い檻の中になど、二度と戻りたくないのだろうと思います。
徳島県南部で新たに那賀・海部・安芸大規模風力発電計画 みんなで意見提出を!6月23日締め切り
- 2020-06-15 (月)
- くまもりNEWS
徳島県では山の命である尾根筋に大規模な風力発電施設を作る計画が次々と出されており、多くの人々が故郷の山を守るために反対しています。
徳島県天神丸風力発電事業計画(オリックス株式会社)の予定地を初視察(2018年7月26日くまもりブログ参照)
熊森は風力発電に反対しているわけではありませんが、取り返しがつかないまで山を大荒廃させてしまう尾根筋への風力発電は認められません。水源の森を失い次世代が困ります。山のすべての生き物たちが被害をこうむります。
この度、徳島県南部でまたしても、山の尾根筋に大規模な風力発電施設を造る計画が持ち上がりました。
那賀・海部・安芸風力発電事業計画(那賀・海部・安芸風力発電合同会社)
計画地は、徳島県南部の那賀町、海陽町、高知県馬路村の3つの自治体にまたがっています。
現在、環境配慮書が公開されています。
クリックすると、計画の環境配慮書が縦覧できます。縦覧期間は6月23日(火)迄です。
事業者が意見を募集しています。
住民でなくても意見は出せます。
とにかく、一人でも多くの人が環境配慮書を読んで意見を出すことが大切です。
可能な方は、ぜひご協力ください。
【意見書の送付先】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
JAG 国際エナジー株式会社 エネルギー開発部 中橋宛
【意見書の提出期限】令和 2 年 6 月 23 日(火)〔当日消印有効〕
以下は、熊森が作成した資料です。参考になさってください。
<那賀・海部・安芸大規模風力発電計画について>
風車は、ローター部も含め136~161mもある巨大なもので、1基あたりの発電出力は約3200kw、山の尾根筋までに工事用の広い道路をつけ、尾根筋に巨大な穴を掘ってコンクリートを大量に流し込み、最大34基の風車を立てる計画です。20年後はゴミとなりますので、ダイナマイトで土台を爆破して片付けるか、放置されます。山はもうボロボロです。
以下の3つの図は、いずれもwクリックで大きくなります。
今回の計画地の一部にはブナ林が残っており、絶滅寸前の四国のクマが利用している可能性もあります。
この計画では、海陽町を流れる海部川の水源の森が広範囲にわたって開発されることになります。
そうなれば、豊かな森は失われ、山に暮らす野生動物は行き場を失い里に出てきます。
町で暮らす方々の水資源が枯渇する恐れがあります。
徳島県内は、これで2例目の巨大風車計画になります。
徳島県の山が業者に狙われているのだと思います。
「山なんか持っていても1円にもならないでしょう」
「高齢で山の手入れなどもうできないでしょう」
地元の皆さん、業者の無責任な甘言に騙されないようにしてください。
山に木が生えているから、保水力があるのです。
山に木が生えているから、崩れないのです。(放置人工林の場合は別です)
熊森の「クマ乱獲罠の規制を求める署名」に、長野県の猟友会員からびっくりするような声が
- 2020-06-11 (木)
- くまもりNEWS
「クマ乱獲ストップ」2万人署名めざすくまもりズーム会議(2020.6.6)に参加された方の一人がさっそくフェイスブックで署名の呼びかけをしてくださいました。すると、長野県のA市の猟師の方から、なぜこんな署名を集めようとするのか理解できないという声が届いたそうです。
長野は、日本で一番クマが多いと言われる県です。
(長野県のクマの推定生息数は400~15,440頭で中央値は 3,940 頭)
熊森本部はこの猟師の方に電話して、じっくりと話を聴いてみました。
以下は、その方の話です。
うちの町では、クマ、シカ、イノシシを獲ろうとして罠をかけてもほとんどかからない。第一、有害捕獲しても駆除費はゼロだから、獲る気もしない。乱獲している町は、高い駆除費が出るからじゃないのか。
うちの町では、猟友会のメンバーによる罠の管理・見回り体制が厳しく、違法罠などかけられない。通報されてしまう。
クマの捕獲は、年に1~2頭あるが、麻酔をかけて山に放す。集落近くに出てきたクマは県の職員と猟友会で追いかけて麻酔し、山に放しに行っている。シカ、イノシシ用くくり罠はクマがかからないように直径12センチ規制を守っている。クマが誤って罠にかかってしまった場合は確実に放獣している。箱罠にはクマ用脱出口をつけている。
うちの町には、人工林は少ししかない。豊かな山がたくさんあり、多くの動物が住んでいる。(熊森:広大な国立公園がある例外的な地域のようです)
自分は最近、動物が増えてきているように感じる。もし、クマ、シカ、イノシシが増えすぎた時、罠規制などかけられたら、獲ることができなくなる。少なくとも、うちの町では罠規制は必要ない。だから罠規制署名は、全国じゃなくて、罠による乱獲がひどい地域に限定してほしい。
熊森本部としては、こんなにクマの保護体制が整備されたすばらしい地域が日本にあったのかと、感激しました。
2019年度、長野県で被害があったとして有害捕殺されたツキノワグマは359頭です。
一方、有害捕獲したけれど殺さずに山に放したクマは84頭、イノシシ罠などに錯誤捕獲されたクマは416頭で、合計500頭のクマが全て放獣されています。
長野県庁担当課に電話してみました。
長野県には、クマの放獣技術も持っているクマ対策員が各地に計10人いて、すぐ現地へ駆けつける体制になっているそうです。
熊森が以前、環境省に強く訴えて、やっとのことで獲得したクマの錯誤捕獲を避けるためのくくり罠の直径12センチ規制を、上限無制限に一番に緩和してしまった(現在はクマが冬眠中の12月15日~3月15日までの4か月間規制緩和)残念な長野県でしたが、最近はクマとの共存に向けて大きく変化し始めているそうです。
有害捕獲であっても、まだ若いクマや、親子、初めて捕獲されたクマは山に返しているそうです。また、あらかじめ許可をだして不特定多数のクマを捕殺する予察駆除もしていないそうです。
500頭ものクマを放獣するには、地元とのあつれきがものすごくあるだろうと熊森は思いました。しかし、県の担当者によれば「以前なら5人いたら5人が絶対放獣反対の地元だったのが、今では5人とも放獣に理解を示してくれるように変わってきた」ということです。
2014年大阪、イノシシ罠にかかってしまった「とよ」
誤捕獲なのに殺処分されることになったため熊森が保護し今も豊能町で元気に暮らしています
熊森から
クマの人身事故を減らし、共存するために必要なことは、生きられなくなって奥山から出てきたクマを捕殺し続けることではなく、奥山生息地をクマたちに保障し、被害防除や棲み分けの努力をすることです。
長野県の第4期 長野県クマ管理計画(2017年~2022年)を読んでみました。
確かに以前の方針とかなり変わってきており、捕殺を抑えるための放獣の推進やクマと人が棲み分けられるような対策など、保護策や共存策が言葉としてどんどん前面に出てきています。
資料も入れると、全72ページもあり、読むのは大変ですが、被害対策という名目で乱獲を続けている多くの都府県および市町村の担当者にぜひ、読んでいただきたいです。
長野県は、まだクマが棲める豊かな生息環境が残っているようで、奥山が人工林だらけの西日本のクマ生息地とは対照的です。
以下は、長野県ツキノワグマ保護管理計画からの抜粋です。
「ツキノワグマは、生息数と被害発生の間に顕著な因果関係が認められないことから、例年の状況から被害発生を予察して行う個体数調整は原則としてしない。(資料編p2-p16の14行目)」など、熊森の主張と同じ記述が結構たくさんありました。
といっても、昨年度の長野県のクマ捕殺数は359頭にものぼります。
活動を再開した長野県支部にさっそく、長野県全市町村の動向を調べてもらおうと思います。A市のような地域が、長野県にいくつくらいあるのかなど、いろいろ知りたいです。
クマ捕殺ゼロという滋賀県のようなクマ保護行政も例外的にはありますが、ほとんどの都道府県での実態はひどいものです。
今、日本熊森協会は、罠によるクマの乱獲規制を求める署名を集めています。
長野県A市のような地域が増えるように、ぜひ、署名を拡散させてください!
今年は、環境省の特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)の改定年です。
個々の市町村にクマ保護を訴えて回るのは大変ですが、ガイドラインがクマを保護できるものに変わったら、一気に問題が解決します。
そのためには、署名数や熊森協会の活動を応援してくださる会員がたくさん増えることが必要です。
インターネット署名はこちら
紙署名はこちら
まだの方は、どちらか一方に、ぜひ署名をお願いします。(完)
「クマ乱獲ストップ」2万人署名めざし、ZOOMで全国会議
3月末から呼びかけを始めた「クマの乱獲をもたらしている罠捕獲の規制強化」を求める署名運動をパワーアップさせたい。
インターネットのチェンジと紙の署名を呼びかけている熊森本部は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の解除をきっかけに本格的に活動を再開しようとしています。さっそく、全国の支部や会員のみなさんと一緒に署名を集めたいと、6日午後から兵庫県西宮市の本部と各地をつないでインターネットのZOOM会議を開きました。
遠くはニュージーランド在住の会員さんをはじめ、国内では11都府県の計約16人がネットを通じて参加されたほか、近隣在住で直接本部に来られた方も含めると約20人が参加していたたき、にぎやかな会となりました。
罠による捕殺が止まらなくなっている
室谷悠子会長が、署名の目的をまず説明。全国のクマ捕殺数が昨年過去最多で現在もどんどん増え続けていることを取りあげました。
「法律上は許可がない捕獲は違法で、放獣しないといけません。環境大臣も国会でそう答弁しているのに実際は地域で放獣の態勢が全然とられていないため、守られていないのです。狩猟の免許者は減っているのに、罠の免許者は1970年代の数倍にも増えています。山の中にはどのくらい罠があるのか分からない実態で、捕殺が暴走しています」と、室谷会長は訴えました。
さらに「滋賀県のように行政の保護意識が強く、捕殺がゼロの県がある一方、隣の京都府では170頭も殺され、0歳の子グマまでも殺されています。放獣態勢は11府県であるだけで、ほとんどできていないのが実態です」と都道府県の実情を語りました。
捕殺に頼らない棲み分け対策こそ重要
水見本部職員がクマの人身事故が起こった現場を調べた様子や、クマの食べ物が年間の時季によって異なることなども解説。
「地域で人里とクマの生息域を棲み分けるために、山の凶作のときに誘因物となるカキの実を除去しておいたり、梅酒などアルコール、ガソリン、腐った食べ物を外に置かない、突然の遭遇が人身事故につながるので、クマの潜み場となる雑草を刈るなどの対策が必要です。過疎と高齢化で、昔はできていたクマとの棲み分けができなくなっている地域が多くなっている。クマ問題は、社会問題でもあります。熊森も会をあげて、地域のクマ対策を応援する必要があるし、公的な支援も必要です」と捕殺では、クマ問題を解決できないことを伝えました。
署名を集めるためのアイデアはいろいろ
「秋の臨時国会までに2万人の賛同を集めて提出したい。『クマの乱獲をストップさせる法規制や人里との棲み分けを進め、罠にかかったクマの放獣態勢を整えよう』と国民の大きな声として国や都道府県を動かしていきましょう」と室谷会長は訴えました。
署名拡大のためのアイデアを問いかけると、ZOOM参加の全国の会員さんから次々と意見が飛び出しました。
「誕生日に、Facebookでお祝いメッセージをもらったら、お礼のメッセージに『クマ署名に協力してください』と呼びかけたら、たくさんの人が協力してくれました」
「美術館や動物病院などに署名用紙を置いてもらおうと思います」「動物園に置いてもらうのもいい」
「分かりやすくアピールできる、くまもり版のユーチューブを制作してみては」
「とよくんの動画を使ってユーチューブで署名のPRもしてみては」「インスタグラムも効果があります」
いただいたアイデアを生かして、署名拡大に向けてさらに取り組みを強化していきます。
みなさんもぜひ、署名にご協力ください!!
ネット署名アドレスはこちらから
シェアして、広めていただけるとうれしいです。
紙署名はこちらからダウンロードできます。
署名用紙がたくさん必要な方は、本部までご連絡ください。
Tel: 0798‐22-4190
Mail: contact@kumamori.org
尚、署名は、ネットか紙か、どちらか一方だけにお願いします。
<会員限定>7月5日(芦屋市)、11日(オンライン)くまもり活動報告会開催します!
- 2020-06-06 (土)
- くまもりNEWS
新型コロナウイルスの影響で中止せざるを得なかった全国大会に替えて、活動報告会を開催します。全国の皆様にも届くようにインターネット報告会も開催します。森林保全も野生動物との共存も今、動かねばならない問題です。ウイルスに負けず、活動を広げていくため、楽しいひとときを過ごしましょう!
7月5日(日)には芦屋市で、7月11日(土)にはオンライン開催ということで世界中どこにいる会員さんでもご参加いただくことが可能です。是非ご参加お申込みお願いいたします。
会員限定での開催です。ご入会がまだの方はこちらからおねがいいたします!
主なプログラム:
2019年活動報告:森保全、クマ保全について会長、担当者が報告します。
懇親会(意見交換会)
[ in 兵庫県芦屋市]
日時:7月5日(日)14:00~16:00
場所:芦屋市民センター本館401号(兵庫県芦屋市業平町8番24号)
参加費:無料
定員40名
[オンライン開催]
スマートフォン、タブレット、パソコンをお持ちの方ご参加可能です!
日時:7月11日(土)13:30~15:00
参加費:無料
定員50名
事前にお申込みいただきこちらからリンクを送ります。
<お申込み先>
一般財団法人 日本熊森協会
TEL 0798-22-4190
FAX 0798-22-4196
Email: contact@kumamori.org
中檻を外し、プールも解禁 大阪府元野生グマ「とよ」しばらく両後肢の様子を見ていきます
- 2020-06-10 (水)
- くまもりNEWS
昨年夏、突如、原因不明で両後肢マヒとなったとよ。
一時は再起不能かと思われるほど大変でしたが、お世話隊の熱い介護を受けて、1か月後、再び四つ足で立てるようになりました。
しかし、足取りはおぼつかなく、獣医さんからは、運動制限のアドバイスをいただきました。そこで、獣舎内に中檻を設置して、鉄格子に登ったり、プールに入ったりできないようにしてきました。
今年の冬ごもり明けから、毎週お世話日に来てくださるボランティアさんたちや日々エサやりに行ってくださるパートさんたちと皆でとよの後ろ足の動きを観察してきました。おかげさまで、まだ完全ではありませんが、ふだん両後肢を使って歩けるようになっています。
プールの中に階段を造る、スロープを付けるなど、とよの足に合わせたプールの改造計画を、これまで何パターンも考えてきましたが、わざわざ改造しなくても、今の足ではもう自力でプールに出入りできるのではないかという結論となりました。
一刻も早く大好きなプールに入れてあげたい。
その機会を、ずっと考えてきました。5月31日、小雨の中、ついに狭い中檻を外してやり、10か月ぶりに大好きなプールも入ることができるようになりました。プールの内側にあく抜きブロックを積んで階段を造っただけで無改造です。
中檻外し、作業開始
中檻を外し終わる
広くなった獣舎にとよを出しました。
とよがどんなに喜び感激するだろうかと思い、みんなでその瞬間を撮ろうと、カメラとビデオを構えました。
しかし、寝室から出てきたとよは、ミズを食べることに夢中で、獣舎が広くなったことや、プールにきれいな水が張られていることを見ようともしません。「あれえっ」。一同期待外れでした。
ミズを食べるのに夢中のとよ
とよが、プールを見ないようにして避けているのが、ありありと伝わってきます。
昨年、両後肢が悪かった時、大好きなプールに入ったものの上がることができなくなって、もがき続けた怖い経験を思い出したのでしょうか。
お世話隊のボランティアたちに、自ら顔を近づけて嬉しそうに寄っていくとよ。
お世話隊の皆さん、いつもありがとうございます。
とうとうこの日は、とよは広くなった運動場を見てクンクンにおいをかいでまわっただけで、プールにも入らず、獣舎の鉄格子にも登りませんでした。
帰り際に、副住職さんに報告すると、「なに、今日は気温が低いからねえ。気温が上がってきたら入るよ」と、全く気にされていない感じでした。お世話隊の私たちは心配し過ぎなのかもしれません。しばらくは、この環境でのとよの足の様子を見ていきたいと思います。(完)
今どきの新聞 誤報を指摘されたら「ツキノワグマ 大人の雄は『肉食』」記事の問題 中間報告
- 2020-06-09 (火)
- くまもりNEWS
(その1)5月27日、ある新聞社の夕刊全国版に、明らかに学術的に間違った記事見出しが掲載されました。すぐに記者さんに教えてあげなくてはと、翌日、新聞社本社に電話をしました。
かいつまんで話すと、電話に出られた方の答えは、
「記者に電話をつなぐことはしておりません。記事に関するご意見は、読者窓口しか受け付けません」という杓子定規な答えで、とりつくしまもありません。誤報を出してしまったショックや慌てふためきは何もないようです。
執筆した記者にとっては、28年間クマ問題に取り組んできた熊森とつながれるまたとない良い機会だと思うのですが、これでは記者の取材網も広がらず、記者の成長も見込めないのではないでしょうか。
仕方なく、読者窓口に電話をしましたが、時間を変えて6回かけてもいつも話し中でかかりません。
読者窓口に何台の電話を設置されているのか知りませんが、読者の声など聞く気はないということでしょうか。終了時間直前にやっとかかりました。
「伝えておきます」との定型対応のみです。
「伝えておくだけではなく、訂正記事をだしてほしいのですが」
「伝えておきます」
ウ~ン、今はこんなことになっているのか。
これでは国民の新聞離れが一層進むと思いました。
第一、真実を伝える新聞の使命を投げ捨ててしまっています。
問題記事は以下です。クリックで大きくなります。
(その2)ツキノワグマもヒグマも、人間同様、雑食動物です。
人間によって長い間、奥山に閉じ込められてきたクマは、まるでベジタリアンの様な食性になってしまいました。学術書には98%草食で、残り2%は昆虫食となっています。以前、川にダムがないころは、奥山まで遡上してきたサケにありつけたクマも多かったでしょうが、今はそのようなことはほとんど望めません。
平成になって、奥山でシカの餓死個体や駆除個体が多く見られるようになってきました。クマは雑食ですから、死肉があれば食べます。そんな中、地形的に特殊な地域である栃木県足尾で、生きたシカを襲って食べたクマが出現しました。
研究者がどのような統計の取り方をされたのか不明ですが、現在、この地域のクマ成獣オスの15%の食料がシカ肉であったとしても、だからと言って、「肉食」と決めつけるのは大きな誤りです。あくまでクマは大きく草食に偏った雑食動物です。
若い研究者の発表がどのようなものであったかも気になって、大学に電話しました。事務職員に、いくら遅くなってもいいので、特任助教という先生に電話をお願いしたいと強くお願いしましたが、何日待ってもいまだに電話がありません。
この国のマスコミと研究者の在り方に、ぞっとしてきました。これでは真理の追究、真実の報道がなされない国になってしまいます。人間だれしもミスがありますが、指摘されたときに、真摯に聞く、改めて見直す、間違っていたとわかったら訂正する。こんな当たり前の以前できていたことができない国になってきているんですかね。
仕方がないので、新聞社の東京本社編集局長あてに、手紙を出し、以下の2点を要望しました。
1、誤った記事見出しの訂正。
訂正していただかないと、クマなんかこの国から殺し尽くしてしまえという誤った世論をいっそう形成してしまう有害性のある見出しです。
訂正見出し例:「足尾の雄成獣グマの食性の15%はシカ肉」
2、電話1本でいいので、クマの写真無断使用に対する謝罪。
この記事にあるクマの写真は、熊森協会が5年前から大阪府で保護飼育している元野生のツキノワグマのオスで推定10歳のとよ君です。山菜、果物、ドングリなどが主食で、昆虫の代わりに時々小魚を与えていますが、ほぼ草食に偏った雑食です。今も元気で大変穏やかに暮らしています。間違った肉食記事に無断使用されて、お世話隊のボランティア一同大変ショックを受けています。
熊森は、新聞社や記者への個人攻撃は一切考えておりませんので、固有名詞は外しました。真実を伝えていただきたいだけです。
新聞社編集局長からのお返事が来たら、ブログ読者の皆様に再度お伝えします。(完)
ウワバミソウがホント好きだね とよ君
- 2020-06-04 (木)
- くまもりNEWS
京都府ツキノワグマ、昨年過去最多170頭捕殺、熊森のコメントが京都新聞に掲載される
- 2020-06-03 (水)
- くまもりNEWS
熊森本部と熊森京都府支部は、昨年9月に京都府庁を訪れ、京都府がそれまでの保護計画を一転させ、兵庫県の間違ったクマ対応をまねて、2017年より開始した非人道的なクマの捕殺(まだクマが出てもいない春の時点からクマ捕殺許可を出し、集落周辺の箱罠・くくり罠にかかったクマは、シカ・イノシシ罠への誤捕獲も含めてすべて殺処分)を中止するように要望しました。
詳細は、熊森NEWS 2019.11.10参照
しかし、京都府は全く聞き入れず、昨年度、過去最多となる170頭ものクマを大量駆除しました。
いくらなんでも殺し過ぎではないかと疑問に思われた新聞記者から、熊森本部に電話取材が入りました。
以下は、5月29日の京都新聞記事です。
<以下が、記事の内容>
京都府が殺処分したツキノワグマが2019年度、過去最多の170頭に上った。府北部ではクマの出没が相次いでおり、住民は殺処分の件数を評価する一方、自然保護団体は「捕り過ぎで絶滅の恐れがある」と批判している。
府によると、ツキノワグマは府レッドデータブックで絶滅寸前種とされ、生息数は由良川西側の丹後個体群が約900頭、東側の丹波個体群が約500頭と推定されている。
170頭の内訳は京丹後市42頭、舞鶴市39頭、宮津市22頭、綾部市16頭、福知山市15頭、京丹波町12頭、南丹市9頭など。丹波個体群では、府の捕獲上限40頭を上回る83頭を専門家の意見を聞いた上で殺処分した。目撃件数は1460件で、府農村振興課は「ナラなどの実が凶作で出没が多かった。生息数や民家周辺での出没が増えており、人身事故を防ぐために捕獲している」と説明する。
府は02年度からクマの保護を目的に狩猟を禁止し、従来はシカやイノシシのおりに捕まったクマは奥山に放つ学習放獣で対応してきたが、17年度以降は人的被害を防ぐため、集落近くで捕獲されたクマは殺処分を可能とし、17年度86頭、18年度103頭の殺処分した。
舞鶴市の大浦半島は出没が多く、住民団体が府にクマ対策を要望。同市河辺中の会社員男性(64)は「家の中にクマが入ってきた話も聞く。出没が過疎化に拍車をかけている」と語り、同市佐波賀の農業女性(81)は「クマが家の柿の木に来て、家族が夜に軒下にいるのを何度も見た。危害を加えられるかもしれず、殺処分は仕方がない」と話す。
一方で府によると、17年度以降、府内でクマの人身事故は発生していないという。
保護団体「日本熊森協会」(兵庫県西宮市)の水見竜哉研究員は「生息数は正確な数字ではなく、人間が一気に捕獲すると秩序が崩れて絶滅に向かう恐れがある」と懸念する。
クマが本来住む奥山がナラ枯れなどで生息できない環境となり、シカやイノシシをおりにおびき寄せる米ぬかなどの餌が出没を増やしている可能性も指摘。「奥山の状況を調べた上で捕獲を見直すべき。クマは人間を恐れており、音の鳴るものを身につけたり、民家近くの柿の木を切り、クマが潜みやすい茂みを刈ったりする対策も必要」と説明する。
熊森から
クマ生息地の奥山を地道に23年間調べ続けてきた熊森協会の声を取り上げてくださった記者さんに、心から感謝申し上げます。
先日、京都府に隣接する兵庫県豊岡市の山を調査したところ、新たなクマの痕跡が激減しており、ぞっとしました。京都府や兵庫県がクマを大量駆除しているからかもしれません。
稜線の向こうが京都府のスギ人工林、手前は熊森がかつて植林した広葉樹
奥山を広葉樹林に戻したり人間が立ち入らないようにしたりして、クマたちに生息地を返してやることもせず、人間に生息地を破壊され、空腹のあまりエサを求めて出てきたクマをこのまま捕り続ければ、クマは絶滅に向かいます。日本が批准している生物多様性条約にも違反しています。
記事を読んだ、熊森京都府支部員からのコメントです。
Cさん:思ったよりも大きく取り上げられていました。京都府でクマによる人身事故が無くなったのは、クマを殺し過ぎたからではないでしょうか。
Kさん:地域の方の中にも、クマを殺すのはおかしいと思っている方たちがいます。クマが奥山に帰れるよう、生息地を復元したいです。
京都府民の力で、どうか捕殺一辺倒の京都府のクマ対応を方向転換させてください。
京都府農村振興課
住所:〒602-8041 京都府京都市上京区 下立売通新町西入藪之内町
TEL:075-414-5036 FAX:075-414-5039
北海道古平町の山菜採り男性行方不明事件で、ヒグマ研究50年の熊森顧問門崎允昭氏がコメント
- 2020-06-03 (水)
- くまもりNEWS
以下、北海道新聞より
山菜採りの71歳男性、所持品残し不明 クマに襲われたか 古平
【古平】5月15日午後4時45分ごろ、後志管内古平町浜町の無職男性(71)が山菜採りに出かけたまま帰宅しないと、妻から余市署に通報があった。
同署などによると、男性は15日昼前に「タケノコを採りに行く」と妻に書き置きを残し、1人で乗用車で出かけたとみられる。通報を受け、同署や消防、猟友会などが16日、約50人態勢で自宅近くの山中を捜索。酒井さんの携帯電話や長靴、リュックサックが見つかったが、本人は見つからず、午後5時に捜索を終了した。
同署などは、現場の状況から、ヒグマに襲われた可能性もあるとみている。
・古平町の担当者は、北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所の間野勉専門研究主幹の「地域の人が気軽に裏庭のように行く集落の目と鼻の先に危険が潜んでいる。同じクマが2年続けて襲ったこともあり、人間をおそれないクマも現れている。今後も人を襲うおそれがあり、問題のクマを早く駆除する必要がある」というアドバイスをもとに、現場への立ち入りを禁止するとともに、ヒグマを捕殺するための罠を山中に11月まで3基設置しており、かかったら殺処分するそうです。
北海道のヒグマの生態とクマの人身事故のメカニズムについて、50年間研究されてきた、北海道野生動物研究所所長の門崎允昭先生は、今回の事件について以下のようにコメントされています。
羆が人を襲った場合の羆の行動特性
1、羆が人を襲った現場には、必ず最低でも半径数㍍の範囲に人と羆が抗争した痕が残ります。
2、人が羆に襲われて、人が羆から逃れて走り逃げた場合にも、必ず、走り逃げた、はっきりとした痕が残ります。
3、羆が人を襲い、人を倒し、羆が己が安心し得る場所に口で衣服や人体を咥えて、移動させる
場合がありますが、その場合は、最遠で90mでした。ですから半径90mの範囲を探すと、人体を見つけ得る事ができます。鹿の死体を300m移動させていた事例が有りますから、半径300mの範囲を、探すのが、最善です。遺体を羆が食べ尽くしても、衣服は残ります。頭部を必ず食べ残します。
4、半径300mの範囲を精査しても被害者の死体が見つからない場合には、被害者が(羆が原因とした場合)発見し得ない場合には、遺留品が有った場所ないしその付近で羆に襲われたとは断じ得ません。
5、檻罠を3個も仕掛けて羆を獲り殺そうという発想を持つこと事態、研究者にあるまじき事です。
熊森から
北海道のヒグマは自分の生息地かそうでないかをきちんと認識しており、人の住む町に出てきた場合、人間を襲うことは皆無です。
しかし、自分の生息地である森に人が入ってきた場合、何か不都合があったのか、年平均約1件の人身事故を発生させています。(たった1件!と意外に思われる方が多いと思いますが、事実です)ヒグマ猟のハンターに対する人身事故は、年平均0.5件です。
怖がりのツキノワグマと違い、ヒグマはまず人身事故を起こさない動物です。にもかかわらず、恐ろしい動物として、北海道で手あたり次第人間に殺されているのが現実です。2019年度捕殺されたヒグマは、711頭にものぼりました。
ヒグマの人身事故に関する門崎先生の知見は、さすが徹底した現場調査を続けられてきただけあって、すごいと思います。
古平町の担当者によると、半径100mをしっかり調べをてみたが、人体が引きずられた跡や衣服などなかったということです。ただし、長靴にクマが噛んだような跡があり血が付いていたり、現場近くにクマの糞と思われるものがあったそうです。この事件はミステリーです。
不明男性の捜索は1週間で終わってしまいました。
この場所は、ヒグマの国です。当然、ヒグマによる人身事故は考えられますが、1週間捜索して何も発見できなかったということから、別のことも考えられます。少なくとも、この場所で事故が起きたわけではないようです。
今回、熊森が問題にしたいのは、古平町がこの場所に誘引物を入れた捕獲罠を長期間設置していることです。またしても無実のヒグマを捕獲して殺人の罪を着せ、殺そうというのでしょうか。許されないことだと熊森は思います。
みなさん、捕獲檻を撤去していただけるよう、古平町にお願いしませんか。
古平町産業課農林係 住所:〒046-0121 北海道古平郡古平町大字浜町40−4
TEL:0135-42-2181 メール:こちらをクリック→古平町お問い合わせフォーム
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ