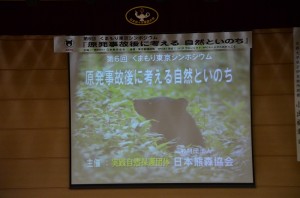くまもりNews
「ツキノワグマ 福島県内に最大3384頭生息か」という記事の真相
福島県は、「クマの捕獲許可権限を県から地元市町村に降ろして、クマをもっと獲りやすくするように条例改正する案」に対する県民意見公募の最中に、記者会見し、福島県に生息するクマは、これまで考えられていた数の2倍以上いるかもしれないと発表されました。まるで、クマはたくさんいるから、市町村判断で、もっと簡単に獲れるようにすればいいではないかと、意見誘導しているようにもみえました。県庁担当者に、電話をしてみました。
熊森 ・・・「カメラトラップ調査」で、何種類のツキノワグマの斑紋が、識別できましたか?
福島県・・・11種類です。
熊森・・・では、福島県に、最低11頭のクマがいることは、間違いありませんね。でもなぜ、11頭が、3384頭になったのですか?まさか、森林面積をかけたりされていませんよね。
福島県・・・最大3384頭というのは、あくまで推定で、3384頭いると言ったわけではありません。いろんなことを加味して、出しました。
熊森・・・11という数字が、どのようにかけたり足したりされて、3384になっていったのか、その全過程を業者から入手して、見せていただけませんか。非常に興味があるので、検証してみたいのです。加味したこと全てを教えてほしいし、どのように加味したのかも知りたいです。
<熊森から>
「これは、科学的に調査した結果です」と数字を出されたら、ふつうの国民は信じてしまいますが、その数字が出される過程を、県民の皆さんに検証していただきたいです。科学は法則です。誰が追試しても、同じ結果にならねばなりません。私たちは、福島県にクマが何頭いるのか知りません。豊かにいればいいだけで、何頭いてもいいのであり、正確な数など分かるはずはないし、知りたいとも思わないし、知る必要があるとも思いません。第一、生まれたり死んだり、絶えず複雑な要因が絡まって変化する自然界を、しかも、見透せない森の中で大きく動き回っている動物を、数字で表す事などできません。生息地が十分に保障されて、人間と棲み分け共存できていれば、それでいいのです。
しかし、野生動物の数を人間がマネジメントすべきと主張している研究者や業者たちは、そうではありません。何頭いるのか、クマたちの迷惑も顧みず、耐えがたい負担をクマたちにかけてまで、数字を出そうとします。次は、適正生息数を決めます。そんなもの、人間が決められるわけないのに、推測します。そして、自分たちが決めた数より増えたと推測されると、殺します。クマたちにはこの上もなく迷惑で傲慢な人間たちです。アメリカ大陸が発見された時、大地が動いたと思ったら、バイソンの群れで、空が真っ暗になったと思ったら、量バトの群れだったという記録を読んだことがあります。ワイルドライフマネジメント派に、バイソンもリョコウバトも、適正生息数はいくらなのか聞きたいです。
11頭いたという数は信じます。しかし、その後、この数字に人間がくわえた操作は、使った数式も含めて、全て、仮定であり推測です。仮定や推測を、何回も何回も重ね続けて出した数字になど、意味はあるのでしょうか。自然界や命は、物ではないので、工業製品のように数式化などできないのです。人間のためにもクマたちのためにも、こういう自然界の実態に気づく人が増えてほしいものです。
< 以下、新聞記事です>
福島県は13日、今年度から導入したツキノワグマの「カメラトラップ調査」で、県内の推定生息数は最大3384頭に上ったことを明らかにした。ツ キノワグマの斑紋を撮影して識別する手法で、調査方法が異なるため単純比較はできないが、これまでの最大1600頭の2倍を超えた。
調査結果は同日、福島市内で開いた県と学識経験者らによる検討会で報告された。県は結果や検討会の議論をまとめて、2013年度からの県ツキノワグマ保護管理計画に反映させる。
調査は8~10月、クマの生息数が多いとされる西会津町で行った。山林の20か所にビデオカメラとハチミツを仕掛け、クマがハチミツを捕る際にあ らわになる胸の「月の輪形」の斑紋を撮影。斑紋は個体によって異なるため識別でき、映り込んだ頭数をもとに生息数を割り出した。
その結果、県内全体の生息数を514~3384頭と推定。従来は農作物を荒らされた場所にわなを仕掛け、捕獲した頭数をもとに推定していたが、この方法で1988年から2003年までに行った調査では、860~1600頭だった。
県は、捕獲頭数は年ごとにばらつきがあるため、実際に山で暮らすクマを数えた方が実態に即しているとして、カメラトラップ調査に切り替えた。た だ、予算の都合などで、今年度の調査は西会津町に限定され、短期間にとどまった。このため検討会では、委員から「結果として生息数を多く見積もっているの では」「調査地域を広げるべきだ」などの指摘があった。
県自然保護課は「調査地域を広げたり、複数年にわたって調べて経年変化をみたりして、精度を高めたい」としている。
県によると、今年度の県内のクマの目撃件数は10月末現在398件で、前年度同期(120件)の3倍以上だ。クマに襲われてけがをした人も5人おり、うち1人が死亡している。
県は住民に危害が及ぶ恐れがある場合、地元で迅速に対応できるように、希望する自治体に対し、クマ捕獲の許可権限を県から移譲する条例改正を目指している。来年2月の定例県議会に提案し、可決されれば13年度から施行の予定だ。
県が実施したアンケートでは、全59市町村のうち、会津地方を中心に27市町村が権限移譲を希望しているという。
雪の収穫祭 2012/12/9(自然農塾)
- 2012-12-17 (月)
- _自然農
12月2日予定だった収穫祭を、本部の都合により急遽9日に変更させていただきました。
ご迷惑をお掛けしたにもかかわらず、自然農メンバーの方々は12月2日の今本先生講演会に
18名もご参加いただき、感謝の言葉もございません。ありがとうございました。
9日の収穫祭は、雪景色の中ので行われました。
いつもと違う雪の古民家の前でまず記念撮影です。寒さのせい(?)でピントが、、、
今日は、最後の作業となるネット外し組とお料理組に分かれます。
お料理組はお汁と収穫した新米をかまどで炊きます
ネット組は耐寒訓練のように厳しい寒さの中での作業です。手のかじかむのに耐えながら延々と続くネットをポールから針金をとって外していきます。
塾生のMさんのお店で作っておられるブドウ酵母を使ったパンをたくさんプレゼントしていただきました。
熊森にぴったりの可愛いクマさんのパンも、とってもおいしかったです。
古民家の中では、手際よくお米の分配作業をすすめます。
皆で楽しいお食事です。黒米を入れたご飯はもっちりとして甘みもあり大変贅沢な味わいになります。
かまどで炊いたコシヒカリは、おこげが香ばしくて懐かしい味がしました。
食後は今年1年の自然農での「振り返り」をしました。今回の塾生の方々からは「勉強になった、腰が痛かった、こんな風にお米が出来て感動している」などの感想を頂きました。世話人としましては、無我夢中だった去年にくらべて今年は分かってないことがたくさんあることに気づいた一年でした。特にお水の管理がいかに大切で難しいかが、良く分かりました。来年は一年間、田んぼを休ませて整え、草を田んぼに戻し、ビオトープと池の整備をしたいと思います。
地元の岸本さんをはじめ、今回ご参加いただいた全ての自然農関係者の方々に心からお礼を申します。ありがとうございました。(H)
2012.12.16 衆議院選挙 立候補者への 「奥山保全・再生」に関する公開アンケート結果
日本熊森協会では、選挙などの機会に、意識調査アンケートを行っています。今回、熊森本部のある兵庫県を中心に、アンケートを行った結果を、ホームページでお知らせしています。以下のリンクからもご覧いただけますので、ぜひご参照ください。
(PDFファイル 12/15更新)
くまもり自然農からのお知らせ 12月9日に収穫祭
9日の収 穫祭では、新米を炊いてみんなで味わいたいと思います。
例年、収穫祭参加者は一品持ち寄ることになっていましたが、今年は本部と有志でそれらをご用意させ ていただきますので、不要です。ご参加くださる方は必ず各自、お茶碗、汁椀、お箸、取り皿、湯呑みをお忘れなくご持参ください。古民家に引いていた山水 が、現在パイプ詰まりの為、使用できなくなっていますので、そのつもりでお越しください。また、来年用の種もみや黒米などをお持ち帰りいただきますので、 適当なビニールもご持参ください。国産無農薬のそば粉のプレゼントもあります。
材料費など500円は、当日頂きます。ご参加いただける方は、12月6日(木)までに、本部までお申しこみください。
当日は、田んぼの周りの鳥獣よけネットをはずしますので、お手伝いいただける方は、どうぞよろしくお願いたします。
12月2日 盛況だった今本博健先生によるくまもり冬の講演会
2012年12月2日 日曜日、西宮市民会館にて、熊森協会顧問の今本博健先生による90分講演会、「ダムが国を滅ぼす」が行なわれました。
急に冷え込んだ師走の時期、朝からの講演会であるにもかかわらず、満席御礼にて、講演会を開催することができました。皆様、ありがとうございました。
ダムで川の流れを止めることによって、川は死に、取り返しのつかないさまざまな弊害が発生します。今本先生は、淀川流域委員会の委員長となられて、研究者以外のいろんな方々と意見交換をされるうち、ダム以外の治水を考えるべきだという思いに駆られるようになられます。
そうして到達されたのが、ダムを撤去し、大雨時、人のいない所では、わざと川を氾濫させる、人のいる所では堤防を鋼矢板で強固にし、堤防が切れないようにするという、<強い堤防による治水法>です。
参加者のみなさんが熱心に耳を傾けておられたのが印象的でした。
<講演の内容> ダムの歴史から始まり、ダムや堤防についてはもちろんのこと、ダム問題にしても、何故正しいことが行なわれないのか、正しい方向にいかないのか、といったことも語られ、ダムの仕組みなど難かしい部分もあったかもしれませんが、わかりやすく話をされ、多くの方に笑顔で帰っていただけました。
●感想
旧建設省のある河川部長が、かつて職員に、「詐欺ともいえる説明は、国民を困惑させる。①隠さない、②ごまかさない、③逃げない、④嘘をつかない。この当たり前 のことをきちんと守っていこう」と呼びかけられたという話は、胸を打ちました。内部からこのような声が出たというのは、このようなことが日常茶飯事に行わ れているからであって、国民として市民として、全ての分野で、省庁内部からこのような声があがることをのぞみます。
今回の講演を、入門編として、この後は自分達でも、もっと勉強していかねばならないと思いました。
午後、熊森協会の事務所で行われた今本先生を囲む懇談会には、20名の方が参加してくださいました。とても充実したものでした。ダム建設によって政治家に動くお金は、3%が相場だということです。
11月29日(土) 森再生活動 宍粟市波賀町 沢沿いのスギ人工林 間伐
- 2012-12-05 (水)
- _奥山保全再生
山の神様に今年一年間、無事故で作業できた
ことの感謝を伝え、間伐等の整備により、豊か
な森が再生することを祈念し、作業に入りました。
自然に対する畏敬の念、感謝の気持ち忘れず
に最後まで気を引きしめていきたいと思います。
前日に雨が降ったため、沢の水量が増えてい
ました。チェンソー等の重い荷物を持って沢を
渡るのは危険なので、間伐した杉の丸太を使って
簡単な足場を作りました。
細い丸太でも多くの水分を含んでいるので、見た目
よりもかなり重たいです。
慎重に丸太を運びました。
切った木が他の立木にかかり、途中で止まって
いる「かかり木」の状態。この「かかり木」の処理
はとても危険で林業の現場でも事故が多発して
います。正しい知識と技術で処理をしないと死亡
事故につながります。
この日は林業経験者が指導にあたっていたので、
無事に処理することができました。
①伐倒方向を決め、受け口の切り込み。
この「受け口」をうまく作れないと倒したい方向
に倒れません。
水平切りと斜め切りを合わせるのが難しいです。
②伐倒方向の確認。
少しのずれが、危険な「かかり木」を発生
させてしまいます。伐倒方と合うまで向きを
修正します。
③最後、追い口を切り進めます。
反対側が見えないので、切りすぎないように
確認しながら少しずつ刃を進めます。
無事に伐倒完了!
一呼吸置いてから枝払い、玉切り作業に
入ります。
みんな太めの木も手際よく伐倒することが
できるようになってきました。
作業終了後、参加者全員で写真撮影。
お疲れ様でした!
11月11日(日)雨 < くまもり自然農塾 > 土間での脱穀作業
- 2012-12-05 (水)
- _自然農
くまもり自然農塾、最後は脱穀です。
当初、11月4日の予定でしたが、前日夕方の雨で一週間延期を決定。
ところが11月11日も雨の予報でした。
慌てて4日に、有志5名で干してあるお米の取り入れ作業に行きました。
雨に濡れてしまうと、脱穀が出来なくなってしまうからです。取り入れたお米は古民家の軒下に干します。こんなとき、広い軒下は便利です。
残った時間で、畔や田んぼの周囲の草を刈り、刻まずに田んぼに入れました。
自然農では草草のなきがらが、土になるので、草を田んぼに返すのは大切な作業です。
草刈り前 草刈り後
脱穀
11日は本降りの雨。古民家の土間で脱穀しました。
広い土間は、こんなとき便利です。塾生の人達全員に交代で、足踏み式脱穀機を使い脱穀してもらいました。
一人で足で脱穀機を廻し、手で稲束を梳くのは結構難しいです。少しでもタイミングや力が足りないと脱穀機が反対に回り始めるのです。もう一人別に踏んでもらいながらだと、かなりうまく回ります。
 脱穀機にかけたお米は一粒残らず拾い、目の荒いざるで余分な藁やごみを取り除きます。次にトウミという選別器にかけます。風のちからで実のつまったお米と 少し軽めのお米とを別々に分けてくれます。軽いごみは吹き飛ばされます。良く考えられた道具だと思い、毎年感心しながら使用しています。
脱穀機にかけたお米は一粒残らず拾い、目の荒いざるで余分な藁やごみを取り除きます。次にトウミという選別器にかけます。風のちからで実のつまったお米と 少し軽めのお米とを別々に分けてくれます。軽いごみは吹き飛ばされます。良く考えられた道具だと思い、毎年感心しながら使用しています。
残った稲わらは、土の養分となるように、大雨の中、田んぼに全部返しました。
黒米、赤米、コシヒカリ、今年は去年よりは少し多めにとれました。
籾すりと精米をすませれば、12月9日の収穫祭には、おいしい新米を食べることが出来ます。<H>
11月4日 第6回くまもり東京シンポジウム 記念講演 小出裕章先生「日本の自然と原子力」
- 2012-11-25 (日)
- くまもりNEWS | 東京都 | 東北大震災・福島原発
福島原発事故以来、日本の森や動物を守るために、放射能汚染の話を避けて通れなくなった熊森です。
第6回くまもり東京シンポジウムのテーマは、[原発事故後に考える自然といのち]
会場は、渋谷にある日本赤十字看護大学
この日のために、何か月も前から準備を続けてきた関東支部長と関東支部スタッフのみなさんが、シンポジウムの成功をめざして、打ち合わせ
会場の舞台正面
参加者が集まり始めました。打ち合わせ通り、スムーズに受付が進みます。
会場が埋まっていきます。
森山会長あいさつ
「報道機関が真実を国民に伝えてさえくれれば、国民はもっと正しく判断して、もっといい行動ができる」
小出先生の登場で、大きな拍手がわき上がりました。
この日の先生の演題は、「日本の自然と原子力」です。
本当に誠実で一般国民にもわかり易く、最先端のお話をしてくださいました。一人でも多くの国民に、この日の話を何らかの方法で伝えねばならないと思っています。
後半は、熊森若手リーダーと小出先生の対談です。日本熊森協会の活動と小出先生の講演がつながります。
質問が相次いで、残念ながら時間切れに。どれも真剣ですばらしい質問でした。もっともっと国民は原子力について知りたがっていることがわかりました。
おかげさまで、いい会になりました。最後に小出先生を囲んで、スタッフ全員で記念写真。
みなさん本当にありがとうございました。
●参加者からいただいた感想
小出さんの講演を初めて聞いて、衝撃を受けました。今の日本人は、自己責任が欠如していると思います。自分が直接の加害者でなくても、今世の中で起きていることに、連帯責任を持たねばならないと思いました。小出さんが、食品の放射能汚染の話をした後、「私は食べます。福島原発事故を防げなかった責任があります」と、言われた。ごく普通の話し方で言われたため、この発言のすごさに、会場の人たちは気づかなかったのではないか。
常に被害者意識で物事を見る習慣がついてしまっている国民に言いたい。自分の子どもをかわいそうに思うなら、福島の子どもはもっとかわいそうであることがわからねばならないだろう。
放射線管理区域以上に放射能に汚染された地域の地図を見せられた時、卒倒しそうになりました。クマや森の保全を訴えてきた会長が、熊森関東が東京でこのようなシンポジウムを開くことを認めた真意について、会員として考えてみたいと思います。
くまもりの横断幕を付けて走り回っています
八幡平クマ牧場からツキノワグマを阿仁熊牧場に移送した時の写真が送られてきました。「せめてもの感謝に、八幡平クマ牧場のトラックの横に熊森協会の横断幕を発注して付けて走りたい」という牧場主の提案を、「多くの個人や団体も応援されているし、元々名を出さないように支援しようと思ってやってきたことなので、そのようなことは望んでいません」と言ってお断りした熊森ですが、牧場主が実行されたことがわかりました。現在もこの横断幕を付けて走り回っているということです。せっかくですので、みなさんにご披露しておこうと思い、写真をアップします。
一番上に、クマの棲む豊かな森を次世代へ・・・
赤字は、八幡平クマ牧場を支援している団体とあります。
もちろん当協会以外にも多くの個人や団体が、それなりに精いっぱい八幡平のクマを応援して下さっているのですから、なんらかの機会にみんなで讃え合えたらと思います。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ