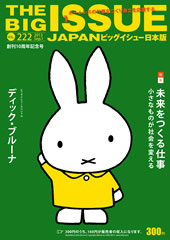ホーム > 支部・地区・地域
カテゴリー「支部・地区・地域」の記事一覧
10月27日 京都府支部 桑谷山佐保の森の実り調査→良好
京都市花脊(はなせ)にある桑谷山佐保の森は、50ヘクタール。2007年に奥山保全トラストが購入しました。10月27日、京都府支部の皆さん7名が、秋の実り調査を行ってくださいました。以下その報告です。
今回は、久多峠から入りました。樹上のドングリはもうありませんでしたが、林床にはミズナラのドングリやシバクリがたくさん落ちていました。今年の実りは良好でした。今年は、動物たちも喜んでいることだろうと思うと嬉しくなりました。アスナロの巨木たちも健在でした。(上写真右)
クリはイガだけになっており、傍らには、栗の中身がきれいに食べられ、皮だけになった実が落ちていました。クマ棚や熊の爪痕など、クマの痕跡を探しましたが、登山道を歩いた限りでは見つかりませんでした。
ミズナラの枯死木が多くありましたが、いずれも何年か前のものばかりで、今年、新しく枯れた木は見当たりませんでした。これまでミズナラの枯死木を多くみてきて、森がなくなってしまうのではないかと胸が痛んでいましたが、今回、2~3年生のミズナラやクリの実生苗が、枯死した木の根元でたくましく成長しているのがたくさん見つかり、希望が芽生えているようで嬉しくなりました。特に、栗の苗木は無数に生えており、なぜここの苗木はシカに食べられないのか、不思議に感じました。
イヌブナの実生稚樹
ミズナラの実生稚樹
シバグリの実生稚樹
10月13日 関東支部例会
東京都中央区で開かれた関東支部例会に、会長と副会長が出席しました。33名の東京都会員が集まってくださいました。
まず、会長が、どのようにして兵庫県で組織を作っていったか、副会長が、石川県支部と滋賀県支部を例に、どのようにして他の支部が本部と連携を取りながら活動を展開していっているかなど話しました。みなさん、大変興味深く聞いてくださいました。
休憩をはさんで、後半は、これからの支部活動について、出席者からの自由発言会となりました。
とても前向きで、いい会になったと思います。
次回の会報で、この時に出た意見などを会員のみなさんにお伝えできたらと思っています。
尚、次回支部例会は、11月3日(日)13時~16時 です。場所は、生涯学習センターバルーン202号室
(JR新橋駅烏森口下車徒歩1分)。奮ってご参加ください。
巨木トラスト活動が『ビッグイシュー日本版』に掲載されました
ホームレスの方が街頭で販売している雑誌『ビッグイシュー日本版』の創刊10周年記念号(第222号 9月1日発行)に、巨木トラストの記事が2ページにわたり掲載されています。
すべての人に「出番」と「居場所」のある社会をという理念のもとホームレスの方を販売員として街行く人々に販売されてきた雑誌であるビッグイシューの10年の歩みを記念すべき号に記事を載せていただいたことはとても光栄です。
10周年記念号の表紙は、ブルーナのうさぎが目印です。現在、街頭で販売されていますので(定価300円、160円が販売員の収入になります)、ぜひトラストの記事をご覧ください。
水源の森の巨木群を、伐採から守るために、基金にご協力を!
以前、このくまもりNEWSでもお知らせさせていただきましたが、3年前から、滋賀県支部の皆さんが滋賀県旧朽木村のトチノキ巨木群を伐採から守るために大奮闘してきました。そして、この度、トチノキの所有権をめぐって伐採業者と争っていた裁判の中で、伐採対象となっていた巨木48本を、熊森が960万円で 買取るという合意を成立させました。既に売られてしまった巨木を守るための決断です。
琵琶湖源流域にある巨木の森をたくさんの人に協力していただいて守っていくために「びわこ水源の森・巨木トラスト基金」を立ち上げました。地元の会である「巨木と水源の郷を守る会」にも協力していただき、巨木トラストを実現させたいと思っています。
業者との約束期限は、今年12月。滋賀県支部長らが、電話帳をたよりに伐採業者を探し出し、時には今にも伐られそうな巨木の前に立ちはだかって、伐採を阻止してきた巨木たちです。 ぜひ応援いただき、周りの方々にもお広めいただけると嬉しいです。
★特設ホームページにて、詳細やチラシのダウンロード、また基金の状況もご覧になれます。
ぜひご支援の程、お願い申し上げます。
山形の月山ブナ原生林とクロちゃん見学ツアーに参加して
参加者レポート/2013.6.15~6.16
【山形の月山ブナ原生林とクロちゃん見学ツアーに参加して】
周り一面サクランボ畑が広がる山形空港で、旅行社の斉藤さんとクマのクロちゃんのお父さん(飼い主)の佐藤さんのお出迎えを受けた後、山形駅で他のメンバーと合流。勝手に少しレトロな山形駅を想像していましたが、綺麗な新しい駅ですぐ横には高層ビルがにょきりと立っていて、遠く東北まで来たという感じがしなくてちょっとがっかり。
一行は、まずは月山山麓の県立自然博物園を目指しました。夏スキーで有名な月山には、たくさんの雪が残っていて雪解け水の激しい流れに驚いていると、山から下りてくるたくさんの人とすれ違いました。聞けば山菜取りの人が行方不明になって警察も出て捜索中とのこと、地元の人も迷うほど山が深いということでしょうか。
その後、歴史を感じるお蕎麦屋さんで美味しいお昼を楽しむうちに参加者も自己紹介などもしながら和やかな雰囲気に。
佐藤さんの自宅に近いブナ林では、ドームのようになったブナの木々を下から見上げると厳かなような何とも言えない気持ちになり、目を地面に移すとそこにはブナの赤ちゃんが一面に広がっていました。佐藤さんいわく「こんなに多くあるけど来年まで育つのは一本もないだろう」とのことで、木々が一人前に育つことの大変さに想いをはせました。
今夜の宿の田麦荘に荷物を置いて、いよいよクロちゃんに会いに、佐藤さんのお宅を訪問。
クロちゃんは、佐藤さんが飼育しているツキノワグマで、佐藤さんがかつて猟師だった頃、母熊を殺されて孤児になった小熊を見つけ、保護することにしたのだそうです。
佐藤さんはクロちゃんを保護した時、「熊はすぐに大きくなるので個人で飼うのは無理だと言われ、引き取り先を探していたのが、ある時クロちゃんが迷子になり、探す私の声を聞いて嬉しそうに駆けてくるのを見たとき自分で飼うことを決めた」とおっしゃっていました。
「それから20年以上いろいろ苦労したけれど、先日私が一週間入院した時にクロちゃんはその間餌も食べず排泄もしなかったと息子から聞いて、私はクロちゃんより先には死ねないと思った」と言われたのが印象的でした。
今では日本全国からクロちゃんに会いに人が訪れます。「来られた人が泊まれるように新しい宿泊所を建てたので、熊森協会からももっと多くの人に来てもらいたい」とのことでした。
クロちゃんのオリの中はとてもきれいに掃除されていて、大事にされているのがわかりました。
野生のクマの寿命は12,3年ということで、それからすると20歳を越えるクロちゃんはかなり高齢なのですが、体のツヤも良くとてもそんな年齢とは思えませんでした。
一時間ほどお話を伺った後、宿で頂いた夕食は山菜と日本海のお魚、それとクロちゃんファンクラブの会長でもある宿の女将さんから差し入れていただいた地酒も美味しく、皆、とても満足でした。
佐藤さんは、食事の間もそのあとの二次会でも会員からの質問に丁寧に答えてくださり、お話からはクロちゃんへの思いが伝わってきました。
翌日も佐藤さんがガイドしてくださり、午前中は羽黒山観光を楽しんだあと、山形駅で解散。それぞれ帰途につきました。
佐藤さん、本当にお世話になりました。またクロちゃんに会いに、田麦俣に行きたいです。(池田)
本部・石川県支部 白山トラスト地及び周辺の調査に入る 6月29日
6月29日、本部8人と石川県支部8人は、研究者と共に白山トラスト地22ヘクタール及びその周辺の山の調査に入りました。
当日は天気も良く、前回の岐阜県の奥飛騨トラスト地に続いて下層植生が生い茂り、多様性豊かな森を見ることができました。
トラスト地は、極相林に近い森です。100年たってもこの景観が保たれます。それぞれの遺伝的な木の高さをもった木が生えており、高木層、亜高木層、低木層、草本層という形できれいに光配分ができているので、一面が緑色でした。
この山にはまだシカが入っていないこともあり、兵庫県ではもうほとんど見ることができないシカの大好物ハイイヌガヤの群生があちこちに残っていました。 
奥飛騨ではほとんど確認できなかった虫たちの食痕が、ここ白山では驚くほど多くの葉に見られました。
しかし、この時期は蝶々がたくさん飛んでいる時期であるにもかかわらず、ほとんど飛んでいませんでした。やはり、昆虫が豊かに生息しておれる状況ではなくなっているのかもしれません。
クマが大好きな桑の実がたくさん実っていました。夏の木の実はクワぐらいしかなく、クマにとっては貴重です。
今回、石川県支部スタッフの皆さんが、大雨の中で事前に調査をしてくださっており、みんなで今年のクマハギを見ることができました。白い部分がクマの歯跡です。
ここにはササも多く生えていましたが、奥飛騨トラスト地でも一斉開花が始まってきているので、10年後にこのササが残っているかどうかは、研究者の先生にも分からないということです。
白山連峰にはまだクマが住めそうな場所がたくさん残っていると感じ、安心しましたが、地球温暖化や、酸性雨、農薬関連の化学物質などによって、地球環境が激変していっている今、10年後にこの森がどうなっているのかという気がかりも残りました。
また、白山では、場所によっては、2005年あたりから、ミズナラなどの広葉樹の巨木の枯れがすさまじく、森が消えてしまうんだろうかと心配していましたが、今回調べてみると、更新稚樹があちこちで育ってきていました。自然界はすごいです。
6月27日 北大阪地区、小学校4年生に環境教育
北大阪地区では、小学校4年生2クラス合計55名に、今年も環境教育を実施させていただくことができました。
会員のハーモニカ演奏(森のくまさん)にのって生徒たちが入室、手拍子も起こり良い雰囲気で環境学習「日本の森と動物・紙芝居(どんぐりのもりをまもって)」が進められました。子どもたちとの一体感が45分間保たれ、すばらしい公演となりました。ナレーターの質問に対する子どもたちの反応は良く、みなさん活発に手を上げて答えてくれました。子供たちがツキノワグマのツッキンに親しみを感じたようで、触らせてほしいと希望があり、生徒の退出時に生徒全員とツッキンとのタッチが行われ、参加者の皆が心温まる思いで環境教育を終えることが出来ました。
今回の環境教育には12名の会員さんが参加してくださいました。練習と工夫を出し合って、よい環境教育ができたと思います。
お世話くださったみなさん、参加してくださったみなさん、ありがとうございました。(くまもり北大阪地区地区長)
6月23日 岡山県支部総会
岡山県支部総会は、JR岡山駅のすぐ近くにある、会員が管理されている建物で持たれました。岡山県支部の例会は毎月ここで夜7時から持たれているのだそうです。便利だし広いし、本当に恵まれていると思いました。希望者には、おいしいお弁当が安く買えるようにもなっているのだそうです。仕事帰りに寄ってくださるといいですね。岡山県支部は、これから組織化を進めていかねばならない、まだこれからの支部だということです。
森山会長の記念講演は、「初めての自然保護」という題で、町内に残された自然を守ろうと住民みんなで立ち上がり、隣町のすばらしい町内会長さんの指導で、初めて無茶な開発を止めることに成功した約30年前の体験談でした。一般国民は無力なようだが、正論で数が多いということは、実はすごい力を発揮します。声をあげる。集まる。力を合わせる。これがいかに大きな力になっていくか、集まられた方々に会長は熱く語り続けました。みなさん、笑い、集中し、食い入るように聞いておられました。
第2部は、岡山県支部の里山整備を通した実践活動が報告されました。自然から離れて暮らしている子供たちを、どんどん里山整備活動に呼び込んで、すばらしい環境教育をされていました。
会員の中には、人工林でびっしり埋まった地域の山を3.7ヘクタールも個人で買い、9割間伐を施して自然林に戻しつつある方がいました。こんな会員がおられたのか。感激でした。
また若い男性や女性のボランティアグループが、土日に奥地に通い、地元の方々と仲良くなって、地元の方々の山をきらめき(皮むき)間伐したり、チェンソー間伐したりさせてもらっている事例が、2例も発表されました。何とか間伐を広め、下草の生える山に戻そうと、汗を流している若者たちに悲壮感はなく、大上段に構えず、とにかくみんなで楽しもうという感じで仲間を集めることに成功しているようでした。若い人たちに拍手。
先週の福岡県支部で出会った人たちに続き、岡山県支部で出会った人たちもまた、未来への責任感で集まり、語り、動こうとしているすばらしい大人たちでした。お互いが出会うことで、こんなに真剣に、未来のこと、地球のこと、生き物たちのことを考えて生きておられる方たちがいたとわかっただけでも、元気をいただき、勇気が湧いてきました。孤立しておられるくまもり会員のみなさんが、まだまだ全国にたくさんおられます。どうか、勇気を出して、集会に出てきていただきたいと願っています。また、各地域のリーダーのみなさんは、集まってくださった方々が大きな元気を得て帰れるような楽しくてためになる集会企画を、がんばって作り上げてください。
6月16日 北九州市での会長講演会
福岡県支部は、当協会の支部の中でも大きな支部で、皮むき間伐などの活動も盛んです。福岡県支部には、事務所もあるし、アルバイトスタッフも1名います。
戸畑駅前の会場には、大勢の方が来てくださいました。半分は、初めて参加された方々でした。福岡県支部はこれまで、何度も会長講演を企画してくださってきましたが、3・11以降は途切れていました。
収束のめどが立たない福島原発、放射線量が高くて入れなくなっている関東以北の山々、自然保護運動に取り組んできた人たちには、これからもうどうしていけばいいのかという閉そく感もあります。
そんな中、元気の出る話をということで、持たれた講演会でした。会長は、何とかみんなを励まそうと、元気の出る話を一生懸命探して話しました。みなさん最後まで一生懸命聞いてくださいました。
後半は、顧問の平野虎丸さんとの対談です。
今、日本の山は、戦後、人がスギやヒノキを密に植えたまま放置したことによって、木が多過ぎて大変なことになっています。
なぜ大雨が降ると九州の山が崩れ出すようになったのか、なぜ<植えない森づくり>がいいのか、代々林業家の家に生まれ、ご自身も数十年にわたって山にかかわってこられた平野さんのお話は、最高の説得力を持っています。
人間が手を入れ続けないといい山にならないと思い込んでいた人たちが、目からうろこでしたと驚いておられました。
<大雨でも崩れにくい山=生物の多様性が保たれた山=保水力抜群の豊かな山>を取り戻すためには、国にお願いするだけではなく、市民が声を上げ動き出さねばならないということで、二人の話が一致しました。官のできないことは民の手で、民のできないことは官の手で。
講演会後の懇親会には、予想外に多くの方々がご出席してくださり、座席、飲み物、お菓子などが大幅に足りなくなるという嬉しい悲鳴でした。いろんな方が、お話くださいましたが、どなたのお話も、胸を打つもので、本当に元気をもらえました。ここには一生懸命生きておられる方たちが集まってくださっている。自分さえよければいいのではなく、未来に責任を持って生きたいと思っている人たちが集まってくださっていると感じました。なんと素晴らしい仲間たちなんだろう。良き友を得て、信頼できる仲間たちと共に人生を送れたなら、人生に100%成功したことになるという言葉を思い出しました。
確かに、元気が出ない今日の日本ではありますが、心ある人たちが集い、民主主義国家を形成する国民のひとりとして、この国、世界、この地球にどう向き合っていくのか語り、信念に基づいて行動するときなのだと思いました。他生物のために、次世代のために、地球環境保全のために。
準備してくださったみなさん、音楽やゲームで場を盛り上げてくださったみなさん、参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。
この後、会長講演は、6月岡山県、7月東京都、8月熊本県、10月広島県、千葉県、11月栃木県、来年1月愛知県、山梨県と予定されています。みなさんの地域でも、ぜひ、熊森会長講演会をご企画ください。今後は副会長も講演していきます。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ