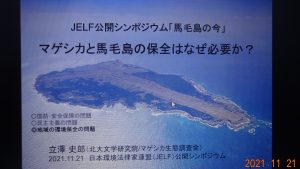くまもりNews
広島・山口・島根の2020年度ツキノワグマの捕獲総数523頭の7割にあたる364頭が「錯誤捕獲」
- 2021-11-27 (土)
- くまもりNEWS
前回に引き続き、くくり罠の錯誤問題です。
(以下、11月22日 中国新聞記事要約)

山口県中部の山中で撮影されたツキノワグマ(山口県提供)
県別ツキノワグマ捕獲総数は、島根352頭、広島131頭、山口40頭。
うち、殺処分合計は425頭と過去最多。
捕獲後は危険なため多くが殺処分となる。
環境省は3県のツキノワグマを西中国地域個体群としてレッドデータブックで「絶滅の恐れがある」としており、狩猟を禁止している。3県の計画では殺処分できる上限の目安を年間に計94頭としている。にもかかわらず、2020年度の捕獲数は過去最多で523頭、大きく上回った最大の要因は、錯誤捕獲の増加にある。
熊森から
熊森は早くから、野生動物たちの足を切断してしまうくくり罠の残虐性と無差別性に注目し、くくり罠の使用禁止を環境省に何度も訴えてきました。
熊森の会長が協議会委員を長年務め錯誤捕獲問題を訴え続けてきた兵庫県は特別で、シカ・イノシシ用くくり罠に錯誤捕獲されたクマは100%放獣されているもようです。
しかし、クマの恐怖や足切断などの重傷例も起きます。放獣されるからいいというものではありません。クマ以外にもおびただしい野生動物たちが錯誤捕獲され殺処分されたり放置されたりしています。生物倫理に著しく反しています。このような残虐罠を、しかも、山の中にまで仕掛ける権利は、肥沃な大地を野生動物たちから全部奪い取ってしまった人間にはないはずです。
環境省の旗振りで罠免許所持者は増える一方です。兵庫県の山奥に住む猟師に聞くと、狙った動物を獲るには、イノシシ道など各種野生動物の通る道が見えてこないとだめで、道が見えて来るのに2年かかったと言われていました。都市のにわかペーパー猟師に、狙った獲物だけ獲ることなど無理だということでした。
熊森は、野生動物のためにも、弱者を大切にする優しい人間社会を作るためにも、鳥獣被害対策の大転換が日本民族に求められていると思います。
宮城の猟師くくり罠を真円12センチに戻すならイノシシを駆除しにくくなると不満 熊森見解は?
- 2021-11-26 (金)
- くまもりNEWS
以下、11月23日河北新報より
里山を駆け回るイノシシの群れ。駆除するわなの形状見直しで異論も=宮城県亘理町
「このままでは繁殖適齢期のイノシシがくくりわなで捕獲できず、獣害を止められない」。
宮城県で有害鳥獣駆除に当たる猟友会員から河北新報社に憤りの声が寄せられた。きっかけは、くくりわなの形状変更(縮小)を呼び掛ける全国組織の大日本猟友会(東京)の提言。わなの形状が駆除にどう影響するのか。現場の事情を探った。
大日本猟友会:
9月1日発行の会報「日猟会報」で、わなを12センチの真円にするよう訴えた(イラスト参照)。 同会の担当者は「(規定より大きな形状のため)クマを誤って捕まえる錯誤捕獲が多発しているし、人間の子どもが掛かる可能性もある。会員は本来の形状のくくりわなか、箱わな、銃で捕獲してほしい」と促す。
環境省が2007年に規制緩和した現行のくくり罠 最大径が18~26センチの楕円(だえん)形のわな製品が出回っている。
■宮城県蔵王町遠刈田猟友会の前会長 佐藤秀一さん(79)
大日本猟友会の主張に真っ向から反論する。
理由はイノシシ特有の蹴爪(けづめ)の位置。ひづめとほぼ直角に横方向へ伸びており、繁殖可能な体重50キロ以上の成獣は足の横幅が12センチを超える。わなの枠内に収まらず逃げてしまうという。佐藤さんは「わなの形状が会報通りに変更されれば、どんどんイノシシが繁殖してしまう」と危惧する。
佐藤さんによると、わなで足全体をくくるイノシシと違い、クマは指1本でも引っ掛かるので最大径を縮めても意味がないという。
大日本猟友会が活用を求める箱わなは、警戒心が強いイノシシの成獣がなかなか入らないとされる。昔のように集団で獲物を追い込み、銃で仕留める巻き狩りをするマンパワーもない。佐藤さんはクマの錯誤捕獲の多さを認めつつ「12センチの真円になったらイノシシが全く捕れなくなる。猟をやめる人が続出するだろう」と強調する。
■環境省:
「見直しは必要」 環境省は「07年度は今ほど極端な楕円形の製品が出ると想定していなかった。錯誤捕獲も懸念されるし、何らかの見直しは必要」(野生生物課鳥獣保護管理室)との立場だ。深刻化する獣害を食い止めようと、環境省は13年度にイノシシの個体数を10年間で半減させる目標を掲げている。担当者は「捕獲数が減っては矛盾する。さまざまな意見を聞き、どうするか判断したい」と話す。(桜田賢一)
熊森から
宮城県の2020年度のクマの有害駆除数は279頭です。うち、64%にあたる178頭が、イノシシ罠に誤ってかかったクマで、罠に掛かったクマは危険だからと全て殺処分されました。こんなことを放置していたら、クマは滅びてしまいます。
クマだけではありません。キツネやタヌキなど、何の問題もない大量の野生動物たちが、山の中に仕掛けられたおびただしいくくり罠に誤って掛かって殺されているのです。
今の日本のやり方の根本的な問題は、自然界の中のある種の動物だけを捕獲することなどできないということがわかっていないことです。(=自然がわかっていない)ワイルドマネジメントによる個体数調整として、山の中にどんどん罠を仕掛けてシカやイノシシを捕殺する政策は方向転換が必要です。
どうしたら大量の錯誤捕獲問題が解決できるのか。基本的には、祖先がしていたように、野生動物を殺すのではなく、被害が減るように田畑を守る対策に方向転換すべきでしょう。

山の中にいるイノシシまで獲る必要があるのですか
彼等は土を掘って根の成長を助け、豊かな森を造ってくれています。
<野生動物を殺さないで被害対策を進めている方もいます>
井上雅央(いのうえ まさてる)氏 1949年、奈良県生まれ。愛媛大学大学院農学 研究科修士課程修了。京都大学博士(農学)。元近畿中国四国農業研究センター 鳥獣害研究チーム長、退職後、同センター専門員。
井上氏は、宮崎県、熊本県、広島県、静岡県等でアドバイザー野生動物を殺さな くても防除対策をとれば被害を減らすことは可能で、女性にもできる防除対策を 各地で広めておられます。
イノシシ、サル、シカなどによる農作物被害。獣害対策がうまく機能しないの は、なぜか。
井上氏は各地を歩いた経験からその原因を鳥獣害は行政の仕事と決 めてかかる頭の固さなど「男」の論理と喝破。女性が主導で女性の論理、パワー で動き出すことでそれを突破し、集落自衛が起動し始めた成功実践例を各地に 作っておられます。井上氏の実践は、目からうろこです。『これならできる獣害対策』、『山の畑をサルから守る』『山と田畑をシカから守る』『60歳からの防除作業便利帳』など、著書多数。イノシシ編もクマ編もあります。
日本は、もういい加減に、残酷なだけの駆除や捕殺一辺倒の野生動物の生命軽視対応から卒業しなければなりません。シカやイノシシは、殺しても殺してもすぐ環境収容力に見合った元の数にもどります。膨大な税金を使って何をしていることかわかりません。発想の転換が必要です。
大発見!シカは捕食者やハンターがいなくても増え過ぎることなく自ら個体数を調整 馬毛シカ例
- 2021-11-24 (水)
- くまもりNEWS
2021年11月21日(日)環境法律家連盟JELFの公開WEBシンポ「馬毛島の今」が開催されました。
冒頭、熊森の顧問でもある池田直樹弁護士が、環境法律家連盟会長としてあいさつされました。
このシンポジウムの中で、北海道大学大学院文学研究院助教の立澤史郎博士が、一定面積以上の自然があれば、シカは自ら個体数を調整しながら自然と共生して生き続けていくという世界で2例目の非常に興味深い研究を発表されました。
巨大な滑走路が造られ、自然が大破壊されてしまった現在の馬毛島
馬毛島(まげしま)は、種子島西方12㎞の東シナ海上にあり、面積は8.20km2最高地点の標高は71.7m、現在は、鹿児島県西之表(にしのおもて)市に属する無人島で、1986年に鹿児島県設鳥獣保護区となっています。
この島に生息する哺乳類はマゲシカとジネズミだけで、マゲシカの捕食者はいません。マゲシカは「奈良のシカ」よりも古くから文献に記録があり、地元種子島では大変親しまれてきた動物で、不思議なことにすぐ近くの種子島のシカとも違う固有の遺伝子を有しています。そのため、環境省が「地域個体群」としてレッドリストにあげているシカです。

マゲシカ(毎日新聞写真より)
これほど小さな面積に数百頭のシカの群れが1000年以上にわたって維持されてきたことが確かな場所は、世界でも例がないそうです。
滑走路が造られる前の馬毛島の豊かな自然
立澤博士は、このマゲシカ個体群がどのようにして、増えすぎもせず減りすぎもせず個体群を維持してきたのかに興味を持ち、1987年以降30年以上にわたって調査を続けて来られました。
その結果、シカが増え過ぎると、妊娠率が落ちたり、オスの子供を中心に大量餓死が起きたりして(餓死とはかわいそうですが、これが自然)、増えたシカが島の植物を食べつくしてしまう前に、自ら個体数を減らして、シカの個体群も島の豊かな自然も持続させてきたことが分かったそうです。
これは、生態学上のすごい!大発見です。
これまで、ワイルドライフマネジメント派の研究者は、人間が適当に野生動物を殺してやらなければ、彼等は増え過ぎて自然を食い尽くし絶滅する。彼らが絶滅しないように、個体数管理を人間がしてやらねばならないと言って、駆除やハンティングを奨励してきました。しかし、立澤博士の研究で、このような自然観は間違いであったことが分かります。
人間なんかいなくても、自然界は持続可能だったんだ。
人間よ、おごるなと思い知らされました。
こんなことがわかったのも、無人島馬毛島が鹿児島県にあり、そこにマゲシカが棲んでくれていたからで、馬毛島の自然もマゲシカも、この上もなく学術的に貴重です。立澤博士は、馬毛島でなければ研究できない生態学上の貴重な課題がまだまだ多くあると言われています。しかし、人々から島の土地の99.6%を買い集めたタストン・エアポート(馬毛島開発から商号変更)から、この20年間立ち入りを禁止され、研究できない状況に追い込まれておられます。
島の所有者は、最初この島を開発してレジャーランドにしてもうけようとしたようですが、うまくいかず断念。次々と用途計画が変更されました。2011年6月、防衛省との間で、アメリカ軍のFCLPの移転先として検討とすることが発表されました。この後、所有者は島を軍事基地として国に高く売りつけようと、林地開発の許可を大きく超えて大規模な伐採・整地・盛り土をおこない(違反行為)、島を十字に横切る「滑走路」を建設しました。島の自然は大破壊され、マゲシカの生息数は半減しました。
2019年12月3日に当時の河野太郎防衛相が記者会見で、防衛省と馬毛島の所有者との間で、約160億円の売買契約の合意に至ったことを発表。その後、馬毛島の基地化計画がどんどん進められていきました。2020年8月には、同島のほぼ全域を自衛隊やアメリカ軍の総合基地として開発する以下の計画が公表されました。
島の9割を占める赤線内が、
戦闘機が爆音をとどろかせる基地に。
残り1割は、マゲシカの生息不適地。
マゲシカはどうなっちゃうの
今の基地計画では、誰が見ても、マゲシカの生存はもはや不可能です。
こんなの、日本が批准している生物多様性条約に違反です。
マゲシカは防衛省によって絶滅させられそうになっています。
ちなみに、ネットで最新情報を検索すると、防衛省は、環境影響評価(アセス)手続き中にもかかわらず、基地整備に使うコンクリートを作るプラント工事の入札を公告しました。いよいよ工事が始まるのです。多くの漁民や市長は、馬毛島の基地化に反対しています。(南日本新聞社2021年11月21日記事)
早く止めないと基地が造られてしまう。
マゲシカが絶滅させられてしまう。
全国民の、全世界の大問題にしていかねばならないと熊森は思います。
みなさんはどう思われますか。
11/13 地元の会と熊森が、大苗植樹で人工林皆伐跡地の広葉樹林化に挑戦 於:兵庫県千種町
- 2021-11-20 (土)
- くまもりNEWS
兵庫県宍粟市千種町に、戦後、自然林を皆伐してスギやヒノキを植えた官行造林地300ヘクタールがありました。
2000年、この造林地が皆伐されることになりました。植樹後、手入れがなされていなかったため、当時、いい感じの針広混交林に育っていました。官行造林地としては失敗作ですが、熊森は伐採すべきではないと保全運動を展開しました。
なぜなら、人工林率83%の千種町に於いて、この官公造林地内に大きく育ったブナやミズナラの広葉樹は、クマをはじめとする千種町の野生動物たちの貴重な餌源となっていたからです。
結果、一角は皆伐されてしまったものの、ほとんどが保全されました。当時の千種町長を初め役場の皆さんの英断に、熊森は今も深く感謝しています。
皆伐されてしまった官公造林地の一角
この一角を、広葉樹の天然林にもどそう!
熊森を初め、ライオンズクラブなどいくつかの団体が、この一角の天然林化に挑戦しました。
しかし、現地は急斜面・豪雪地・シカ高密度の3悪条件がそろった場所で、努力しても努力しても広葉樹の苗木は育たず、やがて動物たちが生息できないススキが原になってしまいました。
熊森もついにこの場所の天然林化を断念
その後、地元のNPO団体「千種川源流を守る会」が、シカの口が届かないような大苗を植えれば天然林に戻せるのではないかと考え、実験。見事、苗木が根付いたのです。地元からの協力要請が熊森にあり、11月13日、いっしょに本格的な大苗植樹会を実施することになりました。
大苗を人力で山の上に運びあげることは不可能ですから、地元がショベルカーを山に入れて、急斜面の山に車が通れるようにまず道を造られました。この道は、植林地の整備や、後には登山客のための遊歩道となるよう考えて造られています。
ススキが原を切り開いて、地元が山の斜面に造ったゆるやかな道
祝 大苗植樹会
当日、室谷悠子会長を初め15名の熊森会員がボランティアとして参加し、地元の皆さんと一緒に植樹に精出しました。
○「千種川源流の会」代表の阿曽さんの挨拶
「千種川の源流を守るということは、川でつながった瀬戸内海までも視野に入れて、水の循環を守るということです。また、わたしたちは、小水力発電にも取り組んでおり、地域で消費するエネルギーの完全自給もめざしています。町をあげて、自然を破壊しない自然エネルギーを推進してまいります。」
○室谷会長の挨拶
「地元の皆さんのお力で、熊森が一度は断念したこの地の天然林化に再び取り組むことができるようになりました。うれしいです。」
0歳の長男を抱きながら、娘さんと一緒に広葉樹の植樹に取り組む室谷会長
道に沿って2メートルほどのヤマボウシやヤマザクラなどの大苗、1メートルほどのドウダンツツジなどの苗木を植えていきました。

大苗を植えるボランティアの方
みんなで植えた大苗
本当は、もっと大きな大苗を植える予定でしたが、掘り起こせなかったということで、近くの農家の方が造られていた苗木に急遽切り替えて植樹しました。大苗以外にも、枝を短く剪定した太めの苗木も植えました。
この日の植樹は、地元の造園会社「千種園」の池田さんが植え方を指導してくださいました。参加者の皆さんは穴の掘り方や肥料の入れ方、最後の土の被せ方などを学びながら植樹していきました。
この日植樹したのは、ヤマザクラやヤマボウシなど17本、カエデ160本、ドウダンツツジ80本です。
参加された熊森会員のみなさんは、「来年、この苗木がどうなっているか絶対に見にきたい。来年はもっと実のなる木を多く植えたい」と、楽しそうに語っておられました。植樹会は来年も続きます。
参加者のみなさん、ご苦労様でした!
とよ君、ただいま、冬ごもり前のドングリ食い込みに余念なし
- 2021-11-14 (日)
- くまもりNEWS
秋も深まってきました。
大阪府豊能町高代寺で保護飼育されているツキノワグマのとよ君(オス11才)、秋になってだいぶん太ってきました。
会員のみなさんから送っていただいたドングリを小山にして与えると、抱え込むようにして乗っかります。
そして、ゆっくり落ち着いて殻を口から吐き出しながら一日中食べ続けています。
冬ごもりに備えての食い込み中です。11月2日撮影
お世話してくださっているみなさんからの報告によると、最近は、1日にドングリを7キロ~10キロ、クマフード0.3キロ、柿やリンゴ2~3個などを与えてくださっているようです。柿やリンゴは食べたり、残したり、食べなかったり、日によって違うそうです。
例年ですと、12月になってもう十分食い込みができて、冬ごもりに入っても大丈夫な体になると、ドングリを食べなくなります。まだ当分は、ドングリを食べ続けるとよ君です。
気温が低下してきていますが、プールにはまだ入っているということです。10月29日撮影
兵庫県養父で人身事故 クマが出て来ないように熊森本部が柿もぎに出動するもすでにクマは駆除
- 2021-11-12 (金)
- くまもりNEWS
(以下、ネット情報)
兵庫県養父市でツキノワグマによる人身事故
11 月1日の朝 7 時頃、農道で散歩中の夫婦が突然前から向かってきた体長約100センチの熊に襲われ、夫が首をひっかかれて軽いけがをし、妻は逃げようとした際に転倒して肩の骨を折る重傷。
夫は持っていた杖を振り回したが、首をひっかかれという。熊は山へと去っていったということです。
市は防災行政無線などで注意を呼び掛けています。
熊森本部が現地を訪れることができたのは、 11 月4日です。
以下は、地元を取材してわかったことです。
当日の朝、いつものように高齢ご夫婦がウオーキングをしていたら、ご主人の先 10m ほどを歩いていた奥さんが、30mほど前からこちらに歩いてくる 1 頭のクマに驚く。背中を向けて走って逃げようとしたはずみで躓き転倒。肩の骨を骨折し動けなくなった。
ご主人はとっさの判断で近寄ってくるクマの方に向かっていき、持っていたストックでクマを突こうとしたところ、クマに首を引っかかれ負傷。クマはそのまま、走って逃げた。
ご夫婦はクマ鈴はご持参されていなかった。1 週間ほど前からクマが集落のカキの木にきてカキを食べていた。
【事故現場付近の様子】
クマとご夫婦が歩いていた農道は、左右を総延長何キロにもわたって金網柵で囲われていたため、クマも人も農道の外に逃げられなかった。
【お怪我をされたご夫婦に】
クマ鈴を持つこと。クマと出会ってしまったときはゆっくりあとずさりすることをお伝えする。
【事故当時のクマの行動】
現場付近を調べたところ、当時のクマのものと思われるクマだなやふんなどの痕跡を 50か所で確認。クマはご夫婦と鉢合わせになる前に、地区で柿を食べて移動中。人と出会ってしまい恐怖のあまり、点々と脱糞しながら逃げていったもよう。
【事故後の行政の対応】
11 月 1 日にクマ捕獲用檻を設置し、11 月 4 日の早朝に罠にかかっていたクマを殺処分。事故を起こしたクマかは不明。
クマが来たと思われる場所付近で、地元の要望により、柿もぎ開始
【区長さんから】
カキもぎをしてくれる人をずっと市に要望していたので、やっと派遣してくれたとうれしかった。(熊森注:行政からの連絡なし。熊森がニュースを見て独自に出動)
【作業】
11 月 4日は2名、5 日は 5名で、午前 10 時から作業し、昼を食べて 16 時ころまで、柿の木を伐倒したり、枝を切ったり、実をもいだりした。
地元の方は、山にスギを植えたが、管理ができないまでに植えすぎてしまったと反省されていた。クマは怖いから近くにいてほしくないが、山にはいるべきだと言われた。兵庫県のクマの駆除数を伝えると、そんなに殺していたのかと数の多さにおどろかれていた。
熊森さんにはまた来てほしいと、喜んでもらえた。
熊森から
クマが山から出て来なくてもいいように、山に柿やクリなど実のなる木をたくさん植えてやりたいです。
以下は、今回の活動に参加した西宮の大学生の文です。
(大学生の感想)
今日は野外での活動ということで熊森の活動の一端に関わることができ、とても有意義な時間だったと感じました。クマの命を救うことができず残念でしたが、地元の方々から聞き取りをしたり、新たなクマとの接触を避けるために柿取りなどを行うなど実践的な活動を体験しました。
日本熊森協会がこの6年間で行ってきたクマの人身事故後の再発防止対応は、今回で10件目だそうです。
その中でわかったことは、事故は人間側の行動一つで未然に防ぐことができるということです。例えば、この10件のうちクマ鈴を持ち歩かれていた方は0名でした。クマに、人間の存在を知らせる音が届いていなかったのです。持ち物一つで、人がけがをするか、クマが殺処分されるかという大きな事件に発展してしまうんだと思いました。
【野生鳥獣ご担当の行政の皆様方へ】
熊森は、野生動物を殺さず、かつ人間の命や安全も守る方法で被害対策を行います。人身事故が起きた原因を究明し、再発防止指導をします。クマを殺す前に、誰かがけがをしてしまう前に、クマが出てきて困っているときは熊森にご連絡をいただきたいです。ぜひお願いします。
日本熊森協会本部 野生鳥獣担当 TEL0798-22-4190 メール:field@kumamori.org 担当:水見
兵庫県佐用町 なぜ?ウッドデッキで寝そべるクマ、衰弱し殺処分に
- 2021-11-12 (金)
- くまもりNEWS
配信

ウッドデッキで横たわったままのクマ=兵庫県佐用町(町提供)
兵庫県佐用町の民家のウッドデッキで10月31日、ツキノワグマとみられる高齢のクマが横たわっているのが見つかった。衰弱しており、翌1日になっても民家から離れなかったため、佐用町が殺処分した。
町によるとクマは雌とみられ、体長約1・2メートル、体重は約30キロ。
住民の男性(73)が10月31日朝に発見し、兵庫県警や町に連絡した。
住民の男性はクマ発見後、民家近くにある別棟に一時避難。町職員らが交代で監視するなどしていた。
一方でクマは衰弱し、発見から24時間が過ぎた11月1日昼以降も動く様子がみられなかった。
同日午後2時半ごろ、町職員が県から許可を得た上で麻酔銃をつかって捕獲し、殺処分した。
佐用町内では10月に約20件のクマの目撃情報があり、町が注意を呼び掛けていた。(以上)
熊森から
熊森スタッフたちが現場を訪れました。まわりに住宅が多くある場所でした。
地元の方から聞いた当時の様子を、以下にまとめます。
・10 月 31 日
朝、家の裏の茂みから動物の唸り声が聞こえた。
12時ごろ、ベランダに毛の白いクマが寝ているのを発見した。クマは、人間の存在に気づき、動き出した。様子が変で、前足を使いほふく前進をしながら庭の茂みへ逃げた。目を離すと、また、ベランダで寝ていた。クマの息は荒くて、後ろ足が動かなく、かなり衰弱している様子だった。
すぐ行政に届け出た。自分は、クマを怖いと思ったが、衰弱する姿はさすがにかわいそうで、水ぐらいは与えてやりたいと思ったが、外には出られなかった。警察と行政職員がクマの見張りを行った。
・11月1日
昼頃、兵庫県森林動物研究センターの職員が来て、安楽死させた。
死期を察して、天敵に狙われないように、屋根付きのベランダに来たのではないかと思った。
熊森から森林動物研究センターに電話して、「こういう時はわざわざ殺処分しなくても、もうそっと死なせてやったらよかったのではないですか。死期を察したクマが、人間を信頼して山から出てきたのだと思います。クマは殺されたくてウッドデッキに来たのではないと思うんですが」というと、「おかしなこと言いますね。人身事故が起きたらどうするんですか。そんなこと言う人はいませんよ」と言われてしまいました。
熊森と森林動物研究センターのみなさんとは、このような時、いつも意見が合いません。
みなさんは、はどう思われますか。
11月8日 飼育グマが取り持つ仲間たち 和歌山県生石高原で、3支部会員が交流
- 2021-11-12 (金)
- くまもりNEWS
他生物への共感が、自然保護活動の原点です。
以下は、和歌山県真造支部長からの投稿です。
11月8日にたろうちゃん、くまこちゃんのお世話をしました。

この日は和歌山県支部の6名に加え、京都府支部から6名、石川県支部から8名、本部から2名の計22名の方が一堂に会しました。
おしゃべりをしながら全員で獣舎の掃除をし、お弁当を食べ、楽しい一時でした。たろうちゃん、くまこちゃんが取り持ってくれた縁に感謝です。
石川県の皆さんは久々のくまこちゃんとの再会を、京都の皆さんは初めてのご対面を喜んで下さっていました。
くまこちゃんは育ててくれた石川県の皆さんに逢えてハイテンションでした。
たろうちゃんは寒さ、高齢のためでしょうか、心なしか元気がなかったのが気掛かりです。
国の規制緩和で“加速” 太陽光発電に法規制なく 温暖化防止の大義で里山無残 熊本日日新聞
- 2021-11-07 (日)
- くまもりNEWS
以下は、11/6(土) 8:35 熊本日日新聞 ネット配信より
「令和の公害」 土砂流出、住民トラブル

山肌がむき出しになったメガソーラーの建設現場。8月の大雨などで大量の土砂が近くの農地や河川に流出した=南関町小原(小型無人機で9月に撮影)
熊本県南関町小原の大規模太陽光発電所(メガソーラー)の建設現場で8月、大雨によって大量の土砂が農地や河川に流出した。
政府は2050年の脱炭素化達成に向け再生可能エネルギー導入を「最優先」に掲げるが、各地の太陽光発電施設では土砂災害や住民とのトラブルが発生。地球温暖化の防止という大義の裏で、ホタルが住む清流や里山が切り開かれる矛盾も。専門家は「令和の公害」と断じ、法整備を求めている。
南関町では南関ソーラーファーム(福岡県飯塚市)が雑木林などを切り開き、約40ヘクタールに出力40メガワットの太陽光発電所を建設する計画を進めている。しかし、8月の大雨などで露出した山肌がえぐられ、大量の土砂が河川や農地に流れ込んだ。「里山や田畑、河川への被害は深刻。生態系への影響は計り知れない」。現地視察した熊本学園大の宮北隆志教授(生活環境学)は、環境への配慮のない再エネ施設の開発に警鐘を鳴らす。
行政は手続き論に終始
菊池市内の業者が建設している太陽追尾型発電施設(写真上)に向け、「断固反対」を訴える住民ら=9月、同市大平
太陽光発電施設を巡るトラブルは全国各地で相次ぐ。県内でも、菊池市の民間企業が市内に建設している太陽追尾型発電施設の斜面が8月の大雨後に崩落。住民がモーターの騒音や強風時のパネル飛散の危険性、景観の悪化を訴え、施設の撤去を求めている。
「これほどまでトラブルが多いのは、災害防止などに関する法規制がないからだ」。再エネ関連の環境問題に詳しい山梨大大学院の鈴木猛康教授(土木環境工学)は「もはや令和の公害だ」と指摘し、手放しで再エネを推し進める国の姿勢を強く問題視する。
県環境保全課によると、メガソーラーの場合、出力40メガワット以上もしくは20ヘクタール以上の敷地を造成する際には環境影響評価(アセスメント)を義務付け。ただ、対象は出力要件が20年4月、面積要件が同10月以降の申請分で、それ以前はアセスが不要。出力が40メガワット未満ならば、今でも環境アセスの必要はないという。
林地開発や固定価格買い取り制度(FIT)の申請では、県や国は事業者が出した書類に不備がないかを確認するのみ。南関町の土砂流出後、県森林保全課は「林地開発の手続きに従って許可しており、県の対応に問題はない」と説明。九州経済産業局エネルギー対策課(福岡市)も「環境はうちの担当ではない。申請書類に問題がなければ、許可を出す」といい、手続き論に終始した。
県は「南関ソーラーファームに対しては防災工事の実施などを指導してきた」とするが、強制力はなく、土砂流出を防げなかった。
ホタルの里でもあった小原地区。被害を受けた住民への補償が11月中にまとまる見込みだが、70代男性は「自然は元には戻らん」と悔しさをにじませる。
一方、政府は規制を強化するどころか一部緩和し、再エネ推進をさらに加速させる。大規模な風力発電について、環境アセスの対象を10メガワット以上から「50メガワット以上」に引き上げるよう環境アセス法を一部改正し、10月31日に施行した。
このような国の動きに、鈴木教授は「政府は脱炭素化を目指す傍ら、自然豊かな国土を次々に破壊しているようなもの。専門家による事前の環境調査を義務付ける法整備は急務だ」と訴える。(田中慎太朗、植木泰士)
熊森から
熊本日日新聞様、このような記事を掲載していただき、ありがとうございます。
国土交通省、経産省、環境省、林野庁など関係省庁の皆さんに是非現実を知っていただき、再エネなどの太陽光発電は電力大量消費地である都市部で行うよう、至急、方向転換をお願いします。
10/23 兵庫県本部 今年秋のクマの餌場づくり実施しました 豊岡市で実のなる木の植樹
- 2021-11-06 (土)
- くまもりNEWS
一昨年、昨年と、全国各地で人里にクマたちがえさを求めて出てきて、過去最多を記録する大量のクマが駆除されました。一方、今年のクマの目撃数はどこも激減です。本部のある兵庫県でのクマの目撃数も、9月末現在、過去10年間で最少です。殺し過ぎたとしか思えません。
人里にクマたち野生動物が出て来なくていいように、何とかえさ場を奥地に再生してやろう。
熊森は過去25年間、実のなる木の奥山植樹に取り組んできました。しかし、民間の力でできることには限界があります。絶滅してしまう前に、早く、国や行政に奥山広葉樹林化に動いていただこうと、熊森はがんばっています。
現在、日本は、人間が荒廃させた奥山生息地を全く顧みず、個体数調整と言って、クマなどの野生動物たちの生息数を推定計算して、研究者が考えた適正数となるように駆除し続けています。しかし、本来、生息地の保障なくして、クマたち野生動物との共存などあり得ません。
2021年10月23日、熊森本部は今年も兵庫県豊岡市のクマ生息地に、実のなる木25本を植えました。この場所は、人工林の皆伐跡地を放置していた場所で、動物たちの餌にならないミツマタやシンジュの木が育ってきています。
今回の苗木は、あるご夫婦が、ドングリから育ててくださったものです。
苗木の種類は、クヌギです。高さ1.5mほどの苗木が10本ありました。植樹地まで運びあげるのに結構重くて苦労しました。
この場所は、急斜面、豪雪、シカと、広葉樹林化を困難にする3条件がそろったところです。
これまでに何度も実のなる樹を植えてきましたが、春先にシカ除け柵やシカ除け網が、なだれて来る雪に押しつぶされて倒れ、一瞬にしてシカに食べられ、なかなか苗木が育たないという森再生困難地です。
これまで、あの手この手で、シカの食害から苗木を守るためのシカ柵に取り組んできましたが、やっぱり、1本ずつの苗木を囲う元のやり方の方が良かったということになり、サプリガードという鹿除け柵で囲う方法にもどしました。
皆さんでどんどん植えて、柵を作って、効率よく作業は進められていきました。
参加してくださったボランティアの皆さん、今年もありがとうございました。
尚、熊森本部は11月13日(土)、兵庫県宍粟市の標高1000mのクマ生息地で、地元千種町の皆さんの植樹会を手伝います。ここも、急斜面、豪雪、シカと、広葉樹林化を阻む3条件がそろった場所ですが、今回、助成金を使ってブルトーザーを導入する大掛かりな植樹会です。植えるのも大苗ばかりです。
地元は過疎化高齢化が進んでおり、都市市民のボランティア参加が求められています。
自車参加で可能な方は、お知らせください。
お申込先:電話0798-22-4190 メール field@kumamori.org 担当:水見 吉井
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ