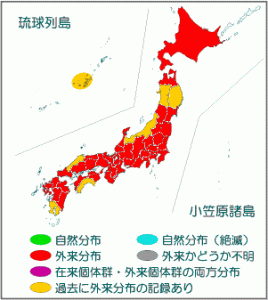ホーム > _野生動物保全
カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧
つくられた有害鳥獣 反省なき大量駆除
神奈川県会員が、以下の埼玉新聞記事を紹介してくださいました。
(熊森から)
人間が野生鳥獣を有害鳥獣にしているのであり、その原因の半分が、小島望氏の記事によってズバリ指摘されています。原因の残りの半分は、拡大造林など人間による森破壊で、こちらの方は熊森が発足当時から指摘し続けてきたことです。
埼玉県の川口短期大学に、鳥獣被害増大の原因が人間にあることを見通しておられる教授がいらっしゃることを知って、うれしくなりました。
全国の研究者、行政マンに、読んでいただきたい記事ですね。
それにしても、「日本政府の現状認識能力の欠落と先送り体質が如実に表れている」は、至言です。
優秀なはずの官僚のみなさんが、どうしてほとんど誰もかれもが物言えぬ野生鳥獣に罪を背負わせ、彼らを殺すことしか考えない人間になっていくのでしょうか。どうして生命の尊厳がわからなくなっていくのでしょうか。
公務員になった時は、みんな正義感に燃えていたはずです。
日本の行政システムに、重大な欠陥があるとしか思えません。
行政は、人間が原因を作っているのに全く反省することなく、野生動物を殺害することを猟友会や業者に指示することで目の前をごまかそうとしています。
誰だって殺生は嫌ですから、行政は自分の手は汚しません。部屋の中にいるだけです。
野生鳥獣から見たら、今の人間は悪魔でしょう。
熊森は訴えます。人間は悪魔であってはならない。
人間本来のやさしさを取り戻すためにも、熊森は野生鳥獣の保護運動を続けます。
くまもり本部2018年7月度 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)
- 2018-06-28 (木)
- _環境教育 | _野生動物保全 | いきもり | お知らせ(参加者募集) | 太郎と花子のファンクラブ | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」
熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。
会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。
学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。
ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。
本部電話番号 0798-22-4190
本部FAX番号 0798-22-4196
メール contact@kumamori.org
2018年7月の活動予定
<いきものの森活動>
7月7日(土)植樹地の草刈り(兵庫県豊岡市但東町)
午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください
- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、どなたでもご参加いただけます。
現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。
雨などで中止になることもあります。
<環境教育例会(於:本部事務所)>
7月2日(月) 毎月第1月曜日
- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。
<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>
7月3日、10日(満席)、16日、24日、31日
(第1,2,4週は火曜日、第3週のみ月曜日)
- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。
現地までの交通手段は本部にご相談ください。
<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>
7月22日(日)(毎月第4日曜)
参加費:1000円(交通費)
- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。
環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。
自車参加も可能です。
たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。
外来種アライグマを駆除しないヨーロッパの合理的精神を見習うべし
NPO法人環境研究所豊明が発行している機関誌「はちどり」VOL46(2018年4月発行)が、ヨーロッパにおける外来種問題を特集しています。
それによると、ヨーロッパでも外来種アライグマが急速に増えているそうです。
根絶がほぼ不可能であることもあって、WWFをはじめとする環境保護団体も各国政府も緊急に駆除が必要とは考えておらず、ドイツ最大の自然保護団体NABUも平和的共存の立場です。すでに帰化動物とされており、ふつうの狩猟対象動物です。
(熊森から)
日本でアライグマの野生化が正式に確認されたのは1977年だそうです。
40年を経過し、すでに広範な国土で繁殖してしまっているアライグマの根絶など不可能です。
<アライグマの分布図:国立環境研究所資料より>
アライグマは多産のため、殺しても殺しても餌がある限りすぐ元の数に戻ります。
未だに国民の税金で大量の根絶殺害を続けている日本は、無用の殺生をしているにすぎません。
民家の屋根裏に入られないように屋根に通じる穴をふさぐなど、税金は被害防止に使われるべきなのです。
その方がずっと合理的であり、効果的です。
アライグマは、もはや自然生態系に組み込まれて落ち着くのを待つしかありません。
アライグマを見つけて助けようとし、殺すしかないと言われて胸がつぶれる思いをしている人がたくさんいます。
環境省が2004年に作った「特定外来生物法」というバカげた法律のせいです。
この法律で喜んでいるのは、お金をもらい続けることができる駆除業者だけです。
無用の殺生をやめるよう、みんなで声を挙げましょう。
行政のみなさんも意地を張るのはやめて、間違ったと気付いた時点ですぐに取りやめる勇気を持っていただきたいです。
元外来動物だった多くの動物が、今や日本の生態系に取り組まれて落ち着いています。
ネコ、スズメ、モンシロチョウ、アメリカザリガニ、ドバト、ハツカネズミ、ウシガエル、ドジョウ・・・帰化動物でいっぱい、書ききれません。
自然生態系を守りたいくまもりが環境省にやっていただきたいことは、外来動物の輸入を止めることです。
当初から、ずっと主張し続けてきました。
くまもり本部2018年6月度 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)
- 2018-05-24 (木)
- _環境教育 | _野生動物保全 | いきもり | お知らせ(参加者募集) | くまもりNEWS
熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。
会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。
学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。
ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。
本部電話番号 0798-22-4190
本部FAX番号 0798-22-4196
メール contact@kumamori.org
2018年6月の活動予定
<いきものの森活動>
毎月第3火曜日、他
6月2日(土)植樹地の草刈り(宍粟市波賀町原 リンゴ園裏山)
6月19日(火)植樹地の草刈り(宍粟市波賀町原 リンゴ園裏山)
午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください
- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、どなたでもご参加いただけます。
現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。
雨などで中止になることもあります。
<環境教育例会(於:本部事務所)>
6月4日(月) 毎月第1月曜日
- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。

保育園児への環境教育
<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>
6月5日、12日、18日、26日
(第1,2,4週は火曜日、第3週のみ月曜日)
- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。
現地までの交通手段は本部にご相談ください。
<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>
6月24日(日)(毎月第4日曜)
参加費:1000円(交通費)
- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。
環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。
自車参加も可能です。
たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。
2月17日 兵庫県シカシンポ 生息地を失った哀れなシカを殺す話ばかり 胸が悪くなりました
<森林動物研究センター主催シンポジウムの感想>
基調講演を聞いて、気候も風土も文化も歴史も違うヨーロッパやアメリカのシカ狩猟が、なぜ日本がめざすモデルになりうるのか疑問に思いました。
大変な思いをして集落総出で土や石を運んで造ったシシ垣で、集落や農地を徹底的に囲い、全体としてはシカを殺さずに共存してきた私たちの祖先のシカ対応の方が、ずっとレベルが高いと思います。
奈良大学名誉教授の高橋春成先生は、滋賀県や三重県などに残された大量のシシ垣跡を研究されています。また、京都大学には金網柵からなる現代版シシ垣を考案して普及させようとされている研究者もおられます。
実際、兵庫県は今や平成のシシ垣ともいえる金網柵を郡部に、8262km(平成28年度時点)張り巡らせて、集落や農地を徹底的に囲い続けており、熊森もこの点に関しては、兵庫県を高く評価しています。
問題なのは、現在、農地や田畑から追い出したシカの行き先を山にしていることです。森とシカは共存できません。森の下層植生は脆弱なので、シカが食い尽くすと消えてしまいます。その結果昆虫も激減し、兵庫の森の中はクマも棲めなくなって、今、大変なことになっています。
そもそもシカは、やわらかくて背の低いイネ科やカヤツリグサ科などの草におおわれた草原(ススキは食べられないので、ススキが原では生きられません)や湿地をえさ場にして生きてきた林縁の動物です。危険を察知すると草原から林内に逃げ込んでいたようです。
これらの草原の草は、森の下草と違って、食料生産量がとても大きいので、シカのような大型野生動物でも養うことができます。冬は草が枯れるために餓死するシカも出るでしょうが、そうやって自然界がシカの頭数を調整するのだと思います。
戦後これらの草原や湿地を、農地や宅地としてつぶしてしまったのは人間です。今や、シカが草を食める草原は、スキー場ぐらいしかありません。
現在シカは、森を破壊する害獣にされていますが、戦後の拡大造林政策で奥山に一時期大草原を誕生させたり、林道を造り続けてシカを山奥にまで導いたのは人間です。
突然現れたシカの群れに悲鳴を上げておられる地元の惨状をこれまでいくつか見聞きして、私たちも胸を痛めてきましたが、といって人間がしたことを反省することなく、いかにして効率よくシカを大量にハイテク技術で殺せるかだけを発表されても、拍手する気が起きませんでした。ハイテク罠の扉が遠隔操作で落ちた瞬間、罠の中のシカやイノシシが恐怖で必死のジャンプを続けている映像は残酷すぎて、見ていて気分が悪くなりました。子どもたちがみたら胸がつぶれると思います。
人間が知らないだけでシカにも自然界に存在する大きな意義があるはずです。この県土で生きる権利もあります。江戸時代の兵庫県内のシカの密度は大変なものだったという研究発表もあります。やみくもに見つけ次第シカを殺すのではなく、シカが安心して生存できる草原や湿地を保証して、奥山からシカを移動させ戻れないようにする方策を考える必要があると思います。
大学に狩猟学を導入して銃を使える人を増やし、シカやイノシシの狩猟文化を日本に創成しようという基調講演には違和感を感じました。生きとし生けるものとして畏敬の念を持って殺さずに棲み分け共存してきた祖先の文化こそ取り戻すべきだと思います。
森林動物研究センターのシンポジウムはいつも野生動物を殺すことによって野生動物問題を解決しようとする西洋思考の研究者たちの発表だけです。野生動物は殺すしかないのだと県民を洗脳する場になっているような気がします。公的な費用で実施するのですから、もっと多様な野生動物対応を国民に提示するシンポジウムにしてほしいと願います。
クマ狩猟終了 兵庫1頭、岡山0頭 これを見ても、まだクマ絶滅の危機に気づかない行政とは!
今年の11月15日から1か月間、兵庫県と岡山県は、クマが爆発増加しているという若い研究者(=現在、野生動物捕獲会社社長)の言葉を信じて、狩猟を推奨しました。
岡山県:上限30頭 狩猟者は誰でもクマを撃って良い。 結果0頭
・・・・11か所でクマ狩猟講習会を開催
兵庫県:上限は100頭 クマ狩猟許可取得者154名 結果1頭
・・・・3か所でクマ狩猟講習会を開催
兵庫県は今年、ドングリの実りが良かったため、一部のクマが里から山に帰っていることが、熊森のクマ痕跡調査からわかりました。
この1か月間「山中にいるクマまでも殺さないでほしい」という思いでいっぱいでした。
熊森本部は、兵庫・岡山の両県行政にほぼ毎日電話して、クマの狩猟状況を聞いてきました。
11月26日に、兵庫県朝来市で1頭のクマが狩猟された時は、山の中に潜んでいただけなのに、絶滅が危惧されるのにと、胸が痛みました。
12月15日付の神戸新聞によると、このクマはシカやイノシシを追い込む狩猟中に出て来たために銃で撃たれたということです。
12月14日の兵庫県知事定例記者会見で、兵庫県井戸敏三知事は、クマ狩猟数1頭の結果に対して、次のように答えられました。
「率直な感想として、昨年発生したハンターの死亡事故が起きたことでちょっと慎重になりすぎたと思う。
だけど、1頭では困る。適正頭数よりも130-140頭オーバーしているはずなんで、さらにどういう対応をとるかというのも考えないといけませんね。」
2016年5月10日、熊森本部は井戸知事にお会いし「クマは爆発増加などしていません。山が大荒廃したので、餌を求めて生きるために里に出て来ただけです。狩猟再開ではなく、昔のように人間とクマの棲み分けができるよう、奥山の生息地復元に取り組んでください。」と、多くの資料をお持ちして説明しました。
その後も、全国から同様のメッセージを井戸知事へ何度も送りました。にも関わらず、知事からクマの生息地復元の話は全く出ず、出てきたのは「狩猟数をもっと増やすにはどうすればいいのか」というものでした。
兵庫県は、来年度以降も、クマ狩猟を継続する方針だそうです。
生息地を失った兵庫県や岡山県のクマが爆発増加しているのなら、その原因を聞きたいです。研究者の計算ミスであったことに、もういい加減に行政の皆さんも気づいてほしいです。
今こそ、「王様は裸だ」という、子供の登場が必要な、両県です。
なぜ、「クマは、もう山におらん」という、猟師たちの声を信じずに、有名大学出ではありますが、現場経験の少ない若い研究者のコンピューター計算の結果に、優秀な行政マンたちが引っかかってしまうのでしょうか。残念の一言です。
クリックしていただくとグラフが拡大します。
兵庫県が重用している若い研究者によると、1992年にクマが絶滅するとして、兵庫県猟友会が狩猟を自粛し、1996には兵庫県も正式に狩猟を禁止したため、60頭だった兵庫県のクマが爆発増加し始め、20年後の2016年には、約16倍の940頭にまで増えたそうです。
ならば、単純計算としても、狩猟自粛前の1991年の狩猟数である15頭の16倍にあたる240頭のクマが狩猟されねばなりません。現在は、昔と違って、クマ生息地の多くが下層植生が消えて遠くまで見渡せますから、以前よりはずっと狩猟しやすいはずです。
昨年、大阪から来たハンターが兵庫県で死亡事故を起こしましたが、兵庫県担当部署は、クマ狩猟とは関係のない事故だと言われました。関係あるのかないのかどちらなのでしょうか。
ちなみに、人里に出て来たからとして、今年兵庫県は有害駆除したクマ数は、32頭です。クマは本来の山に棲めない、集落周辺に潜んでいるという熊森の主張がこれからも確認されたはずですが・・・
熊森の見解は、兵庫のクマが現在仮に940頭いるのなら、昔はもっといたのではないかというものです。何頭いてもいいのです。山の中に棲んでいてくれたら。人間には、山中にいる野生動物の生息数を調整する権利も能力もありません。
人間がしなければならないのは、人間が破壊したクマたちの棲息地を復元してやり、かれらが山中に棲めるようにしてやることです。
くまもり本部2017年9月度> 自然保護ボランティア募集(初参加、非会員も歓迎)
- 2017-09-01 (金)
- _クマ保全 | _野生動物保全 | いきもり | お知らせ(参加者募集) | 太郎と花子のファンクラブ | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」
※拡散希望
熊森協会本部では、各分野のボランティアを募集しています。
会員・非会員に関わらず、多くの方々にご参加していただきたいです。
学生さんや若い方も、みなさん誘い合ってご参加ください。
ご参加いただける方は、活動日の3日前までに電話、FAX、メールにて熊森協会本部事務局までご連絡ください。
本部電話番号 0798-22-4190
本部FAX番号 0798-22-4196
メール contact@kumamori.org
2017年9月の活動予定
<いきものの森活動>森林整備
9月9日(土)柿の植樹地の草刈りと電気柵設置(兵庫県宍粟市波賀町原)
9月23日(土)高代寺の竹の伐採(大阪府豊能郡豊能町)
午前8:00に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。
- いきものの森活動は人工林の間伐や実のなる木の植樹、クマの潜み場の草刈りや柿もぎなど、兵庫県北部を中心に実施しているフィールド活動です。参加者のペースに合わせて活動を進めていきますので、誰でもご参加いただけます。
現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。
天候不順で中止になることがあります。
当日連絡先090-1073-0980(担当:家田)
<環境教育例会(於:本部事務所)>自然の大切さを伝える
9月7日(木)10:15~ 見学も歓迎。
- 小学校や保育施設などで、森や動物の大切さを伝える環境教育を実施しています。環境教育例会では、授業に向けての練習や打ち合わせ、プログラムの作製を行います。絵本の読み聞かせや紙芝居にご興味のある方、子どもがお好きな方、ぜひご参加ください。
<とよ君ファンクラブ(大阪府豊能町高代寺)>飼育グマのお世話
9月7日、14日、21日、28日(毎週木曜日)
- 大阪府豊能町で保護飼育しているツキノワグマのとよ君のお世話です。
現地までの交通手段は本部にご相談ください。
<太郎と花子のファンクラブ(和歌山県生石町)>飼育グマのお世話
9月24日(日)(毎月第4日曜)
参加費:1000円(交通費)
- 和歌山県生石高原で保護飼育しているツキノワグマの太郎と花子のお世話です。
午前8:30に阪急夙川駅南口ロータリーに集合してください。
現地までは本部が用意した車にご乗車いただけます。
環境教育以外は兵庫県ボランティア保険(4/1~3/31の年間500円)への加入が必要です。
太郎と花子のファンクラブ以外は本部の車に乗車される場合、集合場所から現地までの交通費は不要です。
自車参加も可能です。
たくさんの方のご応募をお待ちしております。よろしくお願いします。
(環境省)自然保護の象徴・オオタカの「希少種」指定を解除
- 2017-09-01 (金)
- _野生動物保全
オオタカは、平地から山岳地帯にまで生息している猛禽類(留鳥・渡り鳥)で、水田や畑、森林が混在する里地里山を主な生息地としています。
食物連鎖の頂点に位置する鳥で、里地里山に豊かな自然が残されていないと生息できません。
オオタカ
日本国内では、生息地の大規模開発などによって数が激減し、1984年の調査で約400羽とされ、絶滅の恐れが指摘されました。
そのため、1993年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が施行されると、「希少野生動植物」に指定され、保護対象となりました。
「希少種」に指定されたことで、捕獲や輸出入が禁止され、土地所有者は「保存に留意する」義務を負うこととなりました。その結果、これまでオオタカの生息が乱開発の歯止めとなり、オオタカが自然保護に果たしてきた役割には絶大なものがあります。
そのうち、東日本や里地でオオタカの数が回復してきて、2000年代の環境省調査では生息数が最大9千羽近くと推計されました。
●この度、「希少種」指定が解除されたことに対して、環境省希少種保全推進室担当者に熊森本部が電話で聞き取りました。
熊森:環境省ホームページを見ると、6/3~7/2のパブリックコメントの応募演数は、97件ですよね。(自然保護団体からの応募はゼロ)ほとんどの意見は、オオタカの希少種指定解除に反対していますが、それでも希少種指定を解除されるんですか。
環境省:中央環境審議会の答申です。希少種指定を解除するための審議会です。
熊森:もう答えは決まっていたのですか。パブコメの結果は関係ないのですね。
環境省:指定を解除するかしないかは、多数決で決めるものではありませんので。
熊森:では、何のためにパブコメをとられたのですか。
環境省:希少種指定を解除した後のことなど、いろいろとご意見を参考にさせていただきます。
熊森:希少種指定を外されたオオタカは、これからどうなるのですか。
環境省:これまではオオタカの学術捕獲や飼養登録などは地方の環境事務所の許可が必要でした。これからは都道府県の許可となります。普通の野生鳥獣となるので、「鳥獣保護管理法」が適用されることになります。具体的には、有害捕獲の申請をしたら、駆除できます。
熊森:オオタカが有害駆除されるのはどういう時ですか。
環境省:ハトなどを食べるので、鳩小屋に入ってハトを食害する可能性があります。
熊森:これまでオオタカの存在がどれほど多くの乱開発を止めてきたかわかりません。環境収容力以上に増えることはできないのですから、全国に9千羽ぐらいいたっていいじゃないですか。
環境省:そういうことではなくて、希少種ではなくなったから希少種指定から外すということです。新たに希少種に指定しなければならない鳥が次々と誕生していますので。
(熊森から)
オオタカを希少種から外さないようにとパブコメに応募してくださったみなさん、ありがとうございました。全国に9千羽しかいないのなら、希少だと思います。
今回の措置に、開発業者は大喜びしていることでしょう。破壊された自然は回復していないし、餌のウサギは減少したままだし、オオタカにとっては厳しい状況が今後も続きます。引き続き、手厚く保護すべきだと思います。
これまでオオタカが果たしてきた<乱開発を止める>という役割を、新たに希少種となった鳥が果たせるのでしょうか。開発が止まらない日本には、ぜひそんな鳥獣が必要です。
(農林水産省) 鳥獣捕獲「尾」で証明…ハンターによる補助金不正が相次ぎ、ルール統一へ
以下、読売新聞/ 2017年8月31日記事コピー
有害鳥獣の捕獲頭数を水増しして報告し、補助金をだまし取る不正が各地で相次いでいることを受け、農林水産省は、各自治体がそれぞれ定めている補助金申請時のルールを統一する方針を固めた。
捕獲個体の証拠写真を撮影する際、体の向きを統一し、提出する部位は「尾」に限定することで、同じ1頭を複数頭に見せかける手口などを防ぐ。来年4月から適用する。
鳥獣による農作物被害は年間200億円近くに達し、同省は2012年度から、シカやイノシシなど1頭あたり8000円の捕獲補助金を自治体を通じて支給している。補助金申請時には、証拠写真や鳥獣から切り取った牙や耳などを提出する必要があるが、細かなルールは自治体の判断に任されている。
兵庫県や鹿児島県で昨年度、同じイノシシを異なる方向から撮影して複数頭に見せかけたり、補助金が出ない冬季に捕獲したシカの耳を冷凍保存して、後に提出したりするケースが発覚していた。
(熊森から)
お金が絡んでくるとどうしても、不正をたくらんでもうけようとする人が出て来ます。
以前、ある県の猟友会長さんが、補助金制度は猟友会内に犯罪者を誕生させるものだとして、有害駆除費をゼロにしてほしいと言われていました。
それにしても、各地でハンターの不正が相次ぐというのは、困ったものです。
エゾナキウサギの写真集
エゾナキウサギの写真集を見ました。
2010年7月にまだ残雪が残る大雪山にヒグマ調査に行った時のことを思い出しました。
あちこちに穴があいている岩場がありました。
氷河期の生き残りであるエゾナキウサギの巣穴だということでした。
巣穴に手をかざすと、ひんやりとした風が巣穴から出ていました。
エゾナキウサギはこの冷涼な環境がなければ生き残れないということで、何ともはかなくデリケートな生き物であることよと思いました。
写真を撮りたいと思いましたが、警戒をして登山者の前になど出てこないので不可能だと思いました。
ところが、写真集を見て、このエゾナキウサギの写真を撮っている人がいることがわかりました。
どの写真のエゾナキウサギも全ての生態が愛らしく、見終わってすぐに、鳴き声と動きを知りたいという衝動に駆られ、ネットに走りました。
解説を読むと、まだ天然記念物になっていないのだそうです。
なぜこんな貴重な生き物がまだ天然記念物になっていないのかと憤りを感じ、文化庁にすぐに電話をしました。
<文化庁希少種保全推進室担当者の答え>
天然記念物は、文化財保護法に基づき、動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを指定して、その保存と活用を図る制度です。
天然記念物の指定については、通常は事前に地元の教育委員会から指定に向けた相談があり、その後、調査結果などに基づく学術的価値の評価や生息・生育状況、利害関係者の同意など指定の検討に必要な情報を含む意見具申書を提出していただき、その意見具申書に基づいて、文化審議会への諮問などによる、指定に係る検討が行われます。ナキウサギについては、これまでそうした動きには至っていません。
なお、北海道中央部では大雪山が天然保護区域として昭和52年に特別天然記念物に指定されており、その指定範囲内では、ナキウサギを含む動物や植物、地質鉱物が特別天然記念物として保護されています。指定範囲に係る現状変更等の行為は規制されていますので、当該指定地において、ナキウサギが絶滅する程にその生息環境が人為的に大きく物理的改変を受ける可能性は極めて低いと考えられます。
(熊森から)
エゾナキウサギもヒグマも北海道の先住民です。私たち人間は、彼らの生息地をこれ以上壊さないように注意し、畏敬の念を持って共存しなければなりません。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ