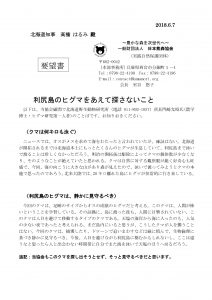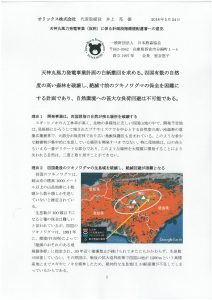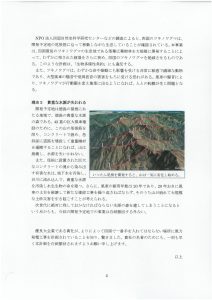ホーム > くまもりNEWS
カテゴリー「くまもりNEWS」の記事一覧
山口県下松市の住宅街 麻酔銃で捕獲したクマを殺処分 熊森山口県支部長が県庁を訪問
5月21日、山口県下松(くだまつ)市の住宅街にクマが現れ、民家に逃げ込んで殺処分されたというニュースが流れました。
5/21 毎日新聞デジタル:https://mainichi.jp/articles/20180522/k00/00m/040/162000c
この件に対して、熊森山口県支部長が県の自然保護課に駆けつけ、担当者と直接お話をしました。
熊森山口県支部長が県の担当者に訴えた内容
①、今回のクマは、人間に対して何の危害も加えていません。本当に殺処分されなくてはならなかったのか疑問です。今回行政がとるべき対応は、捕獲したクマは放獣すべきだったし、今後も同様のことが発生したらクマを山に返してあげてほしいです。
②、山口県のクマ生息地は山奥まで野生動物の食糧にならないスギやヒノキの人工林でいっぱいです。クマが人里に出てくるのが困ると言ってもクマの生息地にクマが生息できる環境がありません。
どうか、奥山のスギやヒノキの人工林を広葉樹林に戻していってほしいです。生息地がなければ、クマは山では生きてはいけません。
熊森本部から
熊森本部も山口県の担当者に電話で問い合わせました。下松市で捕獲されたクマは、体長115cm、オス、2-3歳くらいの若いクマだったそうです。
経験のない若グマが、山から降りてきて、車や人間に恐怖心を抱きながら逃げまわっていたと思います。たまたま逃げ込んだ先が家の縁側だったというだけで、何も人間を襲ってやろうなんて気はなかったはずです。
日本は、行政が生き物の命を大切にしないおかしな国になってきたと思います。
この行き着く先は、自然破壊の拡大と人間社会の崩壊です。
熊森は、どこまでも生き物の命を大切にする国をめざして声を挙げ続けていきます。
殺さなくても良い命を奪うことは犯罪です。
仙台市倉庫にいたクマ、麻酔銃で捕獲して檻に入れた後、射殺 なぜ放獣しなかったのか 熊森が抗議
6月6日、仙台市の日本郵政の倉庫内に1頭のクマが入り込み、麻酔銃で捕獲された後、殺処分されました。
熊森本部は、仙台市の担当者に、なぜ放獣できなかったのか、電話で聞き取りました。
担当者は、人身事故の危険性が高かったためにやむ終えなかったと答えました。
しかし、
クマは麻酔銃を向けても無抵抗で、人間に牙や爪を向けたりしなかった。
体長117cmで体重が36㎏しかない小柄なクマだった。
ということです。
このことを知った宮城県のクマ生息地に住む熊森会員が、「麻酔をかけられ眠っているクマに銃を向けるなど許せない」として、すぐに、仙台市の担当者へ電話を入れてくれました。
宮城県の熊森会員が仙台市に訴えた内容
●麻酔をかけて捕獲をしたところまでは、良い。しかし、その後なぜ殺処分なのか。
●仙台市内でも奥羽山脈の山奥へ行けば、まだ豊かな森が残っていてクマたちが棲んでいる。近くには民家もないし、簡単に放獣できるではないか。
●どうしても放獣ができないと言うのなら、捕まえたクマを仙台市で飼ってほしい。毎日食べものを与えて、掃除などの世話をしてみたら、クマを容易に殺処分することなんてできなくなるはずだ。
市の担当者は本部が電話をした時には謝りませんでしたが、この会員には、「命を奪ってしまって申し訳なかった」と言われたそうです。
地元の会員が、クマの命も大切にしなければならないという声を行政に届けてくださった効果は大きいと思います。
仙台市には、今回のクマ捕殺の件で、どうして助けてやれなかったのかという声が多く届いているそうです。
声を届けてくださったみなさん、ありがとうございます。
利尻島のヒグマ「そっとしておいてほしい」北海道庁にくまもりが要望書提出。
6月7日付けの朝日新聞デジタルに、利尻島のヒグマの今後の対応について、捕獲も検討という記事が載り、熊森はあせりました。ヒグマ放獣体制が全くない北海道では、捕獲後は100%射殺するからです。
朝日新聞デジタル(6月7日)https://www.asahi.com/articles/ASL6635W6L66IIPE003.html
熊森本部はすぐに北海道稚内総合振興局と利尻富士町の担当者に電話をしましたが、会議中ということで出られませんでした。
利尻富士町役場で利尻のヒグマ対策会議が開かれ、道(宗谷振興局)、利尻富士町、利尻町、環境省稚内自然保護官事務所、稚内警察署、宗谷森林管理署の6者で話し合いが行われていたのです。
熊森本部は、このクマが捕獲(=駆除)されないよう、北海道のヒグマ研究の第一人者である門崎允昭先生(北海道野生動物研究所所長、日本熊森協会顧問)に電話をし、先生の見解を聞いてみました。
先生は、捕獲や駆除はすべきではなく、調査のためにドローンなどを使ってクマを追いかけることも避けるべきで、静かに見守るべきということで、私たちと同じ見解でした。
さっそく、熊森本部から北海道の高橋はるみ知事あてに要望書を提出しました。
この日の利尻ヒグマ対策会議では、
「クマの捕獲や駆除はせず、引き続き島民や観光客にむけて警察・町・環境省でクマの注意喚起をしていく」
ということが決まったそうです。マスコミに、捕獲を考えているなど言ったことはこれまでないということでした。
道や町は、自動撮影カメラを設置し、このクマの姿をとらえようとしています。
利尻富士町役場には、このヒグマを捕獲したり駆除したりしないでほしいという声が多数寄せられているということでした。
声を届けてくださった皆様、ありがとうございます。
熊森本部は、今後も、利尻島のヒグマがどうなるか注目していきます。
徳島県天神丸風力発電の白紙撤回を その6 徳島大学鎌田 磨人教授のFacebookの情報から
鎌田先生のフェイスブックに、徳島県天神丸風力発電関連の情報が続々と掲載されています。
とても参考になります。鎌田先生、ありがとうございます。
以下鎌田先生のフェイスブックから
5月24日
(仮称)天神丸風力発電事業に係る「計画段階環境配慮書」に対する知事意見が出ました。あわせて、「徳島県環境影響評価審査会の答申」も掲載されています。
「次の各論に示す指摘事項について,追加書類を速やかに提出することなど 検討することが望ましい。また,あらゆる措置を講じてもなお,重大な影響を回避又は低減できない場合は, 本事業の取り止めも含めた計画の抜本的な見直しを行うこと」との文言が書き込まれたのは素晴らしいと思います。審査会委員の皆さんのがんばりの賜物かと思います。ご苦労様でした。
以下、鎌田メモ。
(1)答申では、「本事業計画で発電機の設置計画区域から周辺1キロメートル 範囲に影響が及ぶと想定した場合,徳島県及び高知県に連なる四国東部域の自 然度7以上の冷温帯林の約7パーセントが消失並びに影響を受けると予測され ることから,希少生物・生態系への影響は甚大であると推定される」との文言が残っている。
(2)しかし、「5km、10km、15kmを閾値として、四国東部の冷温帯域に設置された鳥獣保護区(特別保護区を含む)への影響を検討したところ、本事業計画での発電機設置計画区域から5km以内には冷温帯域鳥獣保護区の20%(特別保護区の9%)、10km以内には51%(特別保護区の43%)、15km以内には71%(特別保護区の56%)が含まれることとなり、影響は深刻である。これは、これまで徳島県や地域が築き上げてきた保護政策を無視した開発行為だと言わざるを得ない。設置場所や配置については速やかに代替案を作成し、風車から5~15km圏域に鳥獣保護区等が内包されない配置を検討すべき」等、重要な指摘は削り落とされていた。
(3)また、「環境省による「平成 27 年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書」によれば、計画区域は開発不可条件に該当する地域となっており、陸上風力の導入ポテンシャル評価は著しく低い。 本来的に風力発電の導入に不適切だとされる地域で行おうとする事業の公益性について、合理的な説明 資料の追加提出が必要である。鳴門市が実施している「鳴門市における陸上風力のゾーニング(適地評 価)」等を参照して、関連する付帯工事も含めて、立地適正を客観的に判断できる資料を作成し、速やか に提出することを求める」との意見も重要だと思っていたが、ここも削り取られていた。
(4)そして、これら意見、知事意見では全てなくなってたのは残念。
5月27日
知事意見提出についての、徳島新聞(5/25)と朝日新聞(5/26)の記事
5月31日
6月1日
「風力発電は広がるか?」5月16日放映されたNHK徳島放送の特集動画。
今後も、鎌田先生のフェイスブックを、読ませていただきたいです。
徳島県天神丸風力発電の白紙撤回を その5 熊森の意見書提出とオリックス社の反応
遅ればせながら、熊森は5月24日、天神丸風力発電計画の白紙撤回を求める意見書をオリックス社へ、また、計画を認めないでほしいという要望書を、飯泉嘉門徳島県知事と中川雅治環境大臣に提出しました。
こんなに遅くなったのは、徳島県には熊森の支部がないため計画を知ったのが遅く、知ってからも責任ある意見書を書くために、一から調べねばならないことがあまりにも多かったからです。
提出後、知ったのですが、天神丸風力発電事業に係る「計画段階環境配慮書」に対する徳島県知事の意見が、5月24日、発表されていました。
意見書や要望書の提出が遅くなって申し訳ないのですが、熊森は、徳島県に住む人々のためにも、徳島県で生きる動植物のためにも、天神丸風力発電計画は100%白紙撤回すべきであると断言していますので、提出先のみなさんには、ぜひ読んでいただきたいです。
熊森の意見書 (ダブルクリックして拡大していただくと読めます)
オリックス社の担当者に電話をしてみました。
熊森:徳島県知事の「本事業の取り止めも含めた計画の抜本的な見直しを行うこと」という意見書が出ましたね。先日、知事が反対したら、この計画は進められませんと言われておられましたから、もうこの計画はなくなったと考えていいですか。
オリックス社:まだどうするか決まっておりません。
熊森:(あれっ?中止じゃないのかな。この前と返答が違う)いつごろ結論が出るのですか?
オリックス社:まだ決まっておりません。
熊森:県外者なんですが、結論が出たらぜひ知りたいです。どういう方法で発表されるのですか?
オリックス社:まだ決まっておりません。
(熊森から)オリックス社の担当者の返答は、取りつく島もないという感じでした。オリックス社がこの計画を断念されるよう、全国から声を届けていく必要があると感じました。
<白紙撤回訴え先>
オリックス株式会社 代表取締役 井上 亮 様
〒105-0023
東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル
電話03-5730-0184 天神丸風力発電事業係 担当者:明治、長谷
同じ国民として、リニア工事に泣く沿線住民を見捨てられない 熊森岐阜がリニアルートを視察
5月20日、日本熊森協会岐阜県支部員23名と本部リニア担当者1名は、岐阜県におけるリニアルートの3か所を視察しました。
地元の「リニアを考える会」のメンバーのみなさんが説明をしてくださいました。
①瑞浪市日吉町:残土置き場が崩れたら下の集落に危険が!
まず、初めに訪れたのは、リニアのトンネルが掘られようとしており、すでに残土置き場が造られている瑞浪市日吉町です。
ここでは、リニアによって地元住民が得るものは何もありません。
リニアに賛成している人は誰もいないということでした。
リニアのトンネルを掘った時に出て来る残土を運ぶための、ベルトコンベアーがすでに設置されていました。
棚田が広がっていた広大な谷が、残土置き場になっていました。
この谷を、残土が埋め尽くすことになるのです。
すぐ下には、集落があります。豪雨などで残土置き場が崩れたら、集落のみなさんの生命に危険が及びます。
工事開始が差し迫っており、騒音、排気ガス、電磁波など自分たちの身に降りかかってくる危険をどう回避するかで地元は必死でした。
②中津川市:駅舎の日陰で、米作りが不可能に
中津川市では、岐阜県駅と非常口予定地を視察しました。
道の両側に田畑が広がり、交通量も人通りもそれほどない、静かな場所でした。
田植えを終えたばかりの田んぼが広がっていました。
ここに30メートルほどの高さの駅ができます。
田畑は駅舎で日陰になってしまいます。
もう米作りはできません。
市が買い取って田畑を駐車場などにするそうです。
中津川市の山口非常口建設予定地では、すぐ上に、人家がありました。
ここにトンネルを掘ることによって、この人家はどうなるのか不安を感じました。
③恵那市:電磁波と騒音が不安な住民たち
最後に恵那市岡瀬沢地区を訪れました。
この地域では、JR東海に対して地上部リニア走行部分にフードを取り付けてくれるように要望していますが、JR東海は首を縦に振ってくれないということでした。
理由はわかりませんが、地上部全てにフードを付けるとなると、建設コストが莫大になるからだろうと住民の人達が言っていました。
家の数メートル上を、大量の電磁波を放出し、かなり大きな騒音を出してリニアが走るのです。
住民たちは、フードをつける約束をしてくれるまでは、断固として中心線測量をさせないとがんばっておられました。
熊森から
岐阜県リニアルート視察に参加して、大企業であるJR東海の利益の為に、何の罪もない住民たちの生活が奪われようとしている現実を目の当たりにしました。
すでにリニアのトンネル掘りが始まっている長野県の大鹿村では、発破のために家にひびが入ったり、裏山が崩れてきたりしているそうです。
2001年に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」によって、地下40メートルより深い土地は、無許可で使用できることになりました。リニア中央新幹線はこれを利用して、地下水脈を次々とぶっちぎってトンネル工事を進めているのです。取り返しのつかない国土大破壊工事です。
リニアルートの沿線では、多くの一般住民がどうやって声をあげればいいのかもわからず、不安を感じながら生活しています。
リニア建設は、弱い者いじめ以外の何ものでもないと思いました。
今、たまたま外部の安全圏にいる私たちこそが、不安におびえている住民の方たちを見捨てず、「リニア工事中止・JR東海は住民の声を聞け」の大声をあげることが必要だと感じました。
多くの国民は、リニア工事に泣く住民の実態を知りません。
マスコミの皆さん、なんとかがんばって報道してください!
ヒグマが生存しない利尻島でヒグマの足跡発見、地元行政は、今は、捕獲や駆除は考えていない
5月31日、利尻島利尻富士町でヒグマの足跡が発見されました。
【5月31日、産経新聞デジタル】
https://www.sankei.com/affairs/news/180531/afr1805310026-n1.html
北海道本土から20km海を隔てた利尻島まで、ヒグマが泳いで行ったのでしょうか。
このヒグマはこのあとどうなるのでしょうか。
熊森本部は、さっそく利尻島行政(利尻町、利尻富士町)に電話をしました。
<利尻富士町の担当者>
砂浜にあった足跡の写真を北海道総合研究機構に送って鑑定してもらったところ、ヒグマであるという結果が来ました。
しかし、はっきりとした実体は確認されていません。
島民の皆さんは、普段の生活でクマを見たことがないので、驚いています。
今は、人が生活する圏内を警察とパトロールしています。
学校は、集団下校をしています。
今のところ捕獲や駆除は検討していませんが、住宅地に頻繁に出てくることがあれば状況は変わるかもしれません。
私たちもむやみに駆除をしようとは考えてません。
このまま、本土に帰ってもらうか、深い山の中でひっそりと暮らしてほしいです。
<利尻町の担当者>
今から106年前の明治時代にも利尻島にヒグマがやってきた記録があります。
その時は北海道本土で森林火災が多発しており、海を泳いで逃げてきたと言われています。
この時は、駆除されました。
利尻島にはミズナラの豊かな森があるので、このヒグマの食料はあると思います。
今回クマが出たのは利尻富士町ですが、利尻町でも注意喚起をしています。
熊森から
利尻島は北海道内でも随一の豊かな自然環境が残された島です。
本部スタッフも行ったことがありますが、クマが棲んでいても不思議ではありません。
両町では現在、生ごみは家の外に長時間置かないよう、ゴミの収集日に出すことを徹底しているようです。
島内ではクマ鈴が急に売れているようです。
【6月1日 北海道文化放送UHB】
https://www.fnn.jp/posts/2018060100000007UHB
島民や観光客の皆さんがヒグマと出会わないように注意していただければ、ヒグマとの事故を防ぐことができます。
利尻島行政には、ヒグマがまだ島内にいても、泳いで本土へ戻ろうとしても、そっと見守ってくださるよう伝えました。
熊森は、今後も動向を追っていきます。
【連絡先】
利尻富士町役場 総務課 TEL:0163‐82‐1112
お問合せフォーム:https://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/1175.htm
10年間連続 駒澤大学高等学校新入生520人にくまもり講演
今年も5月30日1時限目にくまもりが講演させていただきました。
東京と言っても、学校のある世田谷区は緑あふれる住宅地です。
家々の花壇に花があふれていました。
学校の玄関の菩提樹の大きな木も、ちょうど花盛り。
いい香りを漂わせていました。
この学校は毎年夏に1年生を長野県の提携している山村集落に連れて行って、森について学ばせておられます。
2年生は平和学習に取り組まれるのだそうです。
どちらも高校生にとって大切な勉強で、このようなカリキュラムを組まれている先生方に敬意を表します。
講演する森山名誉会長
会長の日程の都合がつかなかったので、今年は名誉会長の講演となりました。
くまもり講演を聞く駒澤大学高校生
講演の後、毎年、全生徒の感想文が送られてきます。
人間として大切な、まじめさや真剣さ、やさしさを失っていないすばらしい生徒たちです。
銃の前には絶対弱者とならざるを得ない他生物のことも考える優しい文明だけが、自然を守って生き残るという趣旨のお話をさせていただきました。
どれくらい伝わったでしょうか。
感想文が届くのが楽しみです。
三重県いなべ市でイノシシ用くくり罠にクマがかかる 山に放獣する予定
|
以下、中日新聞2018,5,30より いなべでイノシシ罠にツキノワグマ 猟友会員ら捕獲
三重県は5月29日、いなべ市北勢町川原の山林に仕掛けたイノシシ用のくくりわなに雄の成獣のツキノワグマがかかったため、麻酔で眠らせて捕獲した。近日中に市内の人家から2キロ以上離れた場所に放す。 県獣害対策課や県猟友会いなべ支部によると、同日午前6時ごろ、わなにクマがかかっているのを見回り中の会員が発見。体長1.4メートル、体重94キロ。10歳を超えているという。県職員らがクマ用のおりに移し、市藤原庁舎で保管した。 市内では、2015年5月にも北勢町二之瀬でクマが捕獲されている。ツキノワグマは県の希少生物として、捕獲した場合、自然に戻すと決められている。クマに電波発信機を着けて、放獣後は1週間ほど行動を監視する。
(熊森より) 2015年のいなべ市でのクマ騒動を思い出します。 熊森本部も、あの時は、いなべのクマを救うため、若いスタッフたちを中心に、午前2時に起きていなべ市にみんなで駆けつけたものです。 もう当時と行政担当者も変わっているかも知れませんが、あの時言われていたように、きちんと保護して放獣して下さるということで、三重県といなべ市に感謝です。
旧式の一生外れない発信機を装着するということは、クマに生涯拷問を掛け続けることになりますが、三重県は熊森の要請で、当時、自動落下できる外国製の高い発信機付首輪を購入してくださいましたから、それを使われるのだと思います。
どんな生き物の問題であっても、殺さない解決法が一番優れているのです。文化の高さを表します。
故東大林学科名誉教授高橋延清先生は、日本の森はクマがいないと森にならないと言われていました。
全ての生き物(クマもその中に入ります)がそろった本当の森を、子や孫に残していくことは、私たち大人の責任です。
|
徳島県天神丸風力発電の白紙撤回を その4 5月24日徳島県知事が建設回避を求める意見書提出
徳島新聞 5月25日 より
オリックス風力発電計画 徳島県知事 回避を求める意見書提出
徳島県の飯泉嘉門知事は24日、オリックスグループ(東京)が美馬、神山、那賀3市町の境付近に計画している風力発電事業の計画段階環境配慮書に対する意見書をオリックスに提出した。想定区域周辺の希少動植物や景観などへの影響に懸念を示し、重大な影響を回避できない場合には事業中止や抜本的な計画の見直しを行うよう求めた。
意見書では、配慮書に生態系などへの影響について科学的根拠が示されていない点を指摘し、追加書類を速やかに提出することも促している。また、希少動植物、景観に与える影響や土砂災害リスクの増大、登山者への影響といった課題ごとに専門家の助言を踏まえた適切な調査と影響の回避、低減を求めている。
知事意見は、河川生態学や景観工学などの有識者でつくる県環境影響評価審査会がオリックスの計画段階環境配慮書に対してまとめた答申をほぼ踏襲する内容となった。答申では、配慮書手続きのやり直しを検討するよう求められたが、環境影響評価法に規定がないことを理由に削除した。
計画段階環境配慮書は計画の立案段階での事業概要や環境への影響を記したもので、配慮書の作成は法に基づく環境アセスメント手続きの一環。県は同日、許認可権がある経済産業省のほか、環境省にも意見書を送付した。
オリックスは知事や経産相、住民の意見を踏まえ、アセスメントの実施計画に当たる方法書の作成手続きに入ることになるが、同社広報部は「知事や住民、経産相の意見を踏まえた上で、方法書段階に進むかどうか検討したい」としている。
計画では、3市町の境にある天神丸と高城山の2990ヘクタールに最大42基、総出力14万4900キロワットの風力発電施設を設ける。2023年10月に着工し、26年秋の営業運転開始を目指している。
県要望ハードル高く、事業の行方は不透明に
オリックスグループが計画する風力発電事業の計画段階環境配慮書に対し、飯泉嘉門知事が出した意見書は、現地の自然環境への重大な影響などを回避できない際の事業中止や抜本的な見直しを迫る厳しい内容となった。
具体的には▽動物の移動経路の分断やえさ場の減少▽渡り鳥の経路阻害や衝突事故▽登山など人と自然とのふれあい活動への影響▽土砂災害リスクの増大-といった懸案を列挙。それぞれに改善を求めている。
県は「脱炭素」を目標に掲げ、再生可能エネルギーの普及拡大を目指している。その県が今回の風力発電所の建設に対し、こうした強い姿勢を示すのは、見過ごせないほど、環境への影響が大きいと判断したためだ。
計画段階での「配慮書」の手続きは、環境保全について早くから検討を始めるとともに、国や県、地元住民らの意見を聞く機会を増やすため2011年の環境影響評価法改正で盛り込まれた。
オリックスは今後事業を進める場合、アセスメントの実施計画に当たる方法書の作成手続きに入るが、県が課したハードルは高く、同社は事業が環境に与える影響をいま一度見つめ直さざるを得ない。今後の事業の行方は不透明になったといえる。
(熊森から)
徳島県飯泉嘉門知事、徳島県環境影響評価審査会の委員、反対の声を上げてくださったいくつもの自然保護団体や県民のみなさま、本当にありがとうございます。いくら何でも、徳島の最高の自然が残されている場所に42基の巨大風車建設はひどすぎましたね。まだ気を緩められませんが、とりあえずほっとしました。
それにしても、さすが、徳島県の県土を守ろうと、細川内ダムや吉野川第十堰可動化を白紙撤回させた徳島県のみなさん。みなさんは、声を上げる力をお持ちで、素晴らしいと思いました。敬服します。日本も捨てたもんじゃない。まだまだ破滅型開発を止める力は残っていたと思うと元気をもらいました。
オリックス社の今後の動きに注目していきたいと思います。山の尾根筋に風車を建てる時代は、環境への取り返しのつかない負荷や効率の悪さを思うと、もう過去のものとなった感がします。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ