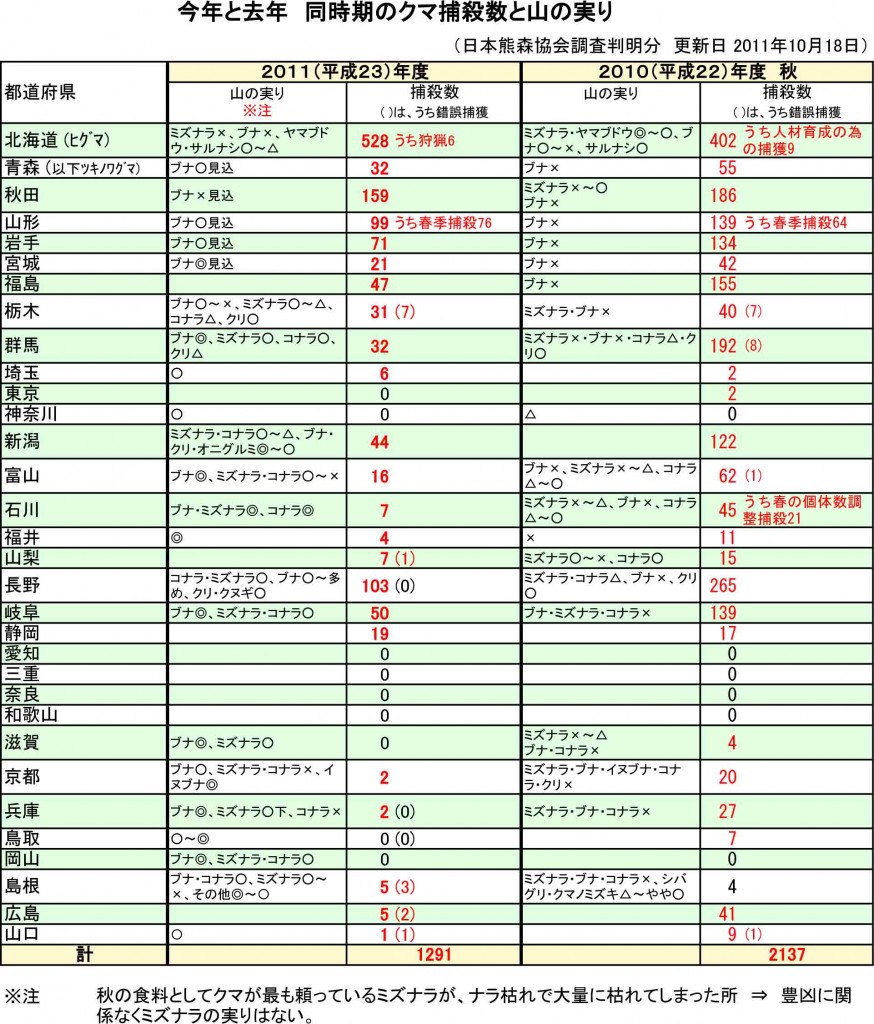ホーム > _野生動物保全
カテゴリー「_野生動物保全」の記事一覧
日本では、農薬ネオニコチノイドの規制なし (農林水産省農薬対策室)
農水省の担当部署に、電話しました。
くまもり「ネオニコチノイドは、日本でよく使われているのですか」
農薬対策室係官「カメムシやウンカ、ツマグロヨコバイを殺すために、農薬のネオニコチノイドは大変効果があり、田んぼなどでよく使われています」
くまもり「ハチが消えて、果樹園が困っておられますが」
農薬対策室係官「ハチが消えたこととの関連は、まだよくわかっておりません。ダニやウィルスによってハチが消えたという説もあり、現在調査中です」
くまもり「疑わしきは規制となりませんか。ヨーロッパでは使用禁止だそうですが」
農薬対策室係官「まだ結論は出ておりませんので、使用禁止にはしません」
くまもり「戦後、松枯れ対策に、膨大な薬剤の空中散布が行われてきましたが、山の中のいろんな虫たちを大量に殺しただけで、松枯れは止まっておりません。農薬会社が潤っただけです。疑いが起きた時点で、すぐに止められないのでしょうか。いまだに山に松枯れ対策として薬剤を空中散布していますよ」
農薬対策室係官「そちらの方は、林野庁の担当ですので」
くまもり「ありがとうございました」
シカは本当に森を食い尽くす害獣なのか、シカ問題の究明にヒント? 馬毛ジカの窮状
- 2012-03-30 (金)
- _野生動物保全
<馬毛島の位置と大きさ、歴史>
日本で2番目に大きな無人島である鹿児島県馬毛島は、種子島の西11キロメートルにある面積約8㎢の島である。
リゾート開発全盛期に、海洋リゾートを名目に大半が買収されたのち、1999年はじめより核燃料中間貯蔵施設の話が持ち上がる。2000年には買収企業である(株)馬毛島開発 の採石事業を鹿児島県知事が認可して、ダイナマイトを使った大規模 な掘削が行われた。2009年には、鳩山内閣時、普天間移設候補地になり、所有者は2本の滑走路を作り、島のレンタルを国に申し出るが、話が進まなかった。現在、2011年5月15日、防衛省が馬毛島で米空母艦載機の陸上離着陸訓練(FCLP)を実施する方向で最終調整に入っているが、地元の首長らは、断固反対の意思を表明している。
この島に昔から住み続けてきた馬毛ジカは、人間に生息地を破壊され、生きられなくなって生態に変化が出ているもよう。日本ジカが、今、各地で起こしている生態変化を解くカギがここにあるような気がする。
以下は、朝日新聞夕刊 2011年10月4日より転載させていただいたものです。
進む伐採 固有のシカ半減 馬毛島[2] 失われゆくもの

固有亜種のマゲシカは、開発が進んだこの10年間に半減した=7月4日、鹿児島県・馬毛島、本社ヘリから、溝脇正撮影
馬毛島には野生のシカがいる。ニホンジカより黒っぽく、体が一回り小さい固有亜種マゲシカだ。奈良時代に皮を年貢に納めた記録があり、千年以上も独自の集団を保ってきたらしい。島の最高点の岳之腰(71メートル)から、なだらかに広がる森林と草原に暮らす。
その生息地が今、十字形の「滑走路」工事で無残な姿をさらしている。7月に本社ヘリで上空を飛んだ。
ブルドーザーやショベルカー、ダンプカーなど十数台が土地を削り、土砂を運んでいた。マゲシカは、まだ開発が及んでいない南部の草原地帯に集まってい る。草は深く食べられ、土が透けて見えるぽど短い。「森が減って餌が不足し、シカと植物のバランスが崩れている。このままでは近い将来、餌不足がひどくな る」。ヘリに同乗した北海道大助教の立澤史郎さん(51)がため息をついた。
保全生態学者の立澤さんがマゲシカの調査を始めたのは1987年。手弁当で3ヵ月ごとに漁船で島に渡り、廃校になった校舎跡に泊まり込んで個体数を配録 した。人間も天敵もいない孤立した環境。増えすぎると栄養状態が悪化して個体数が誠り、減りすぎると、また増える。自然の調節メカニズムが働いていた。
2000年8月の推定生息数は過去最高の約570 頭。その後、上陸調査は行われていない。土地を買い集め、開発に乗り出した馬毛島開発(現タストン・エアポート)が、島内への立ち入りを許さないからだ。
この10年で島の森林は約125ヘクタールが伐採され、半減した。工事の影響で元の植生が失われた土地は、島の半分近い約360ヘクタールに及ぶ。本社 ヘリを利用した今年7月の調査では、マゲシカの推定数は約280頭と半減した。生息環境が悪化し、個体数の回復は望めない。植生の復元など保全策をとらな ければ、絶滅の恐れが高まると見られる。
マゲシカだけではない。メダカやドジョウが暮らし、シイ類やタブノキの照葉樹林が茂った「椎ノ木谷」も、ほとんどが跡形なく埋め立てられた。葉が細く草丈40センチほどの固有種ホソバアリノトウクサが50年代に見つかった場所も、工事で表土がはがされた。
馬毛島に生息する動植物は、公的な調査がほとんど行われていない。立澤さんは憤る。「実態が分からないまま、なし崩しに破壊していいのか。どんな開発をするにせよ、まず専門家による詳しい現状調査を行うべきだ」(安田朋起)
3月27日、被害防止のために捕獲した鳥獣の食品利用や流通の促進が新たに法制化
参議院先議法案として、今国会の参議院農水委員会に提出されていた、野生鳥獣の捕殺を推進するための自民党法案が、多くの反対にあい撤回された。しかしその後、参議院農水委員長(小川勝也参議院議員)案として、鳥獣被害防止特措法の改正(改悪)案が出され、全会一致で、3月23日に参議院で可決、3月27日に衆議院で可決されました。
鳥獣被害防止特措法の主な改正(改悪)内容
(改正前)
第十条 国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣が適正に処理されるよう、当該対象鳥獣に関し、処理するための施設の充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、有効な利用方法の開発その他の必要な措置を講ずるものとする。
⇒赤字部分が改正後
第十条 国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣が適正な処理及び食品としての利用等その有効な利用を図るため、必要な施設の整備充実及び食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
<熊森の見解> 飽食日本では、スーパーに行けば、どう考えても食べきれないまでの食品が、世界中また全国から集められ、山のように積み上げられています。年間に廃棄処分されている食品は大変な量です。そんな中で、野生ジカを食べる文化を作ろうと動きに動いている人たちがいて、行政とつながっていっています。人間は、野生鳥獣を殺すこと、食べることばかり考えていていいのでしょうか。シカ問題を、シカを殺さずに解決しようという動きがこの国の行政にほとんど見られないことを悲しく思います。
命はどんな生き物にとってもひとつしかない大切なものです。熊森は可能な限り、殺生をしない国をめざしています。
3月22日 自民党が国会に提出していた、野生鳥獣捕殺をいっそう強化するための改正法案を撤回
クマもイノシシも、兵庫県内に何頭いるのかわからないというのが現実
- 2012-03-28 (水)
- _野生動物保全
3月12日、兵庫県庁近くの労働センターで、第2回野生動物保護管理審議会が開かれました。傍聴席10席のうち、8席が埋まりました。相変わらず、メディアはどこも来ていませんでした。
県が、前回のツキノワグマの推定生息数や増加率を訂正発表すると、委員である研究者たちから、
「クマは生息推定数を出す手法が確立していないので、推定はむずかしいのではないか」という、鋭い意見が相次ぎました。
2012年1月兵庫県発表 クマの年間推定増加率 14%~30%
⇒ 今回3月の訂正 5.7%~15.0%
2012年1月兵庫県発表 クマの推定生息数 313頭~1651頭
⇒ 今回3月の訂正 300頭~751頭
今回の訂正数が正しいかどうか、それすら人間にはだれもわかりません。人間が自然を把握しきることなどできません。
しかし、絶滅危惧種にもかかわらず、捕獲後原則殺処分の県方針は前回のままで、訂正されませんでした。???
イノシシに至っては、何頭いるのかさっぱりわからず、生息数を推定することすら不可能ということで、行政、審議会委員、研究者、全員の意見一致がありました。しかし、シカ、サル、クマ同様、捕殺する話ばかりでした。
また、兵庫県が県民緑税を使って行っている野生動物育成林事業は、ほとんどが山裾の樹木を刈りはらうバッファゾーン造りであり、いっそう動物が棲めないようにしているだけだと、ある研究者委員が指摘されていました。
戦後、人間が壊した野生動物たちの生息地の広大さを思うと、人として、一刻も早く動物の帰れる森を復元してやるべきだと思いました。全生物のためにも、地元の人のためにも。
兵庫県行政のみなさん、地元との話し合いなど、いろいろとむずかしいこともあるでしょうが、何とぞよろしくお願いします。
兵庫県が強行に進めているシカ肉学校給食に疑問
- 2012-03-05 (月)
- _野生動物保全
害獣有効活用 児童ら「おいしい」
有害鳥獣として捕獲された鹿を有効活用しようと、宍粟市一宮、千種両町の10小中学校の学校給食で16日、鹿肉を使った「ジビエ料理」が出された。17、23日には山崎、波賀両町の小中学校でも提供される。 (2012年2月17日読売新聞より)
<熊森が指摘する問題点>私たちが何を食べて生きていくのかは、大変デリケートな問題です。これまで日本人が食べてこなかったシカを学校給食に出すということは、シカを食べたくない児童に選択権を与えないことになります。シカを食べることに抵抗感を持つ児童にとっては、シカが給食に出されることは、シカ食を強要されたも同然で、人権問題です。メディアが何の疑問も持たずに、このような記事を載せる軽さに、日本の報道の危うさを感じます。おいしい、栄養がある、ジビエという横文字がかっこいい・・・なら、何を食べてもいいのかということになります。裏で誰かがこのような食文化づくりを進めているのです。
戦後、アメリカは、アメリカの牛肉や農産物を日本が輸入するように仕向けるため、新しい栄養学や肉食の勧めなど、すさまじいプロパガンダを展開しました。その結果、魚食だった日本人が、どんどん肉食に変わっていったのです。
本来、日本文化は、仏教の殺生禁止の教えを強く受けています。このことによって、クマを初めとする大型野生動物の棲む豊かな森が残され、今日の繁栄があるのです。
日本人が大量に肉食することで、世界の森の消えていくスピードが速まっています。生き物へのやさしさも、どんどん失われていっています。健康面でも肉食過多の弊害が叫ばれています。
こんな中で、誰がどのような意図で、シカ肉食を進めているのか。シカは豊かな自然界を作ってきた生き物です。元々、害獣なんかではありません。この問題について、もっと、慎重な議論が必要です。
10/30 閉園された札幌定山渓クマ牧場を会長が訪問
当協会森山会長は、札幌での集会を前に、10月29日夜北海道入りし、バスで定山渓に向かい、定山渓グランドホテルに宿泊しました。
このホテルがかつて経営していた定山渓クマ牧場は2004年閉園されています。しかし、今もヒグマたちが、深いコンクリートプールのような獣舎に13頭取り残されており、今年夏のニュースによると、食事もきちんと与えられず、ひどい扱いを受けているということです。
くまもり本部には、このヒグマたちを何とか助けてやれないかという声が、会員からいくつも届きました。胸を痛めた本部は、今も、このヒグマたちの飼育責任者である定山渓グランドホテルに電話をして、何かわたしたち市民団体に手助けできることはないかさぐろうとしました。しかし、何回電話をしても、ホテル側は、責任者は今いませんと逃げ続けるだけでした。
今回、ホテルに宿泊して、ホテルから車で5分のところにあるというクマ牧場を見せていただき、保護団体として何か飼育支援できないか、責任者の方と話し合おうと思いました。クマ飼育に関わっているのはひとりだけで、ホテルの総支配人の仕事だそうです。ロビーの方にたずねると、総支配人は、明日の朝9時ごろ出勤されるという事です。
朝、朝食会場に行くと、ホテルは大勢の宿泊客でいっぱいで、食事はおいしく食べ放題でした。この残りをクマ牧場のヒグマにやっていただけないものだろうかと思いました。朝9時にホテルロビーに出向いて、総支配人に会おうとしたのですが、札幌で会議があるため、本日は出勤しないと言われてしまいました。何とかクマ牧場を見るだけでも見て帰りたいと思いましたが、他にヒグマ飼育に関わっている人はおらず、クマ牧場に案内できる人も、ホテル従業員の中にひとりもいないのだそうです。

仕方なく、タクシーに乗って前まで行ってみましたが、門が閉まっており入れませんでした。中は全く見えず、辺り一面静まり返って何の音も聞こえませんでした。周辺の建物は朽ち果ててつぶれそうになっていました。先ほどまでいたホテルの華やかさと対照的でした。今日のクマたちの食事は与えられるのだろうかと、心配になりました。

何とか、北海道にくまもり支部を作って、地元会員のみなさんで動いてもらうようにしたいと思いました。
タクシーの運転手さんに、北海道では今年すでに585頭のヒグマが殺されている(道庁へのくまもり聞き取りより)という話をしたところ、「北海道民は誰も知らないよ」と、驚かれていました。道民は、毎年1~2頭、ヒグマが殺されているという感覚しかないそうです。マスコミが知らせない限り、誰もわからない。保護の声も何も起きないということです。
<定山渓クマ牧場メモ>
1969年設立 ヒグマ 35頭
1997年 ヒグマ 100頭
2004年閉園
2007年 ヒグマ 26頭
2011年 ヒグマ 13頭(オス4頭、メス9頭)
10月27日 兵庫県野生動物保護管理運営協議会への委員出席と傍聴 兵庫県は、クマに個体数調整を導入しないことに
兵庫県県民会館で午後1時30分から5時まで、兵庫県野生動物保護管理運営協議会が開かれました。
議題:①第11次鳥獣保護事業計画案(平成24年~29年まで)について
②クマ・サル・シカ・イノシシ各保護管理計画案案について(平成24年~)
膨大な資料が配布され、紙の厚さが約2センチでした。森山会長は、朝から3時間半かけたが読み切れなかったと言っていました。行政のみなさんの大変な御苦労を思うとともに、個々の動物についてここまで文書化する意味があるのだろうかという疑問も持ちました。尚、この会議の後は、審議会やパブリックコメントを経て、案が最終決定されていくそうです。
何人かの熊森スタッフが、傍聴を願い出ましたが、傍聴するには開始30分前に申し込んで、開会後30分後に入室なので、室外の待機時間が約1時間となります。次回から、もう少し待ち時間を短くして頂けたらありがたいのですが。また、会議は図表やグラフが話題になりますが、傍聴者には資料がもらえないので、議論の中身が分かりにくかったです。簡単でもいいので、傍聴者にも資料配布をお願いしたいです。メディアの傍聴は、残念ながら今回もありませんでした。森山会長が冒頭に、県民の税金でやっている会なので、会議の内容を以前のように文字化して県民が読めるようにしてほしいなどと3点の要望を行いました。文字化していただけることになったので、それを見て、詳しく意見を述べたいです。
また、これだけの膨大な内容ですので、3時間の会議では質問すら十分にできませんでした。残された質問は、今後、文書等で行いたいと思います。
尚、当協会が、鳥取県に次いで導入されないかと危惧していた、絶滅危惧種クマへの個体数調整捕殺は、兵庫県案では行わないとなっていました。兵庫県行政に感謝です。
10月22日 クマの体に触れないクマ調査法研修会(本部)
本部クマ部会のメンバーを中心に、本部近くの西田公園会議室に25名のスタッフたちが集まり、クマ研究者から、クマの体に負担をかけないクマ調査法を熱心に学びました。
 野生動物を保護するためには、本来、生息推定数や適正生息数など必要ありません。私たちの祖先は、そんなことは誰も知りませんでした。しかし、広大な生息地を保証することによって、見事にかれらを守りかれらと共存してきたのです。しかし、1999年に研究者と捕獲業者が一緒になって当時の環境庁に、ワイルドライフマネジメントを導入させることに成功してからというもの、生息推定数や適正生息数などを出すために、野生動物を捕まえて残酷な手法で痛めつける調査が、学者の論文用研究や業者の仕事として誕生し、今や、これらが普通となり、研究者には研究費が、業者には仕事や利益が降りる利権になってしまっています。
野生動物を保護するためには、本来、生息推定数や適正生息数など必要ありません。私たちの祖先は、そんなことは誰も知りませんでした。しかし、広大な生息地を保証することによって、見事にかれらを守りかれらと共存してきたのです。しかし、1999年に研究者と捕獲業者が一緒になって当時の環境庁に、ワイルドライフマネジメントを導入させることに成功してからというもの、生息推定数や適正生息数などを出すために、野生動物を捕まえて残酷な手法で痛めつける調査が、学者の論文用研究や業者の仕事として誕生し、今や、これらが普通となり、研究者には研究費が、業者には仕事や利益が降りる利権になってしまっています。
当協会の活動は、戦後、人間が壊した動物たちの奥山生息地を復元して、人間との棲み分けを復活させ、共存を取り戻すのが目的ですから、正確な生息推定数や適正生息数の計算などは、人間が出せるものでもないし、出す必要もないのです。しかし、ワイルドライフマネジメントに利権を持つ人たちが現在次々と誕生し、学術捕獲だ有害捕獲だとして、クマなどの野生動物を捕まえ、全身麻酔をかけて、いじくり回しています。わたしたちは、野生動物に手をかける研究法など、倫理上認められないし、大型野生動物研究としては邪道であると考えます。研究が、時々相手を死に至らしめても、最近の研究者たちは平気なように見えます。
おかしい。どこかが狂ってしまっている。
どうしても調べたいのなら、研究対象に手をかけない方法で調べるべきだ。クマのような高等動物は考える力があるので、工業製品の物の様に無感情には動かない。よって、再捕獲法などによる生息推定数がどれほどの信ぴょう性を持つのか、はなはだ疑問です。本当は、自然界を数字で表す必要はないし、表すことも不可能。数字で表わしたら嘘になるのですが、一方で、どんどんと数字発表を行い、行政を取り込んでいくワイルドライフマネジメント派がいます。かれらの、クマがいっぱいいる発表に対抗するためには、熊森のこれまでの痕跡調査を、今後どうしていけばいいか。専門家の話を聞こうという事になったのです。
この日の研修会の中身は、すばらしく、クマ調査を行おうと思っているくまもり全スタッフに聞いて頂きたい内容でした。何らかの方法で、全国のスタッフの皆さんにお伝えしたいと思っています。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ