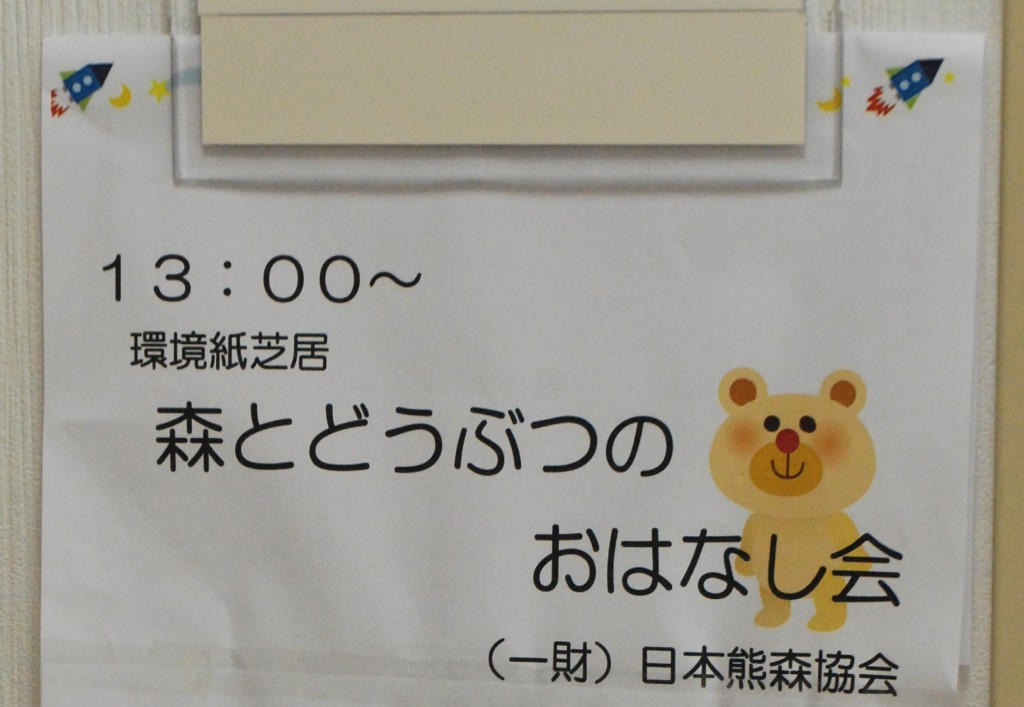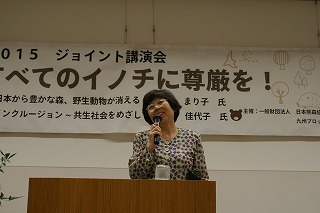くまもりNews
7月10日 幼獣グマは捕獲後山奥に放獣をと、市担当者に願い出る→去年から市の嘱託職員である捕獲隊員(猟友会員)が拒否③
この幼獣グマが殺処分されそうになっているのは、市の意向によるものと判断した熊森は、4名で市の担当者を訪れました。事前にアポをとったところ、午後3時に来るようにと言われました。
午後3時にお伺いすると、いきなり、4時から次の公務が入っているので、1時間で終わらせてくださいと行政担当者に言われてしまいました。
熊森はあわてて、今回の幼獣グマを殺処分する必要などないと思うのに、なぜ殺処分を決定されたのか、行政担当者に聞き取りを始めました。しかし、この後、何を聞いても、質問に答えられたのは、行政担当者ではなく、全てが、去年から嘱託職員となったという捕獲隊員(猟友会員)の方でした。
この捕獲隊員が、このクマを殺処分しなければならない主な理由を6点あげられましたが、私たちにはどれも疑問で納得がいかないものばかりでした。
熊森から
行政担当者は、ふつう3年で部署が変わるので、一つのことに専門知識を持つのは難しいかもしれませんが、
捕獲隊員に任せずに、しっかり勉強して、行政担当者として自分の頭で考えて責任を持って答えていただきたかったと残念に思いました。
この後、熊森はみんなで現地や旅館街を再び見てまわりました。
住民のみなさんは、もし、幼獣を見つけたら、どんなにかわいくても、心を鬼にして怒って欲しいと思います。棒を持って追いかけまわしてもらっても良いと思います。食べ物は絶対に与えないでください。クマは、山に逃げて帰るはずです。
集落近くに設置された罠の蜂蜜の匂いは、何キロ先ものクマを旅館街に呼び寄せていることにもなります。
この幼獣がかかったら、絶対に山奥へ放獣してやって欲しいです。
地球環境を保全し、持続可能な文明を取り戻すためには、日本人ひとりひとりが自然や生き物たちへの共感をとりもどしていかねばならないと思います。
この件は、県の本庁に訴えるしかないと思いました。
7月8日 殺処分ではなく奥山放獣を 幼獣グマが目撃された旅館街の現地調査と県出先行政への申し入れ②
さっそく、現地を調査してみようということになり、熊森本部から6名が出かけて行きました。
旅館街の裏がすぐ山です。どこから幼獣グマ出てきたのか、みんなで手分けしながら探し歩いてみました。
裏山は放置された竹林が繁茂しており、近年はあまり人が入っていない感じでした。
裏山
民家のすぐ近くの裏山にある空家の前に、クマ捕獲罠が設置されていました。(2基)
誘引剤は、ハチミツや蜂の巣、魚の頭でした。
裏山に登って、旅館街を見下ろしてみました。旅館街がどんなところか見に行ってみようと思った幼獣グマの気持ちがわかるような気がしました。人間に親しみを持ったのかもしれません。
地元の人達の声も聞いてみようと思い、「幼獣グマの目撃が数回あったそうですが・・・」と旅館街で旅館の人や観光客十数人にインタビューをしてみました。一部、早く殺してしまってくれと言う人もいましたが、旅館の人達も含め、多くの方は、捕まえたら山に逃がしてやったらいいと、優しい気持ちで答えておられました。
クマとの共存を進めるために、なんとか殺処分を撤回して、山に放獣するように変えてもらえないかと、熊森は殺処分許可を下した県の出先機関を訪れました。お忙しい中、2時間50分も対応いただきました。
しかし、捕獲されたら奥山に放獣してやってほしいとお願いし続けましたが、殺処分撤回は、して頂けませんでした。
<行政担当者が語った、殺処分を撤回しない理由>
・一旦許可を出した以上は動かせない。
・市が人身事故の恐れがあると言っている。
・防犯カメラにこのクマが写っていた。(熊森には見せてくれませんでした)
・クマは数が増えすぎている。
・土地の所有者の関係で、電気柵設置や藪の刈り払いがむずかしい。
・ここは、観光地なので、特例である。
<熊森から>
県の規定では、クマが山から出てきた場合、いきなり殺処分するのではなく、まず、誘引物の除去、防除、追い払い等をすることになっています。しかし、今回の場合、誘引物が不明なのと、観光地という特殊性のため、いきなり殺処分になったようでした。
熊森としては、幼獣を捕獲して殺処分してしまうより、捕獲して山奥に逃がした方が、一般に観光地としての評価は上がると思います。
兵庫県のクマが増え過ぎているというのは、ある研究者がコンピューターを使って長時間計算した結果、クマが近年爆発増加していると発表されたことによるものです。しかし、生息地の森が、人工林、ナラ枯れ、シカの食害などにより、ことごとく失われていっているのに、なぜ生息数だけが爆発増加できるのか、私たちはこの研究者の推定生息数に大変疑問です。
7月6日 クマ生息地の旅館街で5月より幼獣グマの目撃が数回あり、行政は捕獲→殺処分に向け、箱罠2基を設置①
兵庫県(7月16日、県庁担当部署である兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課 電話:078-341-7711 FAX:078-362-3069から公表して良いと言われました)のクマ生息地の旅館街で、幼獣グマの目撃が数回あり、行政は捕殺に向けて、7月2日、鉄製箱罠2基を仕掛けました。
<旅館街における幼獣グマの住民目撃情報記録> (行政発表)
●5月13日 早朝6:10
幼獣をちらっと見た。
●6月20日 真夜中1:40
幼獣をちらっと見た。人に気づくとすぐに逃げた。
●6月24日 早朝7:35
幼獣をちらっと見た。人に気づくとすぐに逃げた。
●6月30日 早朝7:15
幼獣をちらっと見た。人に気づくとすぐに逃げた。
●6月30日 夕方17:50 幼獣をちらっと見た。
(行政は、この時点で、幼獣グマ捕殺を決定し、檻2基を設置)
●7月3日 夕方17:00
幼獣をちらっと見た。人に気づくとすぐに逃げた。
(熊森から)
独立直後の若グマの下界調査
1歳半の子グマは、6月のキイチゴが実る頃、母グマが交尾期に入るため母グマから放されます。母グマから独立したばかりのオスの幼獣は、どのあたりで今後暮らしていこうか決めるにあたって、しばしば人里にちらっと顔出しします。しかし、それは、人里に棲もうと考えたわけではなく、ただ、山の下がどんなところか見ておこうと思っただけで、自分なりに納得すれば、8月頃には山奥に帰り、その後は、奥で定住するようになります。
人間は寛容の精神を
旅館街で数回目撃された上記幼獣も、そのたぐいであると思われます。この程度で捕殺してしまうのであれば、「クマとの共存」などとても不可能です。もう少し行政には、寛容の精神を持っていただきたいと思います。
クマの棲める森があるからこその風光明媚
行政は、観光地であり旅館街であるという特殊性からの殺処分判断だという事でしたが、周りの山がクマの生息地であるという自然の豊かさが、人気の観光地としての風景を生み出しているともいえます。
風評被害を恐れる現地に熊森も配慮したい
現地では、旅館街に幼獣グマが顔出したことが広まれば、客が来なくなるという不安があるそうです。ならば、熊森としては、現地にも配慮したい。捕獲は仕方がないと思いますが、殺処分するのではなく、奥山放獣をお願いしたいと思います。
クマヘの誤解
地元では、人身事故発生の危険性を恐れる声もあるそうですが、あまりにもクマという動物を誤解されていると思います。幼獣が、人身事故を起こした例を私たちは知りません。もし罠にかかったら、殺処分せずに、奥山に放してやってほしいです。この地域では、クマは、絶滅危惧種であり、保護動物と規定されているのです。
変えていくのは私たち
以前、C・W・ニコル氏が、日本人はいたいけない子グマまで殺してしまうが、どうしてそんなかわいそうなことが出来るのかわからないと言われていたのを思い出しました。確かに、日本では、赤ちゃんグマであっても、見つけたら殺してしまうところは現在多くあると思います。しかし、猟師仲間に「3つグマ獲るな」という言葉が残っているぐらいですから、祖先は、厳しい自然のなかで一生懸命生きている野生動物たちに、同じ生きとし生けるものとして共感し、優しい気持ちを持っていたと思います。日本を変えていくのは、今を生きる私たちなのです。
北秋田市の「熊森」と「くまくま園」ツアーの下見(1日目)
経営破たんした元秋田県八幡平クマ牧場に残されたクマたちは、熊森の運動もあって、秋田県に全頭救命していただき、現在、北秋田市立阿仁クマ牧場「くまくま園」で終生保護飼育されています。
2014年7月19日にオープンした「くまくま園」はこの度、無事1周年を迎えることができました。1年目は黒字経営だったそうで、よかったです。
熊森本部は、動物愛護の精神を日本人が思い起こすためのシンボルとしての「くまくま園」と、秋田のクマたちが棲む豊かな「熊森」をセットにしたツアーを企画していきたいと思っています。
この度、本部から会長をはじめとする10名、東京都支部・神奈川県支部から各1名、計12名でツアーの下見に出かけました。
7月18日(1日目)
関西組は、7:05大阪伊丹空港発。関東組は、8:55羽田空港発。10時半に秋田県大館能代空港にそろって到着。
マイクロバスに乗車し、現地の自然保護団体「冒険の鍵クーン」さんのガイドで、まず森吉山山麓高原に向かいました。
昼食後、青少年野外活動センターで、この辺りの森で自動撮影カメラで撮影されたクマたちの写真をいろいろ見せていただきました。
その後、実際にクマが撮影された自然豊かなブナ林を案内していただきました。
ガイドさんのお話によると、この時期は親離れをした若グマたちがいろんな場所を試しに歩く時期なので、一年で最もクマをよく見かけるそうです。
今にもそのあたりからクマが出てきそうで、どきどきしました。

ガイドしてくださった方の説明がとてもすばらしかったです。ツアーの時もこの方にお願いしたいと、一同思いました。
午後4時に、この日の宿舎である打当温泉に着き、荷物を置いてから「くまくま園」に行きました。
この日は4頭のメスのヒグマが運動場に出してもらっていました。
このあと、全頭のヒグマが個室に入り、食事時間となりました。
どのヒグマも、ガツガツとうれしそうに食べていました。
飼育員さんによくなついて、甘えていました。
みんな元気そうで、いい表情をしていました。

近くで見ると、やはりとても大きいです。
飼育員さんがヒグマたちに深い愛情を持って接してくださっているのが、よく伝わってきました。
日々のお世話、ほんとうにありがとうございます。
宿舎に帰って夕食後、入浴、マタギ資料館見学、交流会などを持ちました。
7月30日とよ君の世話
- 2015-07-31 (金)
- くまもりNEWS | 豊能町誤捕獲クマ「とよ」
毎週木曜日に大阪府豊能町高代寺で飼育されている「とよ」の世話には、北大阪や兵庫の阪神地区の会員さんらが参加してくださっています。この日は、本部からも1名参加しました。
「とよ」が高代寺に獣舎へ移って、まもなく4ヶ月です。
この間、新しい獣舎に慣れるだろうか、エサは何を食べるだろうか、世話をする高代寺の方々 と熊森会員、参拝者の方たちに慣れるだろうかなどいろいろと心配がありました。
「とよ」は幸い、新しい環境には慣れてきましたが、食べ物については今も試行錯誤が続いています。
「とよ」は捕獲された 時に4歳でしたので、自然の中である程度の好みができていると思われます。また同じ食べ物でも、季節(時期)によっても食べたり、食べなかったりします。
普段はクマフードと果物を与えていて、私達が世話に行く日は果物を中心に与えています。
会員のHさんの車には、エサとワラと水が満載
獣舎横で打ち合わせ
フンの数と量を記録しています
汚れたワラを交換しています。
プールの水を入れ替えるために、ゴミをすくい取ります
プールを洗った後に、持ってきた水を入れます
今日のエサはブドウとキウイとバナナとモモです。
イチジクは食べませんでした。
掃除が終わって、「とよ」を運動場に戻すと、さっそくプールに飛び込んで、ゴクゴクときれいな水をおいしそうに飲んでいました。獣舎のステンレス容器には、常時、水を入れてありますが、どうも、プールの水を飲むのが好きなようです。
約2時間の掃除の後、獣舎前で記念撮影。お疲れさまでした。
現在のところツキノワグマの世話に慣れた会員さんを中心にお世話していただいています。もう少し「とよ」が人間に慣れてきて怖がらなくなってきたら、新たなメンバーの方にもお世話に参加していただこうと思っています。(tsy)
(7月25日)芦屋市のフェスタで紙芝居上演
- 2015-08-07 (金)
- _環境教育
先日、兵庫県芦屋市で開催されたフェスタに、
本部環境教育チームで参加しました。
この日は、夏空が眩しい絶好のお祭り日和。
参加者の子どもたちは、会場横の河川敷で遊んだりしていました。
私たちは室内での上演でしたが、太陽の下で遊ぶ子どもたちを見て
夏休みのわくわく感が懐かしくなりました。
今回は、紙芝居2本とクイズあわせて80分のプログラム。
紙芝居は「どんぐりのもりをまもって」と「ぴっちゅんとぱっちゃのぼうけん」です。
水プログラムで恒例の、水はどこから来るのかな?クイズでは、
海・池・川・井戸・雨・土・ダム・・・といった意見が集まりました。
毎回、様々な意見が出てきて、面白いです。
中には、熱心に発言してくれる子も。(全部聞けなくてごめんね)
学校での環境教育とは違い、参加者の子どもたちはみんなリラックスモード。
楽しいお祭りの中の、ちょっとした学びの場になれたのかなと思います。
夏休み中には、今のところあと2回、環境教育を控えています。
子どもたちの、夏休みの楽しい思い出に残るものとなるよう、チーム一同頑張ります。(SY)
クロちゃんツアー申し込みは7月6日まで
- 2015-07-06 (月)
- 企画・イベント
7月25日~26日山形県のクロちゃんに会い、育ての親の佐藤さんのお話を聞き、月山の深い森を散策するツアーがあります。
5月にもご案内をしましたが、まだ残席があります。
参加申し込み締め切りは7月11日まで延長しました。
ぜひ、ご参加ください。
<山形の月山体験とクマのクロちゃん対面ツアー>
期日:平成27年7月25日(土)~26日 一泊二日
会費:お一人 32,800円 [最少催行人員10名]
集合:山形空港午前8時50分 山形駅午前10時20分
解散:山形駅前午後3時40分 山形空港午後4時30分
行程:
1日目 山形空港/山形駅~山形中央IC~月山IC~志津温泉(昼食)~県立自然博物館ネイチャーセンター(インタープリターの説明での体験コース)~佐藤宅(クロちゃんとの出会い)~田麦荘(夕食・懇親会)
2日目 田麦荘~あさひ~羽黒手向・・・五重の塔(ガイド先導)~七ツ滝(日本滝100選の一つ)~田麦荘(昼食)~中台池~月山IC~山形中央IC~山形駅/山形空港解散
申込み先:日本海トラベル 電話0234-43-4312 担当 五十嵐 7月11日締め切りです。非会員の方もぜひご参加ください。
第4回日本奥山学会聴講者募集中
- 2015-07-06 (月)
- お知らせ(参加者募集) | くまもりNEWS
8月23日(日)、第20回くまもり原生林ツアーを開催します!
- 2015-07-06 (月)
- くまもりNEWS
来る8月23日(日)に、第20回くまもり原生林ツアーを開催します!!(↓クリックすると、大きくなります。)
現在、日本の山々はスギ・ヒノキの人工林で埋め尽くされてしまっている状況ですが、かつて日本の山には多種多様な植生環境があり、そこには多くの動物の姿が見られる原生林がありました。
今、日本に残る数少ない原生林の一つが、この若杉原生林(岡山県西粟倉村)です。子どもからご年配の方々まで、多くの方々にこの山を見てもらい、かつての日本にあった「原生林」がどのような場所であるかを体感していただけると幸いです。
先着30名様ですので、お早めにお申込み下さい!ご予約は、電話・FAX・メールにて承っております。
電話:0798-22-4190
FAX:0798-22-4196
メール:contact@kumamori.org
多くの皆様のお申し込みをお待ちしております!
6月28日 九州ブロック主催 くまもりジョイント講演会
- 2015-07-13 (月)
- くまもりNEWS
「熊森」森山まり子会長と「勇気の翼 インクルージョン2015」理事長細川佳代子さんの初のジョイント講 演が実現しました。
福岡県の180人会場場いっぱいにお客様がお集まりくださいました。(参加費千円)
開会と同時に、「どうして困っている人や動物たちに手を差し伸べないのか」と心からの叫びで訴える10歳のイギリスの男の子の歌「Tell me why」が流れました。
細川さんも、いい歌ですねと聞き入っておられました。
この後、細川さんは人生をかけ支援してこられた知的障害者のオリンピックであるスペシャルオリンピックスについて生き生きと話 されました。
スペシャルオリンピックスを支えるためには、熊本にいるだけではだめで、東京へ行かなければならないと思いつめていたら、本当に東京へ引っ越せすことになった(首相官邸)話など、細川さんは本当に魅力的な大スターで、参加者のみなさんには大いに講演を楽しんでいただけたと思います。
この後、森山会長が、科学技術というものは、元々地球上になかったもので、私たちの生活を便利に楽にしたけれど、その一方で必ず、わたしたちの命を育んできた地球環境を破壊し汚染するものであり、歯止めをかけなければ、他の生物はもちろん人類も生き残れなくなるという話をわかりやすくしました。
最後に、宮崎中央新聞の松田くるみさんの司会で対談をしました。
出演者も参加者も、最後まで楽しめたと思います。
福岡県・宮崎県・鹿児島県・熊本県の熊森スタッフの皆さん、演出、会場設営、司会、運営、どれもすばらしかったです。ありがとうございました。
 くまもりHOMEへ
くまもりHOMEへ
















![DSCN4154[2]](http://kumamori.org/news/wp-content/uploads/2015/07/DSCN41542.jpg)